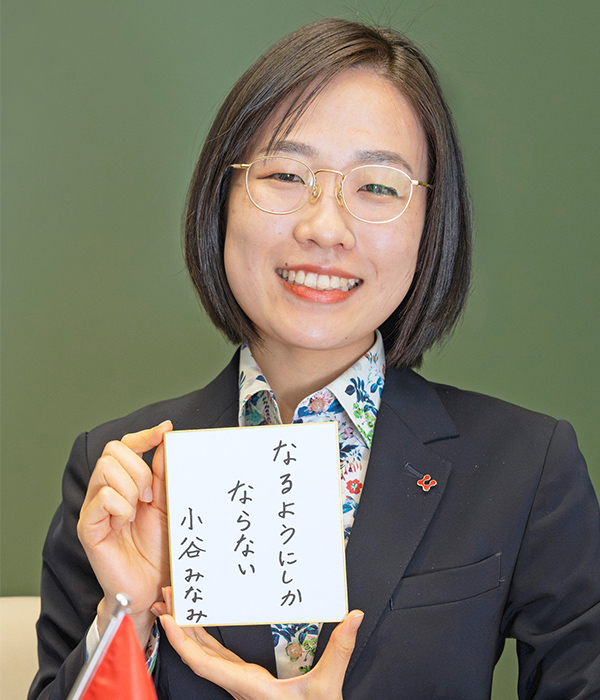東大で初めて知った「わからない」という感覚と「わかる」喜び
 幸い勉強は得意なほうで、ゲーム感覚で取り組んでいました。今考えるとすごくイヤな生徒だと思うんですけど、先生の傾向と対策を考えて、同級生に「あの先生だったらこれを出すと思う」というようなことを言ったりしていました。ですから、本当の意味で勉強に苦労したのは大学に入ってからかもしれません。私はどちらかというと文系科目が得意だったのに、無理して理系に入った口。「わからない」という感覚が初めてわかり、そのぶん「わかる」ことの喜びも初めて知りました。
幸い勉強は得意なほうで、ゲーム感覚で取り組んでいました。今考えるとすごくイヤな生徒だと思うんですけど、先生の傾向と対策を考えて、同級生に「あの先生だったらこれを出すと思う」というようなことを言ったりしていました。ですから、本当の意味で勉強に苦労したのは大学に入ってからかもしれません。私はどちらかというと文系科目が得意だったのに、無理して理系に入った口。「わからない」という感覚が初めてわかり、そのぶん「わかる」ことの喜びも初めて知りました。
「スペースコロニーを作りたい」という夢(前編参照)からは当然、専攻は航空宇宙工学科に進むはずだったのですが、おそらくそこでの勉強に私はついていけないだろうと思っていました。当時一番好きだったのが「化学」でしたので、私の場合はその分野から宇宙方面の仕事ができたらいいなと思っていました。
それにしても東大の理系の方は「わからない」への追究がすごかった。一方の私は、浅いところで納得してしまう。とはいえ、今さら文系の人たちの頭の回転の速さや事務処理能力で勝負できない。そんな感じで、私は文系と理系の間をずっと探っている、いわばモラトリアムだったと思います。でもそのモラトリアムがあったからこそ、今サイエンスコミュニケーターという仕事をしているんだろうなとも思うのです。思わぬところに宝は転がっていたと。
もし子どもを理系に、科学好きにさせたいと願うなら、まずはお父さんとお母さんが科学に興味を持ってほしいです。「理系は苦手」というのは思い込んでいるだけの場合が多い。「カソウケン(*)」の掲示板で感じたことですが、理系が苦手だという人ほど鋭い質問をされるんです。「卵を使った後の容器に水をジャーっと注ぐと泡立つのですが、これは界面活性剤と関係ありますか?」とか。これは実際にそうで、卵黄の中にはレシチンという界面活性剤が入っているんです。じつは「理系は苦手なんですけど……」とおっしゃる方にそういう素晴らしい見立てをされる方が多いので、まずは「苦手」という鎧を取り払って科学と向き合ってみてはいかがでしょうか。
*カソウケン…内田さんが運営する“家庭総合研究所”サイト。記事末尾の関連リンク参照
東日本大震災で知った自分の無力さ
 一方で、科学が「苦手」ではなく「嫌い」とおっしゃる方もいます。科学は人間の直感とは異なるものだからだと思います。たとえば地球が太陽の周りをまわっていると言われても、直感ではわからないじゃないですか。同じように、地球の自転も、地球が丸いというのも、直感ではわかりづらい。だから科学を学んでいくにつれて苦手になっていったり、災害や環境汚染を想起するから嫌いという方もいらっしゃいます。そういう方たちに対して、押しつけがましくならない科学コミュニケーションの方法を、いまは探っている最中です。
一方で、科学が「苦手」ではなく「嫌い」とおっしゃる方もいます。科学は人間の直感とは異なるものだからだと思います。たとえば地球が太陽の周りをまわっていると言われても、直感ではわからないじゃないですか。同じように、地球の自転も、地球が丸いというのも、直感ではわかりづらい。だから科学を学んでいくにつれて苦手になっていったり、災害や環境汚染を想起するから嫌いという方もいらっしゃいます。そういう方たちに対して、押しつけがましくならない科学コミュニケーションの方法を、いまは探っている最中です。
2011年の東日本大震災で、自分の無力さを痛感したということもあります。おそらく科学に関わる仕事をしている方々も、「どうして自分がこんなに役に立たないのか」を考えたのではないかと思います。何より科学技術に対する信頼が高すぎました。そして自然や原発など、コントロールしきれないものをわれわれ人間は扱っていたんだということを思い知らされました。当時から私たちの仕事の中には、原発に関する情報提供や放射能に関する解説をされている方もいて、私もそういうことを書くべきなのか悩んでいました。
そのときはちょうど東京・中日新聞で「おうちの科学」という連載をしていたんですね。震災や原発からは遠いテーマを扱っていたので、「いま私はそれを書いている場合なのでしょうか?」と新聞社の担当者に尋ねたんです。でも「ぜひそのまま続けてください」と言われて、結局一回も途切らせることなく書かせていただきました。私はサイエンスコミュニケーターとして、いま直面する問題に直接的な働きかけはできないけれど、エンターテインメントとして少しでもホッとする情報を担おうと考え始めたきっかけでもありました。
「役に立つ・立たない」ではない、文化としての科学を
 家事の失敗から「見えない科学」を見つけたとき、私の世界は変わりました。世の中の見方が変わりました。そういう意味での「科学」を、専門家ではない人たちにも楽しんでもらいたい。映画を観たり、本を読んだり、音楽を聴いたり……そのちょっとした経験でパァっと目の前が開ける瞬間があります。そういう“新しいメガネ”をかけたような科学の楽しさをもっと広めていきたいと考えています。役に立つ、立たないという視点ではなく、文化としての科学を広めたいですね。
家事の失敗から「見えない科学」を見つけたとき、私の世界は変わりました。世の中の見方が変わりました。そういう意味での「科学」を、専門家ではない人たちにも楽しんでもらいたい。映画を観たり、本を読んだり、音楽を聴いたり……そのちょっとした経験でパァっと目の前が開ける瞬間があります。そういう“新しいメガネ”をかけたような科学の楽しさをもっと広めていきたいと考えています。役に立つ、立たないという視点ではなく、文化としての科学を広めたいですね。
学ぶことは喜びであり、自分に力を与えてくれるものだと思います。だから、学び続けていくことは人生を生きることと同じこと。以前、ある沖縄のドキュメンタリー番組を観て感銘を受けました。それは戦中、戦後と学校に通えなかった高齢者の方たちが再び学校で学ぶお話だったのですが、その方々が学校で学んだことにより「外に出るのが楽しくなった」「自分に自信がついた」「手紙を自分で読めるようになった」と本当に嬉しそうに語るんですね。やっぱり学びはエンパワーメント(※人に夢や希望を与えて勇気づけ、生きる力を湧き出させること)なんだなって。子どもたちは「どうして勉強しなきゃいけないの?」って思うこともあるかもしれませんが、“勉強していると自分に自信が持てるよ”、“自分のことが好きになれるよ”と強く伝えたい。
これは私の体験でもありますが、人生うまくいかなかったときほど、後に何かを拾えます。私はそれを信じ続けてやってきました。無駄なことはひとつもない、すべてはつながっているから。人生に迷ったときは、自分がたどってきた点を線につなげられるようなことを考えてみるのもひとつの手だと思います。うまくいかなかったときを自分の転機と思えるかどうか。先が見えないときほど自分を客観的に見つめてみるといいですよ。科学とはいつもそばにいて、私たちを助けてくれるものです。多くの先人たちが「非常識」と言われながらも研究を積み重ねて、今の科学や常識があります。科学はいわば人間の好奇心の結晶。だからこそ、より多くの人たちにこの楽しさ、おもしろさ、素晴らしさを伝えたいのです。
関連リンク 内田麻理香:カソウケン(家庭科学総合研究所)
 |
前編のインタビューから -主婦として家の中で再会した「普段着の科学」 |