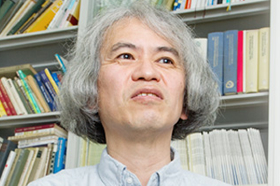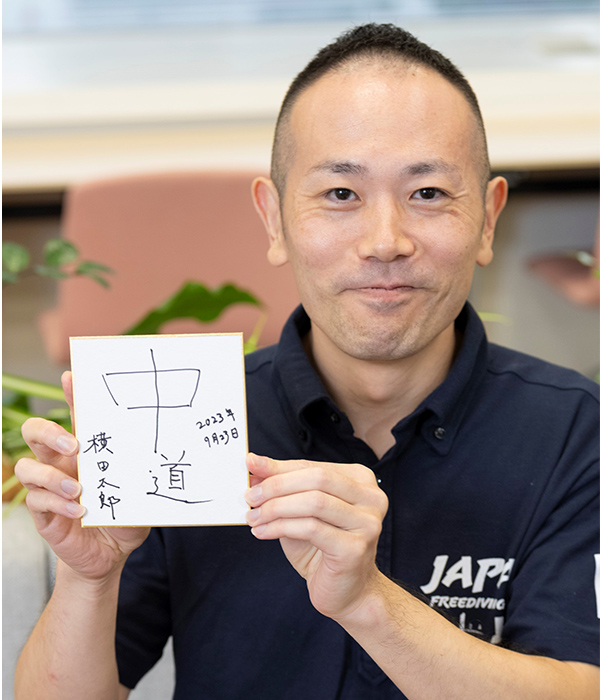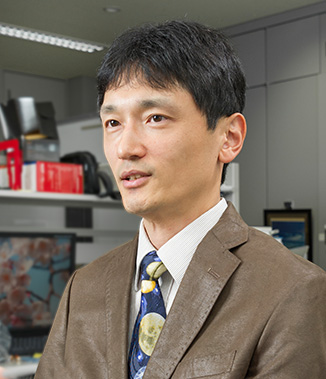紙の上で、自分で100%解き明かせるのが数学の魅力
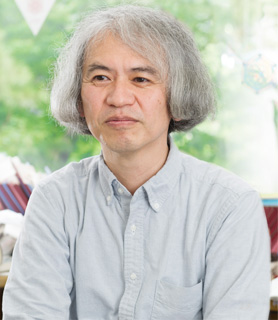
誰もやったことのない領域に挑戦するというのは、楽しいのと同時にしんどいこともあります。そんなとき、自分に言い聞かせるのは「なるようになるだろう」です。だから私は、あまり心配することはありません。というより、あれこれ心配する前に、歩いているとき、電車に乗っているとき、ホワイトボードに向かっているとき、つねに頭には数式があり、それをどう解こうかと考えてしまうからでしょうね。
解きたい問題があり、それを四六時中考えていてもヒントすら見つけられないのに、寝ているとき突然アイデアが思い浮かんで慌ててメモを取るようなこともあります。ただ、そうやって研究していても、解きたかった問題をほかの研究者に先に解かれてしまうこともある。悔しいです。そういうときは「だったら別のものを解けばいい」と切り替えます。数学の楽しさは何より解けたときの喜びにあります。それは、たとえばパズルを解けたときの快感と似ています。でも、パズルであれば作った人がいて、その人は答えを知っている。しかし、研究レベルの数学の場合は、これまで世界で誰も分からなかったことを自分が解き明かすわけです。より嬉しいじゃないですか。
どういった分野の学問でも同じでしょうが、困難であればあるほど、成し遂げたとき、その喜びは大きくなります。数学も研究の途中で挫折する人が少なくありません。しかし、突き詰めれば非常にシンプルで魅力的な学問なのです。すべて理屈がついて、紙の上で100%、自分で解き明かせる。私は昔から数学のそういうこところが好きでした。
理科なら実験や観察をしないと分からないことも多い。もちろん全ての実験や観察を自分ですることは不可能だから、テキストや論文に載っている結果を信じざるを得ません。けれども、数学なら100%納得しながら前に進める。極端なことを言えば、年令も性別も国籍も関係ない、数字の前にはみんな平等なのですよ。さきほどお話しした「なるようになるだろう」という言葉には、「必ずいつかは解ける」という、非常に数学的な真理も含まれているのかなとも思っています。
「学ぶこと」は最良の社会貢献
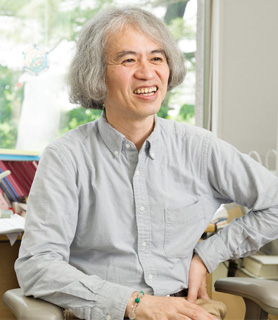
趣味と呼べるほどのものではありませんが、仕事で年間の1/3は海外にいるので、外国の街をぶらぶらと散歩するのが心休まる時間ですね。特にローマは、ローマ大学の先生と共同研究をしていることもあって、とても好きな街です。近代的な都市よりもヨーロッパの古い街並みに心惹かれます。それぞれの時代で人々が努力して一所懸命作ったものが好きです。数学以外の教科で好きだったのは古文漢文。昔の人の考え方って面白いですよね。その時代その時代の最先端の技術が見えるもの、人間が努力して築き上げたものが好きなのです。芸術も文学も、もちろん数学もそのひとつだと思います。
海外の研究者とのやり取りはもちろん英語ですが、数学の英語って実は簡単です。なぜなら、使う単語は専門用語ですし、言い回しもほぼ同じだからです。学会の英語での講演よりファーストフード店で注文するほうが難しいと思います、焼き方やマスタードの有無などを聞かれますから(笑)。もっと言えば、数学そのものが「共通言語」なのだと思います。インターネットで外国の研究者たちと数式でやり取りをしていると、言葉のコミュニケーションはないのに相手の気持ちが分かったりするのも面白いですね。
私としては、数学が好きで、とくに研究しているという意識もなく、ある意味遊びに近い感覚でずっと数字と戯れてきました。と同時に、自分だけの使命を、数学という分野で果たさねば、という気持ちもあります。この世の中はたくさんの人の努力によって形づくられていると思います。毎日きちんと食事ができるのも、車や電車で仕事や学校に行けるのも、いろいろな人のこれまでの、そして今の努力によって支えられています。
努力の仕方にはさまざまな方法があるわけですが、多くの人にとってみれば「勉強する」「学ぶ」というのがその一番なのではないでしょうか。私も同じです。もちろんプロのスポーツ選手や芸術家になれるような能力や実力があれば、それが一番いいのでしょうけれど、そういう人は少ないわけです。だから、私たちにとって学ぶことは最良の社会貢献だと考えています。自分が社会の一員としての責任を果たすということです。そして、それを通じて自分でも生きる楽しさを味わう。私も研究していて本当に楽しいです。
もちろん、「学ぶ」というのにも段階があると思います。娘も公文を学習していたのですが、その様子を見ていると、スポーツと同じで、体で覚えるくらいになるまでくり返してできるようになることは大切で、それが「学ぶ」ことの基礎になっていると思うのです。
世界にはまだ分からないことがたくさんある
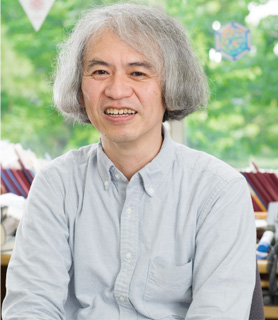
私のことを「天才」などと紹介してくださる方もいるようですが、とてもそのレベルではないと思います。上には上がいますから。数学だけでも、世界にはとてつもない研究者がたくさんいて、そういう本当の「天才」と接すると、悔しいというより、すごいな、嬉しいなと素直に感じるものです。だってニュートンやアインシュタインのような人が目の前にいたら、誰だって興奮しますよね。そんな人たちと同じ時代に、同じ問題に取り組めることに感謝したいです。
そういった天才たちに共通しているのは、好奇心や探求心なのかもしれません。大人になっても、常に新しいことを知りたい、分かりたいというある種の欲望を持ち続けていくことは大切だと思います。それが前に進む原動力になる。そのためには、できる限り子どものような気持ちを持ち続けることです。子どもはいろいろなことに疑問を持ちます。「どうして空は青いの?」とか。そういう気持ちを失わないようにしたいですね。私は「なぜ?」「どうして?」とよく聞く子どもだったそうです。両親はなるべく真面目に答えてくれようとしていたので、それはとてもありがたかったと思います。もちろん、親でも分からないことはあります。分からないことは分からないと言うことも必要です。「いっしょに考えてみよう」と言えれば理想でしょうね。分からないことはこの世界にたくさんあります。それはそれで重要なこと。だからこそ、それを研究する私たちのような人間がいるわけですから。
「数学なんかやって何に役立つんだ?」と言われたりすることもありますが、何に役に立つかどうかはその人しだい。別に数学を使わなくても生きていける……それも正しいことです。けれど、数字や数学は見えないところでもたくさん使われていて、すごく世の中に役立っていると思います。それに、数学ができたら新しい人生の道が開けるし、いろいろなことも経験できます。それは数学に限ったことではなくて、好きだと思うことがあれば、とことんのめり込んで欲しい。そうすれば、その先はきっと「なんとかなる」と思います。
関連リンク
河東泰之|東京大学
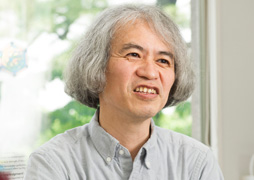 | 前編のインタビューから – 「活字中毒」のように、手当たりしだいに本を読んでいた小中高時代 |