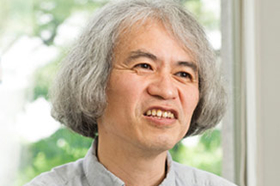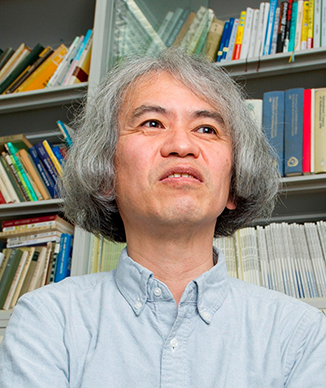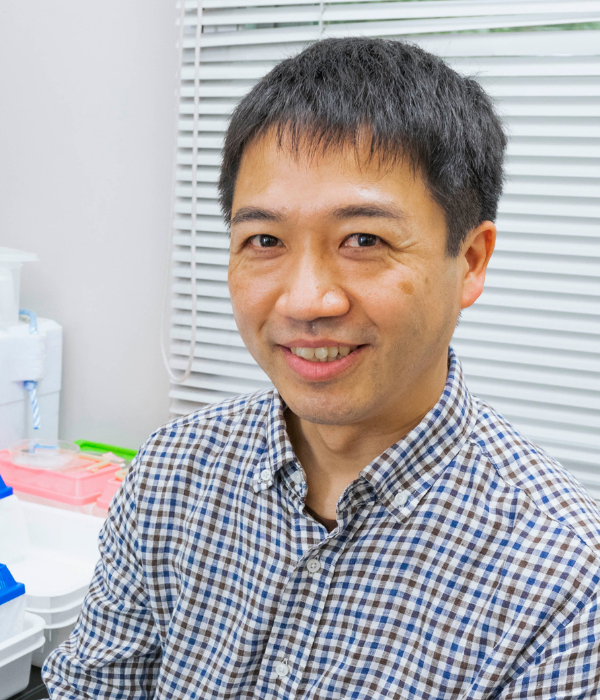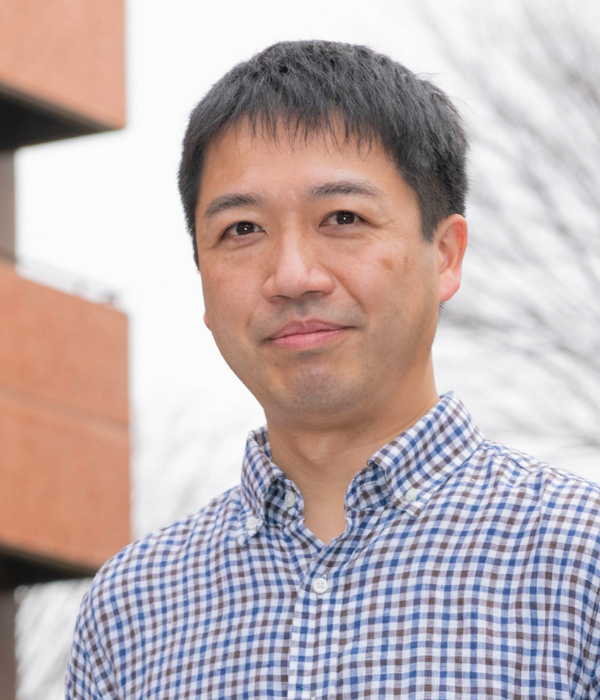手当たりしだいに本を読んでいた小中高時代
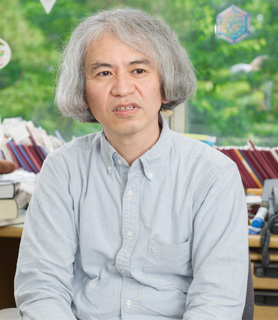
私たちが住んでいるこの空間は、いわゆる三次元空間と呼ばれています。そしてSFなどにも登場する四次元空間。それをさらに次元を上げて“無限次元”にしたような空間も理論的には考えることは可能で、私はそういう空間の構造を研究しています。
抽象的な理論として研究してはいますが、最先端の理論物理学とはそれなりに深い関係があります。たとえば「宇宙がどのようにして誕生したか」「なぜ物質は存在するか」「時間はなぜこのように流れているのか」など、そういうことを突き詰めて考えていくと、最高レベルの数学が必要になってくるのです。
小さいころは……そうですね、勉強は好きでしたね。親から勉強しなさいと言われたこともなかったなぁ(笑)。算数はとても好きでした。小学校にあがる前に四則計算、小6のころには微分積分もできたと記憶しています。それには理由があって、母親が数学が得意だったのです。大学時代に化学を専攻していて、特に計算はものすごく速くて正確。公文の教室の先生をしていたので、私は小6から中1にかけて公文を学習していました。当時は微分積分の教材はまだ手書きでしたね。今から40年ほど前のことです。
本を読むのも好きでした。チョイスするのは主に理科系のものでしたが、特に数学の本は、理解できてもできなくても手当たりしだいに読みました。推理小説もよく読みましたね。新聞も小さいころから習慣的に読んでいました。今でも手あたりしだいに読むクセは抜けません。名著と呼ばれているものをじっくり読むというよりは、なんでもいいから片っ端から読む。読むのも速い。パッと見てみてつまらなそうだと思うと、すぐ読むのをやめてしまうこともしばしばです。胃薬の箱の後ろに書いてある効能書きまで読みこんじゃいますから、たぶん活字中毒だと思います。本ばかり読んで家に閉じこもる私を心配したのか、親からは「スポーツをしなさい」とよく言われていました。
気がつけば、いつも身近に数学があった
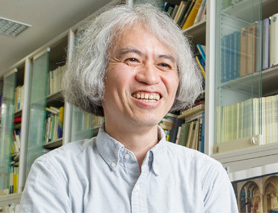
私の家は基本的に良い意味で放任というか、「自分で考えて好きにしなさい」という方針。だから何でも自分で決めなければならなかったです。麻布中学に進学したのも、自分の希望でした。当時でも私立中学受験に熱心な人たちはたくさんいて、そのための塾に通っている子も多かったらしいのですが、うちの両親はそういうことにまったく無頓着でした。私も公立のほかに私立中学があることすら知りませんでした。近所の方が「お宅の息子さんは勉強が得意なようだから受けてみたら」と勧めてくれて、公文をやりながら、そういう塾に行ったら楽しくて、現在の方向に進んだという感じです。ふり返れば、早い時期から自分で選び、その選択に責任を持つことを両親は教えてくれたような気がします。
物心ついてから算数はずっと好きだったので、幼稚園のころから漠然と数学に関係したものを仕事にしたいと思っていました。小学校の作文でも「数学者になりたい」と書いていたほどですから。もちろん、そのころは数学を研究することの意味など分かりませんから、ただ計算が得意な人みたいなイメージだったのでしょうけれど。それでも中学生になると、大学では中学や高校の数学とは違う、もっと抽象的で高度な数学をしている人たちがいて、そういう人は大学で数学を学問として研究していることが分かってきました。そのあたりから、きちんとした意味で数学者になりたいと思うようになったわけです。
小学校時代からクラスのなかでは浮いているほうで、中高時代も友だちとの会話も考えも多少ズレているなと自覚はしていましたが、悩むことはなかったですね(笑)。大学に入り、自主的なセミナーの数学研究会に参加するようになるころから、それがだいぶ解消されました。気がつけば、私の身近にはいつも数学があり、それが心のよりどころになっていたのかもしれません。
まだ誰も見たことのない世界への憧れ
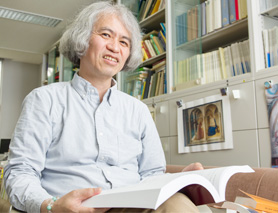
無限次元の空間にはかなり前から興味はありましたが、今の研究領域、作用素環論に辿り着いたのは本当に偶然です。大学4年のころ、ゼミ選択のリストのなかでちょっと面白そうに見えたのと、日本では当時やっている方が少ない、つまりまだ誰もよくわかっていない領域だったというのも大きかったですね。
まだ誰もよく分かっていない領域といえば、当時のマイコン(注:現在のパソコンの創成期の呼称、以下「パソコン」と表記)もそうでした。パソコンに初めて触れたのは中学生のときです。日本で初めてのパソコンで、まだ電卓に毛の生えたような機能のものでしたが、ある日それを父親が買ってきたんです。石油会社で化学の研究をしていた父はアマチュア無線が趣味。加えて、秋葉原に行ってはたくさんの部品を買ってきて、家でテレビまで組み立ててしまうような、いわゆる自作マニアの「秋葉原少年」でした。
パソコンを買ってきたのは父でしたが、使っているのはもっぱら私。それをきっかけにソフトウェアに興味を持ち始めて、高校生のころはかなりのめり込み、パソコン雑誌にトランプやオセロのゲームの原稿を投稿していました。当時はまだパソコンのプロはほとんどいなくて、ふつうの読者が自分で研究したことを編集部に送っては、それがそのまま雑誌に載るような時代でした。
大学に入ってからは編集部の方に声をかけてもらい、ソフトウェアの本を何冊も書くようになりました。一番売れた本は大学3年のときに書いた『PC-9801システム解析(上・下)』(アスキー・テクニカル・バンク)で、その印税で学生生活をしていました。誰もやっていないことを見つけて、それをやるのが好きなんでしょうね。
関連リンク
河東泰之|東京大学
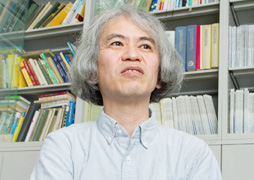 | 後編のインタビューから – 「数学の楽しさは、何より解けたときの喜びにあります」 |