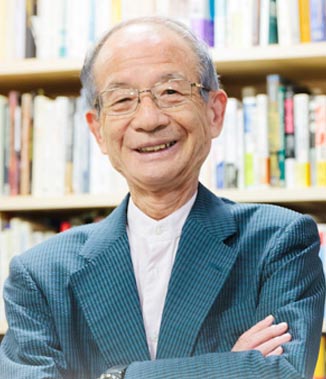寝る間も惜しんで勉強する学生ばかりの中、
どう生き延びるか
 |
1年間の交換留学からの帰国後も、しばらくは「大学卒業後は商社に入ろう」と考えていましたが、野中先生や竹内先生が進めるプロジェクトにリサーチアシスタントとして参画する機会を得るうちに、研究や教育のおもしろさを感じるようになりました。その後、世界的な評価を受けることになる『知識創造企業』のプロジェクトで企業の事例分析を担当したり、日米欧10か国100以上の産業を分析し、各国の競争優位性を明らかにするプロジェクト(のちに経営学者マイケル・ポーター氏の『国の競争優位』として書籍化)のメンバーになったりする機会に恵まれました。
これらを通じ、「ビジネススクールに拠点を置く研究者」にひかれるようになりました。研究活動においては、過去の偉大な企業や経営者に関する知見に触れながら、現代の企業経営の現場における調査に基づき新たな知を生み出していく、また教育活動においては、未来を担う次の世代の若者にその醍醐味を伝え、彼らの人生形成の一端を担うことができる。とても魅力的な仕事だと感じ、この道を目指すことに決めました。
時代はバブル絶頂期。同級生たちは就職活動をしていましたが、私は迷うことなく大学院へ進むことにしました。そしてその後、この道を究めるにはここで学びたいと、ハーバード・ビジネス・スクールへ行きました。
ハーバード・ビジネス・スクールは本当に厳しい世界でした。1学年に900名以上が学ぶ世界最大規模のMBA(経営学修士)
ある時、ある授業でC評価をとってしまいました。その授業では、
なぜそんなことができたか?やはり、
イノベーションを学んできた自分が
学びのイノベーションを牽引する
 |
私にとって「学び」は人生そのものです。「勉強している」という感覚はなく、毎日の生活として、
学生は連携するどの大学の授業にも参加することができます。たとえば、ブラジルのサンパウロにいくと、「Marketing at the Bottom of the Pyramid (最貧困層向けマーケティング)」という授業科目を受講することができ、イスラエルのテルアビブに行くと、「Startup Nation (スタートアップ大国としてのイスラエルのエコシステム)」と題した授業科目を履修することができます。このように、その場に身を置くからこそ学び取れることに焦点をあて、「場」がもたらすイノベーションの論理を解き明かすことを追求しています。
私たちは常に学生に「イノベーション生み出そう」と言っていますが、この取り組みは、教えている自分たち自身がまずはそれを実践しようということでスタートした試みです。このプロジェクトのスピード感も興味深いですよ。年2回、提携校の担当者が集まってアイディアを出して、やってみる。そしてどうだったかを振り返る。これまでにないスピードで仮説・実践・検証をくり返し、プログラムをブラッシュアップさせていこうとしています。私も、日本で学生を受け入れる立場として、「日本に来るからこそ学べる何か」を質高く提供し続けていきたいと思っています。その先頭に私自身が立ち続けていきたいですね。
情報を鵜呑みにせず自分で切り拓いていこう
 |
いまや、人工知能(AI)やロボット工学、ビッグデータ(大規模集積情報)などの進展によって、今人間が行っている仕事の大部分はコンピュータなどテクノロジー
というのも、大人は子どもや若者に何かアドバイスする時、自分たちが生きてきた時代背景を暗黙の前提においている可能性があります。しかし、いま現在のあたりまえが、未来においても当たり前であるとは限りません。就職の相談にしても、周囲の大人がどういうキャリアを積んできたかは参考にはなりません。現時点における成功した方のアドバイスであったとしても、それはその方が過去のある時代において的確な判断をしたに過ぎないわけで、それが今後にもそのまま当てはまるとは限りません。アドバイスする側はそれを意識するべきでしょうし、受ける側はそれを鵜呑みにしないで、自分で考えて切り拓いていくべきです。
私たちの職業も、今と同じ形で残っているかわかりません。テクノロジーの担う部分が大きくなっていったときに、きっと人間である私たちがやるべきことは、より研ぎ澄まされた分野に絞られていくのだろうと思います。テクノロジーとうまく付き合いながら、
そのために、常に世界にアンテナをはり、「今この瞬間にも地球上で誰かが努力している。自分は何をどこまでできているだろうか」という、「地球儀を眺める」ような視点と、常に「上には上がある」という視座を持ち続けていきたいと思います。
関連リンク
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科