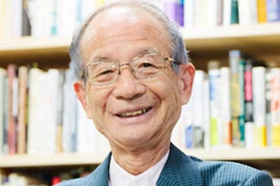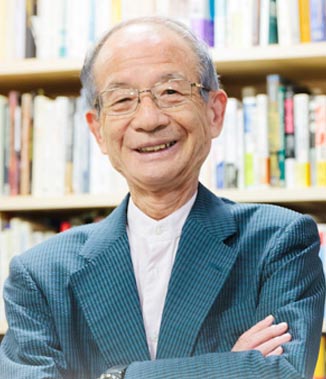経営学とは、生き方を問う学問

私たちは誰でも、自分の経験から得た知識や価値観をもっています。それは言葉では表現しにくいものですが、このように言葉で語り切れない主観的、身体的な経験知のことを「暗黙知」といいます。一方、論理やデータ、マニュアルなど文字化、客観化できる知を「形式知」といっています。
自分の考えや悩みを周囲の人に話したら、共感されたり助言されたりして、考えが変わったという経験はありませんか。これは自分の中の「暗黙知」を、言葉という「形式知」にしていくことで、相手と「暗黙知」が共有され、新しい「知」が創られた結果といえます。企業であれば、個人の中にある経験知や価値観、思いなどを、言葉にして形式知化し合うことで、思いもよらないアイデアが出て、それがヒット商品になることもあります。
このように「知」は、「暗黙知」と「形式知」が絶えずスパイラルに相互作用していく中で創られます。私はこの「知識創造のプロセス」こそが、経営の本質だと捉えています。分析データのような「形式知」だけでなく、思いや信念という極めて人間的な「暗黙知」を合わせまとめながら、新たな知を創りあげていくということです。
こう考えると、経営というのは、単に「企業利益を最大化するための方法」ではなく、「なにをしたいか」「どう生きたいか」ということを究極の目標にしていると考えられます。経営学とは、まさに「生き方」を問う学問なのです。
この「暗黙知と形式知が絶え間なく相互に作用して、新たな知を創造する」という考えを、私は「知識創造理論」として1990年代から提唱しています。長年、この理論を提唱してきたおかげで、今では国内外で知られるようになり、多くの企業で取り入れられています。
ここで重要なのは、一人ひとりの知を、いかに組織的で持続的なものにしていくかということで、人の潜在能力を解き放つことともいえます。これは企業においてだけでなく、家庭や地域コミュニティ、国家、そして世界全体にも必要なことです。
「今にみていろ!」少年時代にアメリカへのリベンジを誓う

実は私は、経営学者になろうと思って一直線に勉強していたわけではありません。少年時代は戦時中でしたから、将来のなりたい職業は軍人以外には考えられませんでした。しかし小学校4年のとき、疎開先で米軍の戦闘機に機銃掃射を受け、九死に一生を得たことが、その後の私の人生を決定づけました。というのも私を追いかけ回した戦闘機のパイロットがニヤリと笑った気がしたのです。私はそれが忘れられず、「今にみていろ!」とアメリカへのリベンジを誓いました。
その後も何になりたいか茫漠としたまま、都立の第三商業高校へ進学します。兄が卒業生で、背広の制服がモダンだから、という単純な進学理由でした。しかし、簿記や珠算には興味が湧かず、得意でもなかったので、卒業が危うくなりました。そこで、心配した先生が進学組に行ってどこかの大学に入れば何とかなるということで、大学受験をすることになったのです。
受験したのは、複数の有名私大の仏文、独文、政治とバラバラで、唯一合格した早稲田大学の政治経済学部に入学しました。しかし、授業にはほとんど出ず、自治行政研究会というサークルで立会演説会の企画をしたり、英語が好きだったのでESSクラブで活動したりと、青春時代を謳歌します。仲間には政治家志望など面白くてクオリティが高い面々がそろっていて、授業よりも彼らとの議論に熱中する日々でした。
この時点でも、特に明確な将来への目標はなく、卒業後は富士電機製造株式会社へ就職します。そこには兄の友人がいて、就職の機会を与えてくれたのです。しかも入社試験の問題が、偶然にも私が好きだった英国の政治学者ハロルド・ラスキに関するもの。ラッキーでしたね。その場その場で流れに乗ってきたわけですが、「アメリカにリベンジしてやる」という思いは心のどこかに一貫してありました。
共稼ぎで貯めた留学資金が株でパーに 何の保証もなく、米国へ

富士電機には9年間勤務し、人事、研修企画、組合執行役員、幹部教育、マーケティング、経営企画と、経営の基幹業務を一通り経験しました。このときの多様な経験が、その後の私に非常に役立つことになります。
最初は工場の人事で、技能者の養成を任されたほか、社員が山で遭難したら捜索隊長として現場へ行くなど、人命にかかわる事故処理も担当しました。工場で初めての大卒採用だったので、「何でもできるだろう」と思われていたようです。労働組合の執行役員にもなりました。そうなると、経営幹部とやりあうために経営問題を勉強しなくてはなりません。ここで初めて経営に触れました。
3年間の工場勤務の後、本社の教育部門に異動し、幹部研修の企画実施に参画します。ハーバード流ケースメソッドを習得された先生を講師に招き、経営幹部と自社の経営課題を議論する機会にも恵まれました。
教育や研修に携わるようになって、私自身も経営手法や経営システムを学ぶにつれ、「また日本はアメリカに負けるのではないか」と思うようになりました。当時の社員教育手法や経営学はすべてアメリカからきたものだったからです。
そこで、「宿敵」の手法を学ぶべく、留学の機会を狙います。だいたいの基幹業務を経験したころ、いよいよ“敵地”に乗り込む覚悟ができました。そこで、手当り次第に願書を送付して、一番早く許可が出たカリフォルニア大学バークレー校経営大学院に行くことに決めました。
ところが職場結婚した妻と共稼ぎで貯めていた留学資金を証券会社の知人に預けたら、思わぬ株投資でほぼ全額パーになってしまったのです。それでも留学の決意は固く、辞職届を人事部長に出しに行ったら、受け取らずに休職扱いにしてくれて、しかも50万円を無利子で貸してくれたのです。妻と船で渡米したのですが、その費用もつてで安くしてもらいました。当時私は32歳。今思えば、これが学者人生のスタートとなったわけですが、当時は何の保証もカネもなく、「アメリカで学べるんだ」という高揚感だけがありました。