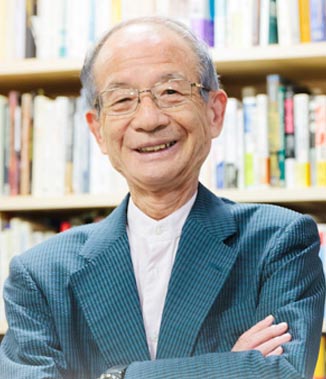「太平洋のアテネ」で理論のつくり方を徹底的に叩き込まれる

アメリカでは、妻がベビーシッターやウエートレスをして稼いでくれたので、私は研究に没頭することができました。
留学前、場所さえ知らなかったカリフォルニア大学バークレー校経営大学院ですが、「太平洋のアテネ」といわれる哲学的な雰囲気が漂うこの大学院で学ぶことができて、本当によかったと思っています。それは、経営学に加えて第二の専門分野として履修した社会学のコースで、理論やコンセプトのつくり方を徹底的に叩き込まれたからです。
西海岸のバークレーに対して、東海岸のハーバード大学の経営大学院は、事例研究をしながら現実の経営の知恵を習得することが柱となっていました。ですから、企業経験があり、現場のことはわかっていた私にとっては、バークレーで「新しいコンセプトを発信する」という能力も鍛えられたことは幸いでした。
バークレーでは、1年間かけて優れた「理論」の事例研究を学び、最後は自分のセオリーを提案するといった全く新しい経験をしました。非常にしんどかったのですが、ドクター論文として提出したものが日本で書籍化され、「日経・経済図書文化賞」という優れた経営図書に与えられる賞をいただくことになりました。こうして学者の一歩を踏み出します。
帰国後は、大学で教鞭を執る一方で、仲間とともに研究を続けました。そこで生まれた数々の論文や著書は、さまざまな賞をいただいています。それはやはり仲間と一緒にやってきたからで、すべて暗黙知と形式知が相互作用した結果といえます。人はネットワークをつくりながら知を生み出していくのです。
リスクを恐れず実践しよう

私のこうした歩みは、私が提唱する経営の本質、「暗黙知という経験、形式知という論理が、絶えずスパイラルに相互作用しながら新しい知を創り出していくこと」にそのまま重なるかもしれません。
富士電機での実務経験は暗黙知を豊かにしてくれて、バークレーではその暗黙知を形式知にすべく理論のつくり方を学びました。そして今も仲間とネットワークしながら、さらに新しい知を創り出すことを続けています。
ただ、振り返ると私の人生は、計画的、分析的だったとはいえません。人生の大事な分岐点において、深刻に情報分析をして選んだ結果ではなく、チャンスが来たら、とにかく動いてそれに乗って挑戦した結果なのです。あとは、「いつかみていろ!」というアメリカへのリベンジという、いたって個人的な経験による思いが原動力でした。
このような自分の体験から言えるのは、客観的で分析的な「形式知」に執着せずに、主観や身体的な感覚(身体知)である「暗黙知」を大事にして、リスクを恐れず実践しようということです。ただ、主観が大事といっても、主観が個人の中の主観にとどまる限りは、普遍にならないし理論になりません。暗黙知の本質をきちっと形式知化して、他の人たちとの間で合意形成をしていく必要があります。言語化することによって、暗黙知はより自覚的に触発され深まっていくのです。両者はスパイラル的に創造的な関係にあるのです。
「リスクを恐れず実践せよ」ということは、企業に限ったことではなく、いまの子どもたちにも伝えたいメッセージです。あまりにも形式知偏重になると、頭でっかちになり、傍観者になるだけで、主体的な実践も行われません。
子どもたちには、まずはからだを動かして、身体知を養ってほしいですね。それから「質の高い経験の場」を意図的につくることです。自分の全身をかけて挑戦する場をつくることが、一番高質の経験となります。経験の質量は、暗黙知を豊かにし、新たな知を創り出す力となるのです。
「ちょうど」の判断が人を育てる

近年私は「フロネシス」という概念を提唱しています。もともとはアリストテレスの概念で「実践知」「賢慮」を意味します。ものごとの文脈の関係性を読み取って、最善の判断に基づきながらその文脈に合う「ちょうど(Just right)」の解を見つけて実践する力といえるでしょう。暗黙知と経験知をスパイラルに回して知を創造するために、大事な力です。
公文で教える先生方は、まさにこの「ちょうどの教育」に長けているといえます。そのときどきの生徒の様子を洞察し、ちょうどいい教育をしているからです。
このように個別に「ちょうど」の判断をして実現に導くことは、究極のマネジメント(経営)であり、それができる先生方は優れたマネジャー(経営者)といえます。優れたマネジャーの元でこそ、人は育ちます。
こうしたことができるのも、生徒を教室に集めて形式知ベースのレクチャーをするのではなく、先生と生徒一人ひとり暗黙知の共感による教育、つまり一人ひとりに直接向き合う教育システムが確立されているからでしょう。直接のケアや対話がなければ、その場その場のちょうどいい判断をすることはむずかしいものです。
家庭においても同じで、子どもとの直接経験や対話が基盤にないと、暗黙知の共有はできません。そうなると文脈を共有することもできないので、知の創造はおろか、「ちょうど」の判断もできません。子どもと暗黙知を共有し、文脈を洞察しながら、質の高い経験をさせる――それが、今後子どもの成長を支援するうえで大切なことではないでしょうか。
時代はダイナミックに動いています。不確実で、偶然が支配する中で生きていくには、関係性を読んで最善の判断をし、実践できる力が特に必要になってきます。身体的感覚を伴う体験、理論や概念のつくり方や教養の獲得など、暗黙知と形式知をバランスよく備えていくことが、これからの子どもたち、私たちの善き未来につながっていくのではないかと思います。