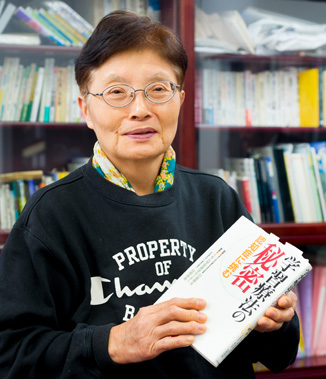赴任した特別養護老人ホームの現状を見て、「これはどげんかせんといけん」

佐賀県の施設のあと、私は父がつくった社会福祉法人に入り、特別養護老人ホーム(以下「ホーム」と表記)で現場の責任者として働くようになります。このホームの当時(平成初期)のモットーは「褥瘡(じょくそう)をつくらない、寝たきりにはしない」でしたが、からだのケアは十分でも、車イスに座ってはいても眠っているような状態はどうだろうと考えました。脳に刺激を与えなければ、痴呆症(当時の呼称、現在の「認知症」)が進んでしまうと直感的に思いました。「これはどげんかせんといけん(これはどうにかしないといけない)」。すぐに佐賀の施設での公文式学習のことが思い浮かびました。
施設内を見まわっていると、チラシの裏に文字を書いている女性の入所者が目に入りました。聞けば、働きづめで勉強するひまもなく、文字が書けないから練習しているというのです。また別の女性は、日々の朝昼晩の食事で出されたものをノートにびっしり書いている。糖尿病で食事制限があるけれど、食べるのが好きで、何を食べたかを忘れないように書いていたのです。
そうした様子を見て、やっぱり公文のプリントに取り組んでもらいたいと思い、希望者を募ると5人くらいが手をあげてくれました。ホームのスタッフにとっては、「高齢者が読み書き計算、それも公文式なんて…」と、当時は不可解だったでしょう。でも私は、かつて佐賀の施設で公文式を導入し、できることをする、ちょうどの学習を重ねることで子どもたちが変わっていくのを目の当たりにしていましたから、「高齢者も変わっていくのでは?」と半ば確信めいたものがあったのです。
もうひとつ佐賀の施設で学んだことは、職員の関わりによって子どもたちが変化や成長をすると、そこに私たちは働きがいや喜びを見つけられました。そうであれば、高齢者介護施設のスタッフも、人生の終末に向かうお手伝いだけでなく、高齢者と密に関わることで、「こんなに楽しいことがある」「自分が役に立ててうれしい」と感じてほしい。そして、そうスタッフが感じられる“舞台”をつくることも私の責任ではないか、と思いました。
5人という少ない人数でしたが、公文の学習がはじまると、文字が書けなかった女性の入所者は、1年後には、慰問に来る幼稚園の子どもたちにお礼状を書けるまでになりました。旦那さんが亡くなったとき、「最期まで世話をしてあげられなかった」ととても悔やんで、葬儀に行くのを拒んでいましたが、「ご主人に最後のラブレターを書いてみたら」と勧めると、何時間もかけて書きあげ、お棺に入れて見送ってあげることができました。
食べたものを毎日メモしていた女性は、公文のプリントが大好きになりました。体調を崩し入院し、そのまま他界しましたが、病院で亡くなる3日前までプリントをしていました。すでに鉛筆を握る力も弱くなっていたので、看護師に鉛筆と自分の指とを輪ゴムで結んでもらい、プリントに向かっていたのです。すさまじいまでの学びの姿勢でした。
そうした高齢者の姿から、「学び」がもつ真の意義、「学び」がもたらすものの大きさを感じつつ、数人のホームのスタッフたちと細々ですが公文を続けていました。でも、ほんとうの気持ちは「このホームに入所している高齢者全員に公文をしてもらいたい」でした。とはいえ、ホームのスタッフの忙しさを見るにつけ、そのことは言いだせずに、何年かがすぎていってしまいました。
東北大学の川島隆太先生と「運命の出会い」。そして『学習療法』誕生

そして2000年のある日。公文の社員の紹介で、東北大学の川島隆太先生(現在、同大加齢医学研究所所長・教授)と「運命の出会い」を果たします。川島先生はそのころ、何人かの大学の先生方とチームを組み、子どもたちの健やかな成長とより良い教育を脳科学の立場から科学的に解明しようとしていました。私はホームでの高齢者の学習事例を話したところ、興味をもたれたようで、数週間後に電話があり、共同研究の申し出を受けました。公文式学習が、子どもたちだけでなく、認知症の高齢者にも効果があるかどうかの可能性を検証したかったようです。当時は「認知症になったら進行するだけ、回復することはない」というのが医学的にも常識だったからです。
私は喜んで協力することにしました。大学の先生方の研究によって、公文式の学習が高齢者、それも認知症に有効だと科学的に証明されるなら、これまで「やらされ感」のあったホームのスタッフたちも、もっと前向きになってくれるかもしれない。もしかすると、ホームの入所者全員に公文をしてもらえるようになるかも…と考えたのです。
2001年9月、ホームに入所している47人の高齢者に公文のプリントで読み書き計算をしてもらい、その学習を通して高齢者と支援者(ホームのスタッフ)とがコミュニケーションするという試みがスタートしました。
初めのうち、「こんな簡単な問題ではかえって自尊心を傷つけるのでは」と、醒めた感じで高齢者に対応していたホームのスタッフたちでしたが、1~2ヵ月もすると驚きの表情に変わっていきました。頬を紅潮させ嬉々としてプリントに鉛筆を走らせる姿、大きなマルと100点をもらったときの得意げな表情や笑顔。決められた学習時刻の1時間も前から、学習室の前には順番待ちの車いすがズラリと並ぶ。それまで見たことがなかった光景を目の当たりにしたからです。
その光景は高齢者自身の変化となって表れてきました。無表情だった方が笑顔を見せるようになる。失語症といわれていた方の口からポツポツと言葉が出てくる。車イスにたよりがちだった方が自分で歩こうとする。なかには、尿意がもどり、やがてオムツがとれてしまった方も出てきました。「認知症になったら、あとはただ進行するだけ」という、当時の常識を覆す、にわかには信じられない効果であり、「認知症は回復する可能性がある」という大きな発見がありました。
こうして誕生したのが『学習療法』です。音読と計算を中心とした教材を使い、学習者と支援者がコミュニケーションをとりながら進める療法で、それにより認知機能やコミュニケーション機能などの維持や改善が期待できるというものです。
「研究」や「実践検証」というような概念がなかった介護現場。それも「いったん認知症になれば、その進行は止められない」というのが医学の常識だった当時、そのようなチャレンジをするには勇気がいりましたが、入所者のご家族の理解もあり、「これはどげんかせんといけん」という思いもあったのでやりきれました。ちょうどそのころ、私は介護保険制度の仕組みを学ぶため、大学院の修士課程に通っていたので、「研究者」という人たちのの立場や気持ちを理解できるようになっていたことも幸いしました。
変わったのは高齢者だけではありませんでした。スタッフたちも変わっていきました。高齢者に対することばや行動はもちろん、これまで「認知症になったら何もわからなくなる」「できなくなる」という認識だったのが、認知症になっても残された力を引き出すことで、「わからなくなる」「できなくなる」という症状が改善していく。最後の最後まで高齢者とコミュニケーションすることが大切。そのことに、スタッフ自身が気づくようになったのです。よし、これでここで頑張る人たちがもっと増える。うれしくなったと同時に、自分の責任の大きさも痛感しました。
みんなで楽しく暮らす。そのために学び続けたい

私がいまの仕事をしながら、それも川島先生たちとの共同研究もしながら、大学院の修士課程で学ぼうと決めたのは、新しく施行されることになった介護保険制度をきちんと知りたいという思いからでした。50歳すぎてからの大学院でしたから、ある意味、覚悟も必要でしたが、もっと知らなければという気持ちが強かったですね。
というのも、この制度の施行により、社会福祉法人の経営が大きく変わるからです。利用者はどうなるのだろう? ご家族の精神的、経済的な負担は? 私たち介護する側は? いろいろな思いが駆け巡り、私はものすごく悩みました。先行きが心配でした。でも。その悩みや不安が、大学院に行こうという気持ちを後押してくれたともいえますね。
学びの源泉ですか…。私の場合、目の前に課題や問題があると、これって何かおかしいな?と感じてしまい、それをなんとか解決するためにいろいろ調べます。ですから、必要に迫られてあれこれ知ろうとするだけなので、それが学びと言えるかどうか…。
たとえば、ホームのスタッフをもっといい組織にするために、いろいろ調べるのは避けて通れないのです。いまも、スタッフの気づき力を高めるには、現場でどういう仕掛けをするのがいいか、経営学の本を読んだり、同じ事業者から情報を集めたり、自分なりにまとめてみたりと考えを巡らせていますが、毎日が悩みの連続。「学び」にはほど遠いですね。
私は親から厳しく育てられてうんざりしていたのに、いつのまにかわが子にも厳しくしていました。母がしょっちゅう、「苦は楽の種、楽は苦の種」と言っていたからでしょうか、私も「人間どこかで苦労しなくては」と思うようになっていました。その意味では、いまの子どもたちは、親から大事にされすぎているような気がします。よくない意味としてですが。厳しさや苦労のなかから学びとることもあるはずなので、親御さんも、ほめることはもちろん大切ですが、「ここは」というところは毅然としていてはどうでしょう。
私がこれまでブレずに、こうしてずっと福祉の道を歩んでこられたのは、両親や生まれ育った環境が大きく影響していると思います。貧しい家庭で育ちましたが、大学教育まで受けさせてもらったことは、父や母にほんとうに感謝の気持ちでいっぱいです。困ったら近所や親せき、みんなで助け合うのもあたりまえでした。人と人、地域の絆がとても強かったように感じています。
お金持ちであろうと貧乏であろうと関係なく、「みんないっしょやろ」。そんな思いが根っこにあり、障害があろうとなかろうとみんな同じ、といういまの考えにつながったのかもしれません。要は、「地域のみんなで楽しく暮らそう」ということです。そのために、これからも知り続け学び続けていきたいと思っています。
関連リンク
永寿の郷(社会福祉法人道海永寿会)認知症高齢者が自分らしさを取り戻すために~学習療法とは(1)~|KUMON now!認知症高齢者が自分らしさを取り戻すために~学習療法とは(2)~|KUMON now!
 | 前編のインタビューから – 山崎園長のお母さんが“いつも一番になりなさい”と言い続けた真の理由とは? |
おすすめ記事
-

KUMONグループの活動
Vol.510
公文式英語で世界とつながる経験をきっかけに
将来を一つひとつ切り開くことができた 間違いをおそれずに挑戦しよう
-

学習経験者インタビュー
Vol.093
弁護士・ニューヨーク州弁護士
松本慶さん少しずつでも前進すれば大丈夫 「一日一歩」の精神で歩いていこう
-

スペシャルインタビュー
Vol.075
認知症専門医/ライフドクター®
長谷川嘉哉さん自分の「得意」を認識して 自分の頭でしっかり考え、 行動できる大人になろう
-

トピックスインタビュー
Vol.337
特別対談 ブレイディみかこさん×KUMON
2019年話題のノンフィクション本と KUMONに共通する思いは 「自分の力で人生を切り拓いていける人に」
Rankingアクセスランキング
- 24時間
- 月間
© 2001 Kumon Institute of Education Co., Ltd. All Rights Reserved.