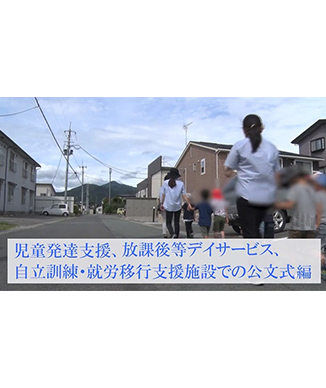「るみっくぷらす」の開所は、コロナ禍で学習環境の棲み分けの必要性に迫られたことがきっかけとなりましたが、石原代表は「るみっく」開所当初より、利用者の成長に合わせた事業所を立ち上げる構想を持っていました。
 里菜先生と教具で学習 里菜先生と教具で学習 |
「『るみっく』を未就学児の頃から利用していた子は、現在小学校高学年になっています。当初は意思疎通ができなかった重度知的障害(A判定)の子どもたちも、この6年間の取り組みによって、職員の話すことを理解し、指示にしたがって行動をすることができるようになりました。私はこの子たちが高校卒業後に迎える『就労』という次のステージに向けて、さらにできることが増やせるよう、落ち着いて作業や学習に取り組むことができる環境を整えてあげたかったのです」
「るみっくぷらす」に通う子どもたちは、おやつや飲み物を自分の席まで運び、落ち着いて食事をし、テーブルをふきんでふくといった、自立して生活するために必要なこともできることが増えてきたそうです。
また公文式学習を続けることによる変化も出てきています。一人ひとりの「できる」に合わせた教材に取り組む中で、一定時間座って取り組む、鉛筆を持って線をひく、自分の名前を書く、時間を計って学習する、学習済みの教材をひもで綴るといった行動面だけでなく、学習の内容も、+1のたし算から、+2、+3、と進むなど、ゆっくりのペースではありますが、できることが少しずつ、そして確実に増えていきました。
「るみっく」を6年間利用している中野さん(仮名)も「できることが増えた」と実感している一人です。中野さんの娘さんは現在小学6年生。小さいころから発語が少なく、幼稚園の活動では他の子についていくことができなかったそうです。そんな娘さんを心配した中野さんは、フリーペーパーで見かけた「るみっく」に問い合わせ。そのときに初めて会った石原代表に、強くひかれたといいます。
「ご自身が障害児の親として悩み、試行錯誤されてきた経験を、初めて会った私にオープンに話してくださいました。そして私の話すことに『わかる、わかる』と共感を持って聞いてくれ、力強く励ましてくださったのです。そんな石原先生を、私は温かくて信頼できる方と感じ、『るみっく』でお世話になることを決めました。
そして『るみっく』が公文式を導入していることについても、ありがたい、ぜひやらせたいと感じました。私自身、公文式の学習経験があり、できるまでくり返しやることで成長できたという実感があったからです。娘は、何百回も、何千回ものくり返しが必要ですが、できることからくり返し取り組むことで、少しずつステップアップしてきていることを感じます」
最近、中野さんの娘さんは、食べる前に机をふくことや、料理の手伝いをすることなど、生活スキルについても、できることが増えてきているそうです。
「石原先生には、娘の成長をサポートしていただくだけでなく、私自身も親としてたくさんのことを学ばせていただいています。例えば、子どもには短い言葉ではっきり伝える、厳しくも愛情を持ってしっかり接する、といったことなどです。そして石原先生は常に『今必要なものは何か』を考えて行動してくださっています。放課後等デイサービスの利用は18歳までなので、その後のことが不安でしたが、就労という次のステップも考えて対応してくださっていることは、とてもありがたいことだと思っています」
「いつでも話を聞いてくれる安心感があります」と、石原代表に全幅の信頼を寄せる中野さんにとって、石原代表の娘さんである里菜さんは「憧れ」なのだそうです。
「里菜先生は『るみっく』の職員として、多くのお子さんたちを日々サポートされています。里菜先生の子どもへの指示はとても的確で、普段は人の話を理解することが難しい重度の障害がある利用者さんであっても、里菜先生の言うことであればきちんと聞くことができるんです。しっかりと自立されている里菜先生の姿は、娘のロールモデルです」
 るみっくぷらすの久田先生 るみっくぷらすの久田先生 |
「るみっくぷらす」で公文式を担当する久田先生にもお話をうかがいました。
久田先生は2019年3月から「るみっく」に勤務し、2022年10月の「るみっくぷらす」開所と同時に異動。ご自身の役割を、「石原代表と保護者の思いを支えること」といいます。
「さまざまな特性がある子どもたちと接する中で、私たち職員が子どもたちに教えられている、助けられていることがよくあります。たとえば、子どもが何か失敗をしたとき、こちらはなんとかしなくちゃと心配するのですが、そんなときでも明るく悠然としている本人の姿に、逆に私たちが救われていると感じることがあるのです。学習面の歩みはゆっくりかもしれませんが、『るみっく』に通う子どもたちと接していると、どの子にも大きな可能性があるということを感じます」
久田先生が公文式の担当になったのは、「るみっくぷらす」に公文式が導入された、2022年12月からです。「公文を初めて担当するので、私自身が勉強中です」と前置きしつつ、こう語ってくれました。
「できたら次に進む、という公文式の学習システムはとても明快でしっかりしていると思います。一人ひとりの特性に応じて教材を選ぶことができるのもいいですね。私自身は、子どもの得意を見つけ、急がずに待つことを心がけています」
公文の学習に取り組み始めたばかりの子どもの場合は特に、じっと座っていることが難しいことや、なかなかやろうとしないこともあるそうです。
「そんなときでも子どもを急かすことはしないで、じっくりつきあいます。そして、座ってプリントに取り組むように、くり返し丁寧に伝えていくと、やがて席につけるようになるのです。初めはじっとしていることもできなかった子どもが、学習開始時刻になると自分の教材を持って、席に座るようになった姿を見ると、成長を感じます。そんな子どもたちの成長を見ることが私の喜びであり、やりがいなのです」
また久田先生とともに「るみっくぷらす」で働く里菜先生も、子どもたちに接する際に大切にしていることを、次のように話してくれました。
「私が大切にしているのは、年齢などに関係なく、どの利用者さんに対しても平等に接することです。そして、遊びや公文式学習を通して、利用者さんの『できること』を増やしていけるよう心がけています。そうなるには、何度も何度もできることをくり返し、少しずつできることを積み重ねることが大切だと思います。子どもたちの『できること』が増えて、楽しそうにしている姿を見ると、私もうれしくなります」
石原代表は、子どもの自立のためには、「まずはさせてみる」ことが大切だといいます。
「『できること』を増やすには、まずはやってみなければなりません。まずやってみて、最初はできなくても、何度も何度もくり返すことで、少しずつできるようになります。これは誰にでも当てはまることです」
 石原代表のカード学習 石原代表のカード学習 |
「だからこそ、『できないだろう』ではなく『させてみる』。それが私の信念です。多くの場合、危ないからやらせない、失敗しそうなことはさせない、と本人の行動を制限しがちです。しかしまずはさせてみることで、子どもの経験を増やすことの方が大切だと、私は思っています。それが子どもの自立につながると信じているからです。子どもはあっという間に成長してしまいますから、その時々を大切にして、『させてみる』ことが重要だと思います」
「こうした私の思いに合致したのが公文式学習でした。公文式は年齢や学年にとらわれず、一人ひとりの力に応じた『ちょうどの学習』で進みます。公文式の『ちょうどの学習』は今できることよりほんの少し難しいことに挑戦すること。『ちょうどの学習』を『させてみる』ことで、学ぶ楽しさやできる喜びを感じるようになります。そして『できたね』とほめられて自信がつき、それが自立に必要な『自ら考えて、行動する力』につながります。だからこそ、公文式学習を療育の要にしたのです」
そして公文式学習を導入したことによって、子どもたちの「できること」が増えつつあると、石原代表も職員たちも実感しているといいます。
「公文式のお陰で、私たち職員も子どもたちと一緒に成長することができました。施設の職員が同じ思いを持ち、行動方針を共有していたとしても、実際に全員が同じように子どもたちに指導するというのはとても難しいことです。そんなとき、公文式の教材と学習システム、そして公文の会社の方のサポートがあったのは、本当にありがたいことでした」
「これからも子どもたちとその保護者に寄り添っていきたい」と、石原代表は次なる夢を描いています。
「具体的には、2年後に相談支援事業所を、3年後には生活介護施設を開所する計画があります。これらの施設の開所は、現在の利用者さんとその保護者を支えることにもつながります。こうしたことをきちんと実現するためには、私たち自身も学び続けていく必要があります。命を預かっている責任と覚悟をしっかり持って、これからも信頼してくださっている利用者さんとその保護者の期待に応えていきたいと思います」
「るみっく」に通う一人ひとりが、自立に必要なことを身につけ、笑顔で過ごせるために、公文式学習はこれからも貢献していきます。
関連リンク 公文教育研究会 施設・学校向け公文式導入事業 放課後等デイサービスでの公文式学習①(前編)|KUMON now! 放課後等デイサービスでの公文式学習①(後編)|KUMON now! 公文式を導入している障害児・障害者支援施設での学習効果アンケート|KUMON now! 児童発達支援・放課後等デイサービスでの公文式学習|KUMON now! “つながる”療育支援―児童発達支援、放課後等デイサービス、自立訓練・就労移行支援施設での公文式 |KUMON now! 療育のなかのKUMON-放課後等デイサービスでの取り組み|KUMON now! 児童発達支援 放課後等デイサービス るみっく – 大阪市