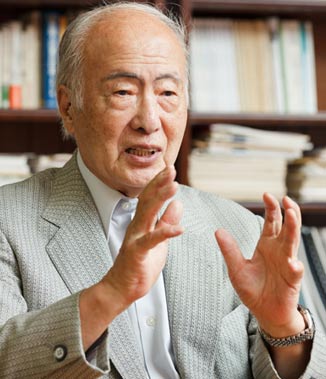人はいろいろな人と関わることで発達し続ける

親や友だち、保育士や先生など、子どもはさまざまな人と関わりながら大人になります。その過程で、どのような関係性やどういう側面が発達に影響をおよぼすのか。私はそれを明らかにしようと研究を続けています。
最近では歌いかけや読み聞かせの影響を中心に研究していますが、その際、高齢者と小学生がひとつのチームになって、乳幼児に読み聞かせをするという試みもしています。なぜそうするかというと、さまざまな世代の人との交流が、子どもたちの発達を促すと予測したからです。興味深いのは、読み聞かせを「受ける」乳幼児はもとより、「する」側の小学生たちと高齢者も変化していく、つまり発達していくのが見てとれることです。
一般的な発達の過程を簡潔に説明しておきましょう。例えば0~1歳の乳児期には、基本的に身近な一人の大人、多くは母親ですが、その一人とやりとりすればよく、そこから「自分には頼れる人がいる」と安心感や信頼感を得て、ひとつ大きな発達を遂げます。
幼児期になると、友だちと触れ合うようになりますが、すべてのことを受け入れてくれた母親とは違い、思うようにはいきません。戸惑いを感じ、「自分とは異なる人がいるんだ」ということを受け入れざるを得なくなります。ここでも子どもは急速な発達を遂げます。他者の存在に気づくと、人とつき合う態度だけでなく、自分の欲求をコントロールできるようにもなるからです。これを「発達課題の達成」といいます。
同様に、児童期・思春期・青年期とさまざまな人と関わるなかで、いろいろな発達課題が生まれますが、それを葛藤しながら乗り越えて達成していくと、またひとつ大きく伸びます。その意味では人間はさまざまな人との関わりを続けていく限り、生涯発達していく可能性があるといえ、成人期以降も発達が止まることは原理的にはありません。
発達が止まるとすれば、つき合う人の範囲が固定されたり、発達課題にチャレンジしなくなったりするからです。成人期以降は個人差がものすごくあり、チャレンジングな人は高齢でもどんどん伸びます。いろんな人たちと関わっていこうという積極的な気持ちがあれば、ずっと発達し続けるのです。
母の背中を見て「人を支えること」の素晴らしさを知る

私は「心の不思議さ」には子どものころから興味はあったものの、それを職業にするとは思ってもいませんでした。小さいころは電車の運転手、中学では教師や医者、高校時代は弁護士と、なりたい職業はさまざまでした。ただ、「困っている人を助ける職業に就きたい」という思いはありましたね。私には身体障害のある身内がいて、ずっと一緒に生きてきたことが、その背景にあるのだと思います。
もうひとつ大きな影響を受けたのは、中学校の教師をしていた母の存在です。いわゆる不良たち、あるいはいじめを受けた生徒たちをわが家に呼んで、食事をともにしていました。私はその生徒たちに嫉妬するわけでもなく、一緒に遊んだりするなかで、彼らの苦労も理解するようになり、そんな彼らを自宅に呼んで居場所をつくろうとしている母の姿から、「人というのは、人を支えることに喜びを感じるのだ」ということを学びました。
心理学への関心は、多感な思春期に、「自分はどういう存在なのか」と考えたことが原点かもしれません。近所のカトリック教会で説教を聞く機会があり、そこでますます「人間とは?」という思索を深めるようになりました。
そこから人の心への関心が生まれたのです。高校生時代には、たまたま自宅にあった「心を診療する内科」というサブタイトルのついた、池見酉次郎先生(いけみ ゆうじろう、心身医学者)の『心療内科』(中公新書)という本を読み、身体をコントロールする心の不思議さにひかれ、それを解明したいと思うようになりました。
そして心理学を学ぶため、東京教育大学(現・筑波大学)を第一志望で受験したのですが、不合格。第二志望だった東京外国語大学に進みます。そこで「外交官になろう」と、語学の習得に励む一方で、心理学にも未練があり、サークルは心理学研究会に所属していました。
銀行への内定が決まっていたが、心理学への思いが断ち切れず……

月日は流れ、いよいよ就職という時期になります。70年安保による長期の大学紛争にまともにぶつかり、心もすさんでいましたので「雇ってくれるならどこでも」と、銀行に内定が決まりました。けれども、卒業まであと半年というとき、ふと、「銀行で働くのでいいのか?」と、初めて本気で自分の人生を考えました。「心の不思議を解明したい」「人を支える仕事がしたい」という潜在的な気持ちがくすぶっていたのでしょう。
悩みに悩みましたが、卒論も迫ってきていました。専攻はロシア語で、心理学は勉強していません。せめて卒論は心理学をと、ロシアの心理学について書くことにしました。外国語を学ぶ大学なので、言葉の側面からテーマを探し、「言葉が思考をつくる」という理論を提唱したロシアの心理学者レフ・ヴィゴツキーに行き着きます。
担当教授と卒論の話を進めていくうちに、「実は心理学の道に進もうか悩んでいる」と打ち明けると、「人間その気になったらできる」と大学院の受験を勧められ、挑戦することに。本格的に勉強したのは卒論提出後の約1か月間。それまで生きてきたなかで一番勉強しました。
大学院を受験しようと決めたのは、卒論を書くために通っていた保育園での経験も影響しています。研究データを集めるため、子どもたち全員と仲良くする必要がありましたが、一人だけ、私を無視して話もしてくれない子どもに出会ったのです。今でいう発達障害児だったのですが、当時そんなことは知る由もなく“知らぬが仏”で、粘りづよく接していたら熱意が通じたのか、しゃべってくれるようになりました。
卒論執筆前にその子のことを園長先生に報告したところ、「本当にあの子がこう言ったの? 園では一度も話したことがない子なのに、そんなことを考えていたのね。ありがとう」ととても感謝されたのです。この経験が、心のどこかにあった「人を支えたい」という思いと結びつき、「心理学の技法を使って、こういう子たちのために働きたい」と、あらためて思うようになったのです。
大学院受験の結果は合格。まさに火事場のばか力でした。安堵したとたん、内定をもらっていたことを思い出しました。すでに入行1ヵ月前で、あわてて銀行へ事情説明に行きました。すると人事担当者は、「同業他社に行くなら納得できないが、そういう道へ進むのであれば喜んで送り出しましょう。将来、わが社を指導してくれるくらい、立派な研究者になってください」と言ってくれたのです。気持ちや志があれば、それに沿うような人々との出会いがあり、そうした出会いがまた人生を進めていくものなのだと、つくづく思いました。