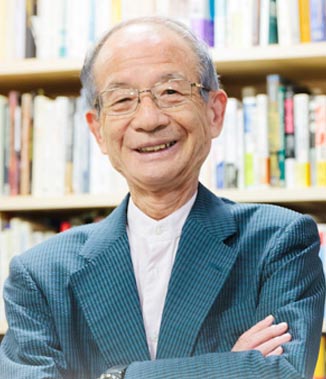期せずして行ったカナダ赴任がきっかけで、世界から声がかかるように
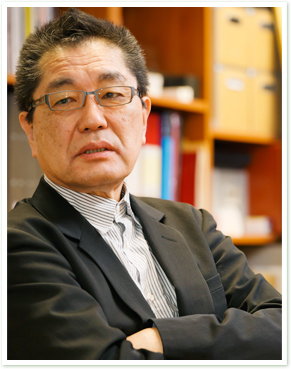
ミクロ経済の面白さに目覚めた私は、その中でもよりミクロなマネジメント・サイエンスの研究者になりたいと思うようになりました。自由にデータをもとに科学的検証をして、事業戦略の知見を得るという学問です。幸いICUの図書館では、関係する英語の文献が割と自由に手に入りましたので、勝手に相当高度な論文もワクワクしながら読んだ記憶があります。もともとアメリカで勝負したい、修士もPh.D.(博士号)もアメリカでとりたいと思っていたので、この分野で名のあるアメリカの大学に行こうと具体的に考えていました。
そんなとき、中高からの悪友がそういうことならうちの恩師に会えと強く薦めてきました。当時慶応大学の教授で日本のマーケティング論の若手の第一人者だった村田昭治先生です。正直そのときはお名前も知らず、分野も少し違うということで気乗りしなかったのですが、友人の顔を立ててお会いしたところ「修士は日本で取れ。しかも君がやりたい分野であれば、大学院は東大か阪大しかない」と大変説得的なご助言をいただき、そうすることに決めたのです。ただし、時は11月。阪大はすでに願書受付を締め切った後でしたが、東大は安保闘争の影響でこの年だけ募集期間を遅くしていて、しかもそれまで学外からの募集はしていなかったのにたまたま募集していたのです。それで運よく東大の大学院へ進むことになります。
東大では、企業経済の宮下藤太郎先生に師事し、併せて阪大からいらっしゃっていた大澤豊先生にマーケティングを教わりました。宮下さんからは「真理の前に上下なし」を教わり研究指導者としての基本を叩きこまれました。大澤さんからはその後専攻することになったマーケティングの手ほどきを受け、お亡くなりになるまで恩師としてお世話になりました。いまお二人を「さん」とお呼びしたのは、宮下ゼミも大澤ゼミもその当時では考えられない自由な雰囲気でみな「先生」と呼ばずに「さん」と呼んでいたからです。この宮下、大澤両先生こそ村田先生が名指しで師事すべしとお薦めになったお方で、東大で一度にお二人の指導を受けられたなんてまさに幸運としか言いようがありません。
そんな「運が良すぎる」人生を過ごしてきた私が言えるのは、「いい話は予定調和では来ない」ということ。しかも僕の場合、「会いたくない方に会う」「行きたくない会合に出る」という一見ネガティブなことがきっかけで、人生が決まることが多かったように思います。へそ曲がりだったからこそ、気が乗らないことにも取り組めたのかもしれませんが、そんなときでもポジティブに捉えてやってみると、案外おもしろい結果が出るものです。
その後、1989年以降海外のさまざまな大学で教えることになるのですが、これも初めから意図していたことではありません。最初のきっかけは、東大の助教授時代、誰も行きたがらないカナダの大学に、文化交流の目的で3ヵ月間滞在したことでした。
あまり気乗りせずに向かったカナダでしたが、せっかくだからと日本へ帰る途中、知人のいるマサチューセッツ工科大学に寄って行きました。そこで、その当時米国の学会で流行していた分析手法をまな板にあげて「あなた方の方法は間違っている。こうすべきだ」と、まるで道場破りのごとく、日本で開発した分析手法を自信をもって伝えたのです。現地の教授陣からしてみれば、「アジアから妙な奴が来た!」という感じでしょうが、私の熱心さが伝わったのか、帰国後、マーケティング・サイエンスの分野の第一人者のジョン・リトル教授から、「ダラスで学会があるから、そこで発表してみては」とファクスが来たのです。出席すると、たくさんの学者の方と仲良くなり、その後、アメリカを中心にさまざまな大学へ呼ばれるようになりました。
こうしてふり返ると、我ながらまったくロジカルな展開ではないですね。「これ、やらない?」と誘われ、「気が向かないけどやってみよう」と、チャレンジしたことで道が拓けてきたように思います。
「道楽」だったブランド論を徹底的に究める
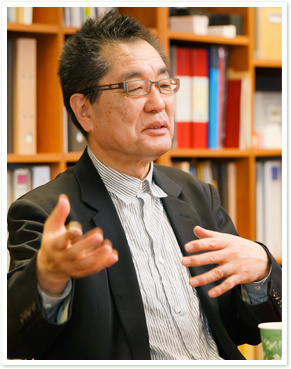
国内外でマーケティング・サイエンスを教えていた私が、ブランド論に進むようになったのは、1991年カリフォルニア大学バークレー校の客員教授時代、デービッド・アーカー教授と一緒に「マーケティング・マネジメント」を教えることになったのがきっかけです。彼も私と同じ専門でしたが、途中からブランドについて研究するようになり、1991年に『ブランド・エクイティ戦略』を著します。書き上げたばかりで、ブランドのことを話したくてしようがなかったようで、ランチ中にも「ブランド論のほうがおもしろいぞ」と私を熱心に誘うのです。マーケティング・サイエンスでタフな論文を書き、それで勝負しようと考えていた私は、「何を言っているんだ?」と思っていました。
ところが帰国後、ある広告会社からブランドについてのコラム連載を頼まれることになり、少し勉強し始めたらこれがおもしろい。当初、ブランド論は「道楽」だと位置づけていたのに、深みにはまってしまいました。
そこで、もっと究めるために、海外を中心に一流といわれるブランドを作り上げている企業の経営者に直接話を聞きに行くことにしたのです。「当たって砕けろ」の精神で、手紙を書いて取材を申し込んでいったところ、結構OKが出る! どの相手も、「ブランドのことを聞きたい」というと、喜んで話をしてくれるのでした。
そうしてさまざまなブランドの経営者の話を聞いているうちに、みな同じことを言っていることに気がつきました。強いブランドに共通するキーワードは、「夢」と「革新」と「一貫性」。このときの取材を拙著『パワー・ブランドの本質』としてまとめ、ブランド研究の道をひたすら歩むことになります。
それぞれ異なる「らしさ」をぶつけ合おう

固有の「らしさ」の塊ともいえるブランドに取り組み続けてきた私からしてみれば、少なくともこの20年、日本人は個を出さないようになったと感じています。みな同じ「会社語」を話していて、内心、「違うんだよね」と思っていても、自分の本当の考えを押し殺して議論している。これは勤め人ばかりでなく、主婦や子どもにも見られる傾向です。その反動で、ネット上には、本音や自分の生活をさらけ出す人があふれています。
自分を隠してムリをするのはナンセンスで、これからは、誰もが自分の固有名詞で生きなくてはならない時代になっていくでしょう。親も、自分自身に、そしてわが子に対しても自信をもち、また持たせてあげてほしいと思います。子どもが「自分しかできないこと」「自分が本当におもしろいと感じること」ができるよう応援し、自分の世界を開発していくよう導いてあげるのです。
といってもむずかしいことではありません。そうするためには、何ごともポジティブに捉えるのがいいと思います。私自身、ネガティブな教育は受けたことがなく、両親を含め、教師など周囲の大人がすべてポジティブに対応してくれたことが、今の自分につながっていると思います。
加えて、子どもを含む今の若い人たちには、「世の中や親がいうこと以外に、人生にはいいことがたくさんある。それは自分で探さなくてはいけないんだよ」と伝えたい。親も子に、それを実感できる体験をさせてあげることが大切です。
その意味では、一貫して「自学自習」を掲げ、「自分で考えて答えを見つける」場を提供する公文式学習は、自分で考える訓練をする絶好の場だと思います。
大人も子どもも、自分固有の「らしさ」を隠すことなく発揮すれば、相手が自分とは異なることに気づき、人としての幅も広がります。同じ「らしさ」ばかりでは退屈です。それぞれの「らしさ」がぶつかり合うことで人生はもっと豊かになり、自分の道を切り拓くヒントも得られるのではないかと思います。
関連リンクMBF:丸の内ブランドフォーラム