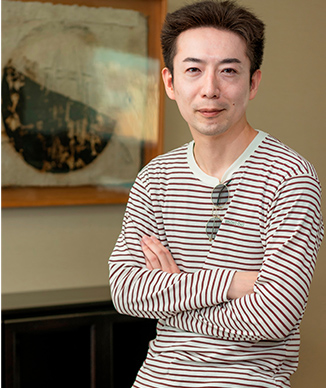東日本大震災を機に
「自分のスキルを社会に還元しよう」と決意
 |
小、中、高校と、デジタルに慣れ親しんでいた私ですが、高校時代に思いがけず小説に目覚めることになりました。夏目漱石など教科書の常連作家や、村上春樹など現代小説を好んで読んでいましたが、中でものめりこんだのが太宰治でした。太宰を深く理解するには文学部に進学するのがよいと考えて、大学は文学部に進みました。
専攻の授業はまじめに出席してはいましたが、むしろハマったのは必修科目の「情報」の授業でした。そこでウェブデザインに出会ったんです。元々、デジタルなものに接する機会の多かった私にとって、ウェブの世界の先進性は極めて新鮮で、以来、前のめりになってウェブデザインを勉強しました。
そしていざ、将来をどうするかというとき、教授にこう尋ねました。
「自分がこのまま大学院に進学したら、文学の分野で大学教員になれますか?」
教授の答えはノーでした。文学系の教員はすでに飽和状態でポストがなく、あっても熾烈な競争であると教えられました。そこで私は考えました。時は、ちょうどIT革命といわれ始めた頃。これからはインターネットが主流になるだろう。では、もうひとつの得意分野であるウェブデザインの道に進もう、と。
ただ、大学教員への思いも捨ててはいませんでした。ウェブ制作のスキルを使って、研究系の教員ではなく、「実務家教員」という道もあるかもしれない。そこを目指すには実社会での経験が相当必要だと考え、出版社など複数の会社でウェブ制作の実務経験を積みました。
転機となったのは、2011年の東日本大震災です。東京でウェブデザイナーとして働いていた私は、連日のようにメディアで報道される被災地の映像を見ながら自分の働き方を見つめ直すようになりました。このまま会社員として働くのではなく、もともと希望していた大学教員となって、自分の学びを社会に還元したい、と。
そこで、修士を取得するため、産業技術大学院大学に社会人学生として入学。32歳のときでした。その後、大学院修了のタイミングで北海道大学に就職し、サイエンスコミュニケ-ションに出会ったというわけです。
失敗をおそれずあきらめないで
「やり抜く力」が「生き抜く力」
 |
コロナ禍や自然災害、何が起こるか予測できない時代にあって、どんな難局でも乗り切っていく力をつけることが必要だと痛感しています。偏差値やTOEICのスコア、グラフィックデザインが素晴らしいといった一過性のスキルではなく、「生き抜く力が大事」だということです。そうした子を育てるには、家庭だけ、学校だけでは難しく、社会全体で育てていく必要があるように思います。
では「生き抜く力」をつけるにはどうしたらいいか。ひとつは、やはり公文式のように「まず自分でやってみる」ことです。加えて、私が最近興味を持っているのが「失敗させる技術」です。失敗して、自信を失ってしまう子を見るたびに、失敗してきた経験が少ないと感じるんです。成功体験は自信にはなりますが、失敗体験のほうが学びは大きい。授業やゼミの中でどう「失敗させること」を組み込んでいくか、具体的な方法を考えているところです。
じつは私は小学校の卒業文集で「高山市長になりたい」と書きました。子どもながらに市長になって、市政を改革したかったんですかね(笑)。今でも自分を育ててくれた高山市に還元できることはないか模索しています。昨年、高山市で市民講座が開催され、私も講師としてサイエンスコミュニケーションについて語りました。このように自分が学んで得たものを故郷にもちかえる活動についても、今後注力していきたいと思っています。
やりたいと思ったことを実現するために何を意識してきたかというと、「人生の伏線を回収しようと思って歩んできた」ということになるかと思います。高山市で公開講座をしたこと、それをまた今後も続けたいと考える根底には、市政に関心を持っていた小学生の頃の思いが少なからず影響していると思います。前半でお伝えした「カーリングAI」のサイエンスカフェでは、2006年のトリノオリンピックで小笠原 歩さんらの大活躍に感動して「いつか、カーリング選手と仕事をしたい」と思い続けた結果、実現にこぎ着けられました。「大学教員に」という夢も同様です。
つまり、当時の情熱を心に温めておいて、「ここぞ」というときに回収する。今でなくても、いつか引き出せるように、そのための努力をしておく。50歳でも60歳でも、人生のどこかで花開けばいい。そう思いながら歩んできました。やってきたことがムダにならないように生きている、ともいえますね。それができるのは、性格的にしつこいというか、あきらめずに勝つまでやるからだと思います。「やり抜く力」ともいえますね。それが「生き抜く力」につながっていくのかもしれません。
子どもは社会の中で育つもの
社会にもまれて多様な考えがあることを知ろう
 |
子どもというのは、日々の暮らしの中で長く一緒にいる人の影響を受けやすいのではないかと思います。その意味ではご家族の影響は少なくありません。ですから、学ぶことに積極的ではない方が「勉強しなさい」といっても、それは子どもにとっては理不尽な話ですよね。ほったらかしでも過干渉でもだめで、見ていないようでちゃんと見ている。その加減が難しいかもしれませんが、そうしたことも大切ではないかと思います。
子どもは、かつては親や学校だけではなく、地域、つまり社会の中で育っていたように思います。いまは社会と切り離されてきているように感じます。それでご家族や学校の負担が増えてきているのではないでしょうか。「子どもは社会の中で育つもの」と、みんなで考えていけるといいなと思います。
私自身を振り返ると、親からは「勉強しろ」とはあまりいわれず、やりたいならやらせてあげるという家庭で育ちました。何にせよ、自主的にやらないと身につきません。自分で考えて取り組む。親はその枠組みづくりに関われば良いのだと思います。
子どもたちには、多様な意見があることを知ってほしいですね。自分たちのいる教室や友だちだけが社会ではなくて、学校の外にも学びはある。むしろ、学校の外にこそ本当の学びはある。教科書やインターネットに書かれていることがすべてではありません。どんどん外に出ていってほしいですね。
サイエンスカフェもその一つです。科学は難しそうとの先入観を持たずに、気軽に参加してみてくださいね。それに、「サイエンス」をテーマにしているからサイエンスカフェといっていますが、そのほかに「人文学カフェ」などさまざまな“場”があります。そこで展開されているのはコミュニケーションです。
いろんな立場の、いろんな考え方の人と話をする。相手の言葉を否定しないで、いったん受け止めて、自分なりの解釈をしていく。そうやって、学校だけでなく、地域の中でさまざまな学びを得て、社会に還元できる大人になれたらステキだと思います。
関連リンク
常葉大学サイエンスコミュニケーターを育てる研究室村井貴デザイン研究室Facebook
 |
前編のインタビューから -他者の声に耳を傾ける |