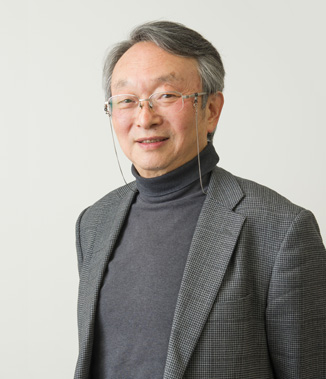*松川るいさんのご所属・肩書等は、インタビュー当時(2015年3月)のものです。
本を読んで空想ばかりしていた幼少期

子どものころは外で遊びまわっていました。家のうらに山があったり竹藪があったり、のどかな環境でしたから。とはいっても、小学2年生くらいまでは自分からお友だちと積極的に外に行くという感じではありませんでした。家のなかにはたくさんの本があり、もの心ついたときから本に囲まれて育ちました。母が読み聞かせをしてくれたこともあり、読書が好きで、本を読んで空想しているほうが楽しかったのです。その空想をもとに、いろいろなお話を自分で作るのですが、いつもきまって自分がお姫様や女王様(笑)。
自分をいつも女王様にするくらいですから、空想のなかでは積極派だったのでしょう。しかし、現実の世界は真逆で、自分のやっていることを、いつももうひとりの自分が見ているような、ちょっと冷めたようなところがありました。おまけに、人の前に出るのが死ぬほどいや。いまでもよく憶えているのですが、小学1年生のとき、担任の先生から「この作文はよく書けている。これを全校生徒の前で読んでみよう」と言われたことがありました。いま思えば名誉なことなのですが、そのときはもういやでいやで。人の前に出るのも目立つのも恥ずかしくて仕方ない。成人してからも、母に「あのときはたいへんだったのよ!」と何回も言われるほど。ほんとうにいやだったのでしょうね。
こんなこともありました。母に勧められ、わたしが子ども会で手品をやることになりました。厚紙で黒い山高帽を作って、「ここから鳩を出すのよ。さぁ、練習しましょう」と母が言うのです。人前に決して出ようとしないわたしを心配して、母なりにいろいろチャレンジさせようとしていたのでしょうが、そのときのわたしは「なぜこんなことをさせるんだろう。困ったなぁ」としか思えませんでした。人の前に出るのがいやなわたしが、みんなの前でいきなり手品って、かなりハードルが高いですよね。その結果は……。みなさんのご想像におまかせします。
そんなわたしが見違えるほど変わったのは小学3年生のとき、ひとりの友だちと出会ったときから。近所に引っ越してきた女の子、“めぐちゃん”はとても積極的でした。授業中も進んで手を挙げるし、たくさん発言する。「わたしはこう思います」と堂々と言う。すごいな、こういう生き方もあるんだなって、ちょっと驚きでした。家が近所だったこともあり、めぐちゃんは家のなかにいるわたしを毎日のように外へとひっぱり出しました。そうしてめぐちゃんと遊んでいるうちに、「みんなのなかで目立ってもいいんだ、こわがることはない」と、だんだんわかってきたんです。
幼かったわたしに、本が教えてくれたこと

勉強に関しては好きでも嫌いでもありませんでした。「勉強をしなきゃ」と思ったこともなければ、「自分は勉強ができるとかできない」と意識すらなく、もう記憶はおぼろげですが、おそらく小学3年生くらいまではそんな感じだったと思います。
公文は小学3年生くらいからはじめました。「算数って楽しいな」って思えるきっかけになりました。小学5年生くらいからでしょうか、中学受験のための進学塾にも通うようになりました。そのころからですね。「勉強が面白い」と思うようになったのは。人と競争するのも楽しい、やればやるほど先に進んでいろんなことがわかるようになるのが面白いなと、そう感じるようにもなりました。
読書はもちろん好きで、お気に入りの本を読んでいるときは、母に名前を呼ばれてもまったく気づかないこともめずらしくありませんでした。本にかぎらず、好きなことへの集中力はかなり高かったと思います。父も本が好きでしたし、家のなかの壁という壁が本で埋まっているような家だったので、本が生活の一部のような感じでした。
小さいころに読んだ印象深い本を一冊だけあげるとすれば、イソップ童話の『からすと水がめ』という本です。からすは水がめに入っている水を飲みたい。でも、くちばしをつっこんでも届かない。そこで、からすは石を入れるんです、水がめに。すると水位が上がってきて、くちばしが水に届く。なるほど、頭を使ってちゃんと考えれば、できなさそうなことも、できるようになる。必ず良い解決法が見つかるんだと、幼いながらに感心したことを憶えています。
“ベルリンの壁崩壊”進むべき道を決めた衝撃の出来事

大学受験を考えたとき、初めて自分の将来と真剣に向き合うことになりました。じつはわたしは、高校2年生のころまでは漠然と「医学部に行こう」としか考えていなくて、授業では理系の科目を履修していました。そこには、将来の明確な夢や想いはありませんでした。大学受験が迫ってくるにしたがい、「こんな中途半端な気持ちじゃいけないな」「じゃあ何がやりたいのか?」と自問自答した結果、医者になりたいと思っていたわけではなかったことに気づきました。逡巡したのち、とりあえず、将来の選択肢が幅広い文系に転じて受験。志望の大学に合格できました。
入学後、自分の進む道を定めてくれたのは、大学のESS(English Speaking Society)サークルでした。思い返せば、中学生・高校生のころから、国際関係とまではいかないのですが、外国の文化に興味がありました。英語も好きだし、外国の人と話すのも純粋にうれしかった。大学のESSには国際問題に関心のある人が多くて、卒業生のなかには外交官の先輩もたくさんいました。
そして、大きな転機がおとずれました。忘れもしません、大学1年生の秋。「ベルリンの壁崩壊」のニュースが飛び込んできたのです。すごい衝撃でした。さらにそのあと、まさかソ連がなくなるなんて……。ほんとうに信じられないことでした。そのときはっきりと、「国際関係の仕事に就きたい」と思いました。国も世界も動くんだ、ダイナミックだなって感じました。外交官になるということを意識したのも、このころです。
とはいえ、外交官試験は超狭き門。こんな話を耳にしました。900人近くが受験して、一次試験を突破するのが約60人、そして最終的に外務公務員Ⅰ種に女性で合格できるのは1人か2人。こんな話を聞くとやる気がなくなりますよね。でも、わたしには独特な考え方があって、自分で勝手に「四分の一の法則」と名づけているのですが、ほんとうの競争率ってだいたい4倍くらいだという感覚なのです。もちろんぜんぜん根拠はないのですが(笑)。ただ、ライバルが100人いようと200人いようと、この席をほんとうに争っているのは4人くらいだと自分に言い聞かせています。4倍だと思えば、やる気がわきますよね。大学入試も外交官試験も、そういう気持ちでのり越えてきました。ある意味、すごく楽観的な性格なのかもしれません。
 |
後編のインタビューから – 両親から愛されているという気持ちが、いまの仕事を支えてくれている |
おすすめ記事
-

学習経験者インタビュー
Vol.087
ピアニスト
中川優芽花さん「まずは行動して、失敗して、学ぶ」 プロセスは 音楽にも勉強にも大切なもの 失敗しても、すべての経験は力になる
-

KUMONグループの活動
Vol.251
療育のなかのKUMON-放課後等デイサービスでの取り組み
障害のある子たちによりそい 一人ひとりが幸せになるサポートをしたい ~ ライフステージに合わせた“つながる療育支援”をめざして ~
-

学習経験者インタビュー
Vol.093
弁護士・ニューヨーク州弁護士
松本慶さん少しずつでも前進すれば大丈夫 「一日一歩」の精神で歩いていこう
-

スペシャルインタビュー
Vol.075
認知症専門医/ライフドクター®
長谷川嘉哉さん自分の「得意」を認識して 自分の頭でしっかり考え、 行動できる大人になろう
Rankingアクセスランキング
- 24時間
- 月間
© 2001 Kumon Institute of Education Co., Ltd. All Rights Reserved.