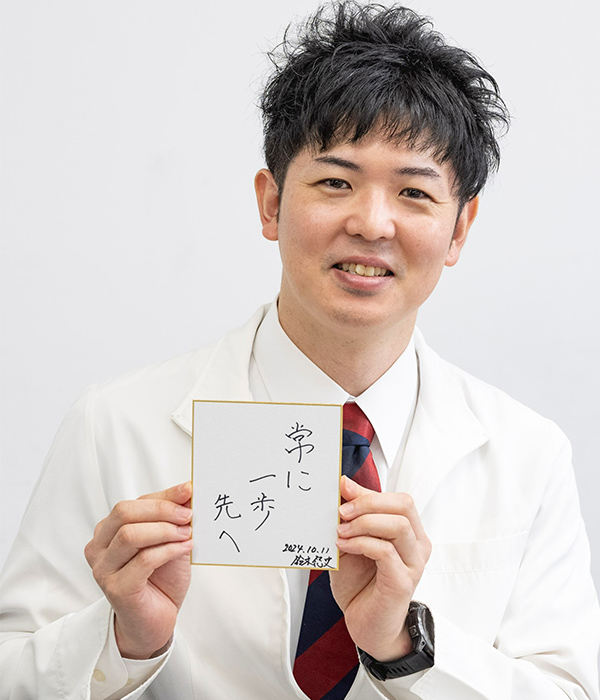「正解」が分からない囲碁の世界

プロになったのは15歳のときでした。ホッとしたという気持ちは確かにあるんですけど、よく言われる「プロになっていちばん嬉しかったのはプロになったとき」というような感覚はあまりなくて。「プロになるのは通過点だ」とそのころは考えていました。これからもっともっとがんばらなきゃと。そして、プロになってからは想像以上に険しい道が続いているのも事実です。
二十歳くらいのときのことです。大きなタイトル戦に出るための決勝戦で、この対局に勝てばタイトル戦出場が決まる対局で3連敗したんです。負けるたびにショックは受けますが、このときのダメージはさすがに大きかった。このままタイトル戦に出られずに終わってしまうのか、という不安も大きくなりました。
けれども、ありがたいことに、僕は一晩寝るとスッキリ忘れてしまうたちなので、あまり引きずることがないんです。もう長くこの世界にいるので、負けるのは日常茶飯事。歳を重ねるうちに、気持ちの切り替えは上手くなってきたと思います。
負けたことをつぎに生かすには……。まず、納得できるまで敗因を調べ、その対策を考えます。また、これは負けに限りませんが、自分の試合は必ずふり返ります。反省点は自分なりに消化して、利点に変える。ただ、なかなか成長はしないもので、反省したつもりでもまた同じようなミスをくり返してしまうことはあります。これと同じようなことは、公文を学習しているときにも体験しました。ミスした問題をきちんと訂正することで、「どこで」「なぜ」ミスをしたのかに気づき、それがまた学ぶ力になるのですね。
囲碁というのは分からない部分が非常に多くて、考え方はそれぞれのプロが違うものを持っています。さらに、そのどれが正解なのかの判断がむずかしいのです。私自身も、若いころと比べて囲碁に対する考え方が変わっていますが、それが正解に向かっているのかどうかも分からないんです。
一応日々修行は重ねているので、自分としては進化しているつもりではいても、それが果たして正しい方向に進んでいるのかは分かりません。しかし正解が分からないからこそ、囲碁にはこれだけ長い歴史があるようにも思います。
日々の研究で、さらに進化していきたい

10代、20代、30代と囲碁への取り組み方は変わってきました。不思議に思われるかもしれませんが、若いころのほうが先を読む力はあったと思います。先を読む力というのは体力に近いものがあり、私の場合、10代、20代のころは先を読むことによって、多少力任せに打っていたと思います。
30代になると、先を読む能力はだんだん衰えてきますが、その分判断力や柔軟性が身についてくる。先を読み、頭のなかにできた対局図を見極める力ですね。自分がこう打てばこういう図に、こう打てばこういう図に、と無限にできるパターンのなかから自分にいちばん合った図を選ばないといけません。その見極めが速く正確な人こそ、プロとして成功するのだと思います。ただ、先を読んだ図自体が間違っていたらどうにもなりませんから、やっぱり最終的には総合力でしょうか。
だから今、自分のなかでテーマにしているのは「進化」なんです。囲碁の世界ではやっぱり若い人のほうが強いんですね。読みの正確さがモノを言っている。世界的には20代前半くらいまでがピークとされています。自分が歳を重ねてきたというのもありますが、それは少し残念なこと。でも、かつては70代でタイトルを取られた方もいらっしゃる世界なので、常に自分も進化して、いくつになってもタイトル戦に出られるような力をもっていたいなと思います。
そのためには、やはり日々の研究です。研究すること以外に強くなれる方法はありませんから。あとは体力的な面も重要ですね。座っていることが多い職業ですので、意識的に身体を動かすというプロはけっこういらっしゃいます。そして精神のコントロール。試合中、ずっと自分のほうがいいということはなかなかなくて、逆転したりされたりのくり返し。どんな状況でも冷静でいられる精神力は、経験から身につくものだと信じています。
対局で予想もつかない考えと出会える喜び

今公文を学習している子どもたちは、日々の積み重ねの大切さはよく分かっていると思います。だから私がみなさんに何かアドバイスするとしたら、「自分で考える」ということでしょうか。これは自分もそうですが、最近は何か分からないことがあるとすぐパソコンで調べたり、漢字の読み書きも携帯電話に頼ったり。しかし、自分で一所懸命考えたり調べたりしたことはなかなか忘れません。囲碁も同じで、人からただ教えられたものは時間が経つと思い出せなくなりますが、自分で研究し納得したものはいつまでも記憶に残っています。
先ほどもお話ししましたが、誠心誠意囲碁に取り組んでいても、はたしてそれが良い方向に行っているのか、正解に近づいているのかが分からない。それに、対局に負けると本当に悔しいし、イヤになることもありますが、それでもどうして囲碁をするのかといえば、やはり囲碁が楽しいからです。
正解に近づいているのか分からないけれど、考えても考えてもよくわからないところがある囲碁ですが、一所懸命取り組むのが楽しいのです。分からないことの面白さと、そのなかでときどきハッとするような光を見つけたときの嬉しさ。なるべく小さな目標を設定して、少しずつ達成感を味わう。そうすれば自然と楽しくなるし、続けることに希望が持てます。
私は囲碁が大好きです。その気持ちがいつもベースになって私を支えてくれている気がします。だからこの歳になっても苦になりません。どんなことにも楽しみを見つけられさえすれば、幸せな気分で取り組めると思うのです。私の場合は対局のたびに新しい考え方に出会い、それが続けるモチベーションになっています。人の数だけ考えがある。対局とは日々出会いです。予想もつかない考えと出会うことこそ、碁を打つ喜びなのかもしれません。
関連リンク
山下敬吾|公益財団法人日本棋院
 | 前編のインタビューから – 「実は、囲碁をやめていた時期があったんです」。その時期とは? |