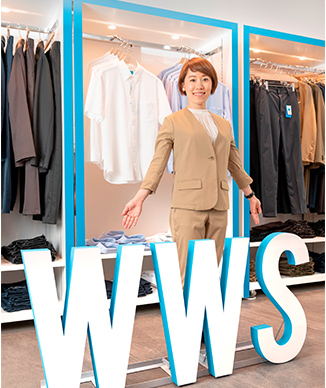未開の領域を開拓するため様々な研究会に参加
博士課程に進んだ私は、「できるだけ新しい分野がいい」という単純な発想で、サービス業のマーケティングをテーマにしました。当時、「ブランド研究」は盛んでしたが、「サービスマーケティング」はあまり研究されていなかったんです。その反面、先行者がいないので、過去の研究事例がなく、自分で切り開かねばならない苦しさがありました。
そのため「これは大学院の勉強だけでは不十分だ」と思い、在学中から様々な研究会やプロジェクトに参加しました。そのひとつが、調査研究のパイオニア、日本生産性本部での調査です。手弁当でデータ分析やインタビューなど、様々な調査に関わりました。
私の研究スタイルは、理論的な仮説があり、それをデータで裏付けるという仮説検証型です。たとえば教育現場では、担任の先生をつけたほうがいいのか、それとも毎回違う先生が担当しても変らないのか、それぞれの場合について実際にデータをとって確かめてみる、といったスタイルです。
やがて、CSI(=Customer Satisfaction Index:顧客満足度指数)の研究を専門にするようになりました。特に注力するようになったのは、2007年の第一次安倍内閣の「骨太の方針」に、「日本のサービス業の生産性向上のための施策づくりを」ということが盛り込まれたのがきっかけです。
製造業に比べて日本発のサービス業が少ないため、もっと力を入れていこうという政府肝いりの施策で、人材育成などいくつかの項目と並んで「CSIの開発」もありました。そこで、その研究をしていた私が開発委員会に呼ばれ、アカデミックアドバイザーとして活動することになったんです。
前編で述べたように、CSIとは「消費者目線でサービスを評価する」ものです。製造業の場合は「耐久性」など客観的な指数がありますが、サービス業は目に見えないので「これはいい」といっても、どういいのかわかりません。それを、実際に利用した消費者に細かく聞いていき、指数化したのがCSIです。その方法論をアメリカ、スウェーデン、韓国、シンガポールなどの先人たちを訪ねたり、産業界のさまざまな経営者やマネジャーのお話を伺いながら、3年かけてつくりました。
「この情報は本当だろうか」と一度疑ってみよう
現在、大学でも教えていますが、私の世代から比べたら最近の学生はまじめですね。また情報をたくさんとれる時代のせいか、言葉をよく知っています。ですが、その言葉を体系的には知らず、うわべだけで理解しているようにも感じます。また、書いてあることを吟味せずに真に受けてしまう傾向もあります。グラフの単位を見ないなど、基本的なことに目が行き届いていないことも少なくありません。情報入手が容易になった反面、情報の整理や咀嚼が雑になってきていると感じます。
そこで学生によくいうのは「グラフやデータをきちんと読み解くリテラシーをつけよう。データに騙されるな」ということです。学生に限ったことではないでしょうが、目の前のデータがどういう意味をもっているのか、かみ砕くことができていないと、データに踊らされてしまいます。「意識をもって見る」くせは、若いときからつけておいたほうがいい。たとえば一度自分でグラフをつくってみるといいかもしれません。
データに限らず、「本当だろうか」と疑ってみることも大事です。私のゼミではその繰り返しで、「この記事は本当だと思う?」と聞くと大体の学生は困惑します。ネット記事でも雑誌記事でも、「誰が、どういう立場で、何を主張しようして書いているのか」を読み解けるようになることが必要です。
レポートも、なんとなく表面的にきれいにまとめてはいるのですが、自分なりの視点がないことも気になります。議論をしていても、私としては異論を述べてもらいたいのですが、周囲と違うことをいって、変な目で見られるのを恐れているのか、誰かが意見をいうと「私もそう思います」と続きます。たとえ同じ意見だとしても、「私もそう思いますが、付け加えると……」という「自分なりの意見」が欲しいですね。
自分で体験して現場を見て、探求する心を育もう
時代は変わっていくので、経営やマーケティングの手法も変化していきます。10年前の手法が現在に使えるかわかりませんし、今の手法が10年後に使えるかもわかりません。そうした中、私にとって学びとは、「いつまでも究められないもの」。たとえれば、大きな袋に手を入れて、一つひとつピースを見つけては取り出して、埋めていく作業の連続です。「もうすぐ完成する」と思ったら、思いがけず溝があってうまくはまらなかったり……。
「学問とは何か」と問われれば、「問いを学ぶ」ことだとお伝えしたいですね。私は必ず学生に「問いをつくることが一番大事」だと伝えています。答えを学ぶのではなく、何が問題か、自ら問いを定義していくことだ、と。それができれば研究の方向性が見えてきます。実はこれは、私自身が大学時代にゼミの先生から言われた言葉なんです。
今後、成し遂げたいことは大きく2つあります。ひとつは11年分蓄積されているCSIのデータと、各社の財務データとを付き合わせて、関連性を見ていくことです。年間約12万人の消費者を対象とした国内最大級の顧客満足度調査として、11年が経過しましたが、それを『サービスエクセレンス』というタイトルで本にまとめました。次の仕事は、「満足度が上がるから会社の業績が上がる」ということだけでなく、「ファンが多いなど満足度が高い会社は、たとえばコロナ禍などで業績低下しても回復が早い」などの仮説を、データで実証したいですね。こうしたことは昔から多くの人が疑問に思っていたことですが、長期データがないと分析できず、まさに当初からこの調査に関わっている自分の責任としてやっていきたいと思います。
もうひとつは、ハイテク&ハイタッチをテーマにした研究です。ハイタッチとは人による触れ合いですが、そこにテクノロジー(機械やIT)を入れていく流れにあります。人とテクノロジーのバランスをどうつくっていくか。ある種のサービスのイノベーションであり、今、事例を研究し始めているところです。
子どもたちに伝えたいのは、「探求する心」を大事にしてほしいということです。期末試験や受験対策としての暗記の勉強だけでなく、実際に自分で体験して現場を見て、探求する心を育んでください。私自身も、現場に行くことを心がけてきました。今でもヒアリングやフィールドワークを重要視しています。それはデータだけでは言えないことがあるからです。
たとえば、あるスーパーのデータをとるのであれば、私はその現場を実際に見ないと落ち着かないんです。店の外観、お客さんの様子、駐車している車の種類、自転車の多さなど、現場を見るようにすることで、データの納得感も高まります。
仕事でなくても、たとえば歴史で習った地域に行ってみると、疑問が湧くこともあり、そこから探求心が芽生えます。意識さえ持っていれば、道を歩いていても発見や疑問は見つかるものです。保護者の方も、そうした場をお子さんに提供してあげるだけではなく、一緒に現場を歩くなどして問いを立ててみてはどうでしょう。案外と日々が楽しくなると思いますよ。
関連リンク 青山学院大学
 |
前編のインタビューから -目に見えないサービス業を「消費者目線」で評価する顧客満足度調査 |
おすすめ記事
-

学習経験者インタビュー
Vol.087
ピアニスト
中川優芽花さん「まずは行動して、失敗して、学ぶ」 プロセスは 音楽にも勉強にも大切なもの 失敗しても、すべての経験は力になる
-

学習経験者インタビュー
Vol.091
千房株式会社 代表取締役社長
中井貫ニさん「全人格格闘技」 目の前のことに全力を尽くして 「ありがとう」の感謝の心で生きていこう
-

スペシャルインタビュー
Vol.073
特別対談 棋士 藤井 聡太さん
終わりのない将棋の極みへ 可能性のある限り 一歩ずつ上を目指していきたい
-

KUMONグループの活動
Vol.486
学校でのKUMON-長岡英智高等学校
『やればできる』の体験が チャレンジ精神を育み 夢や目標を描く力となる
Rankingアクセスランキング
- 24時間
- 月間