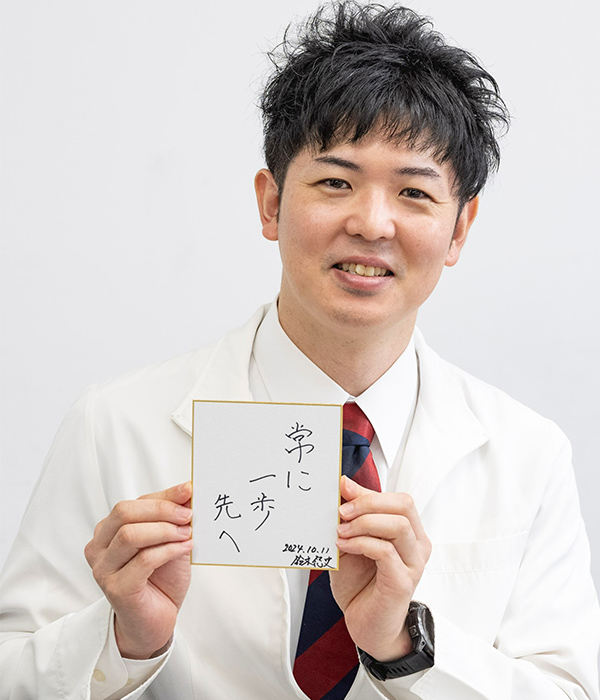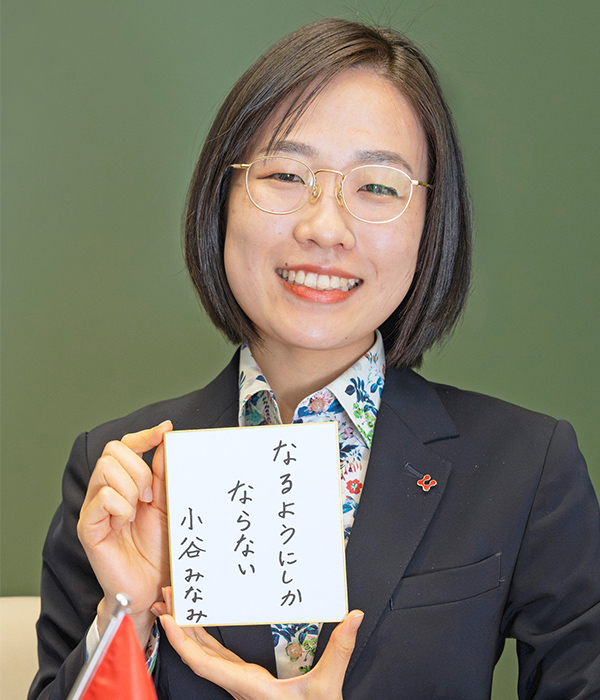子どもの学びの旬を逃さないことが大切
 |
私は活字好きな両親の元で育ちました。新聞は全国紙と地方紙、「週刊朝日」や「婦人公論」といった雑誌や文学全集など、家は活字だらけ。私もいろんな本を読みました。新聞は小3の頃から毎日2時間かけ、“子ども新聞”ではなく大人が読む本紙を読んでいました。新聞では、私の原点となるたくさんの気づきを得ました。
ひとつは小4のときに読んだ記事。72歳の方が戦争で学ぶ機会を失い、夜間学校に通ってひらがなを勉強しているという内容でした。そこに「あ」の字が難しく、覚えるのに数ヵ月かかったとあって驚きました。「子どもは簡単に覚えられるのに、大人になると覚えにくいんだ。学ぶのには“旬”があるんだな」と思ったのです。
もうひとつは中2のとき、バイオリンなど音楽を通じて心豊かな人間を育てる教育法「スズキ・メソード」の記事でした。「子どもがバイオリンを上手になれないのは子どものせいではなく指導者のせいだ」と鈴木先生の言葉が書かれていて衝撃を受けました。それまで私の周囲には、子どもが何かできないときには「子どもの努力が足りない」という大人ばかりだったのです。しかし、それは「指導者の責任」という大人がいることに感動しました。
この2つの記事のことがずっと頭にあり、子どもが生まれたとき、「ひらがなを早く覚えさせるのも、子どもが楽しくどんどんやっているならそれがその子の学びの旬なのだから、どんどんやらせていい。むしろ旬を逃すと大変になる。そして、子どもが伸びなかったりいやだと言ったりするなら、指導者つまり母親である私のやり方がいけないのであって、その子に合う別のやり方を試してみるべきだ」と改めて思いました。
大人の勝手な都合で怒らない、他の子と比較しない
 |
4人の子どもたちが全員東大理三に進学したことで、私がいわゆる教育ママとの印象を持たれることが多分にありますが、進学先について学校の固有名詞は一度も口にしたことはありません。大学と学部はそれぞれ自分たちで選びました。
親が希望の学校名を言って、子どもがそこに合格できなかったとき親をがっかりさせたことに子どもは傷つくのです。「親の希望を叶えてあげられなかった」という思いをずっと抱えて生きていかせるのは子どもが気の毒です。大学は単に人生の通過点に過ぎず、大事なのはその後、どう生きるかですし、そもそも親と子の人生は別ものですから。
私は何より子どもたちと信頼関係を築くことが大切だと思っています。気分や感情で怒り方を変えていると、親子の信頼関係は築けません。わが家での出来事です。リンゴジュースをコップに入れ、「こぼさないようにね」と子どもに渡したとたんに走り出して、絨毯の上にこぼしてしまったことがありました。「まったく…」と言いながらふき、数日後にはオレンジジュースをこぼし私は「なんでこぼしたの!」と怒りながらふき、さらにその後日にはブドウジュースをこぼしてしまった子どもに私は「だから言ったじゃないの!!」と大きな声で怒ることに。なんといっても、ブドウジュースは拭いても色が落ちないんです。
私はリンゴ→オレンジ→ブドウの順に段々怒りが大きくなったことに気づいて、大人って勝手だなと思ったんです。同じジュースなのに後始末のやりやすさによって怒り方を変えるのは、子どもにとっては非常に理不尽なことだと気が付きました。それで、自分が正しい基準で子どもを怒っているのか自信がなくなりました。親が感情や気分や都合で怒る基準を変えたら子どもに信用されなくなります。それからは、子どもが何をしても危険なこと以外は、「こんなことをしてしまう子どもはかわいい」と思うようになりました。
もうひとつ、わが家で心がけてきたのは、兄弟間でも他の子とでも、比較しないことです。たとえば日頃100点満点のテストで50点しか取れない子どもが60点を取ったとします。うれしくて「ママ!60点取ったよ!」と学校から走って帰ってきた時、「何言ってるの。お兄ちゃんなんかいつも100点よ」と言ってしまったら、その子は二度とお母さんに話をしなくなるでしょう。子どもの“お母さんにうれしさを伝えたい気持ち”が、他の子と比較したためにお母さんには見えなくなってしまうのです。
わが家では比較することを避けるために、通知表には、ひとこと「お疲れさま」という言葉をかけるだけにしていました。また、4人の子どもたちは体の大きさは違うけど、お菓子や果物などは全て同量。誕生日も、全員に同じプレゼントを渡すことに。みんな一緒に楽しそうに遊んでいましたよ。そうすればケンカもねたみもありません。今でもずっと兄妹の仲はいいですよ。呼び方も大切なので「お兄ちゃん」と呼ばせず、全員名前で呼び合うことに。だから上下関係もなく、反抗期もありませんでした。よく反抗期に悩む保護者は多いのですが、それまでに親が反抗のタネをつくっているのではないかと思います。
子どもが巣立ったときに
「楽しかった!」といえる子育てを
 |
今は多すぎる情報に惑わされて悩んでいるお母さんが多いように感じます。何でもネットですぐに見られるので、情報を受け入れすぎて身動きが取れない。だから今の時代こそ、より自分の芯をもつべきでしょう。
誰かの成功例が自分の子に合うとも限りません。ノウハウを求めるのではなく、トライアル&エラーを繰り返して、失敗から知見を得るほうがいいと思います。私も公文のプリントにしても、「この子は何枚やったらいいかな」など散々試しました。恐れすぎたり手間だと思ったりせずに、「とりあえず」「ゆるく」「ざっくりと」やってみましょう。3ヵ月続けてみたら変わってきますよ。
働いていて時間がない、余裕がないというお母さんも、帰宅後30分だけでもお子さんの隣りに座って話を聞いたり宿題を見たりしてあげてください。近くにいるだけでもいいと思います。子どもは毎日その30分を待つようになります。子どもというのは「お母さんを待っている」存在だということを忘れないでくださいね。
お子さんたちに伝えたいのは、目の前の小さなことを少しずつ確実に積み上げていくことが自分の未来に必ずつながるということです。毎日楽しく保護者の方と一緒に前に進み、自分の未来を確実なものにしてください。
子どもは本来、新しいことを学ぶのが好きなのです。それなのに、子どもは勉強を嫌がり、親は子育てに疲弊している状況は、ちょっと違うのではと思います。やはり楽しくないからそうなるのでしょう。何事も「楽しさ」がやる気のもとになります。楽しく学べばより学びたくなりますから、実力は必ずつきます。人生を開くのは「学び」しかありません。その元になる基礎学力を、旬を逃さずに楽しく身につけてほしいですね。
子育ても本来楽しいものですから、私はその楽しさも伝えていきたいと思います。以前は、「東大に合格するにはどうしたらいいですか」という質問ばかりでしたが、最近は「子育てを楽しむにはどうしたらいいですか」というものが増えてきて、少し安心しています。
子育ての相手は人間です。答えは全部違います。思い通りにいけばうれしいですが、うまくいかないことのほうが多いですよね。私も何度もありました。子どもは「やっちゃだめよ」ということばかりしますからね(笑)。でも、その思い通りにいかないことが子育てのおもしろさなのです。
子育ては18年間の期間限定。その間に親も18歳年を取るわけですから、せっかくなら、いいことも悪いことも楽しんじゃいましょう。そして18年間終わったときに、お子さんと、「なんか楽しかったね」と言えるような子育てができたら、ステキだと思いませんか。
そんな方が少しずつでも増えるよう、私の活動がお役に立てればと思います。
関連リンク 『我が家はこうして読解力をつけました』の詳細情報はこちら「なるほど!くもん出版」内 佐藤亮子さん特集記事佐藤ママ スペシャルインタビュー動画
 |
前編のインタビューから -4人の子育てで奮闘中に、応援してくださった方々への感謝と恩返しとして |