17歳で偶然みた浮世絵に衝撃
10代の体験が自分の興味を引き出すきっかけに
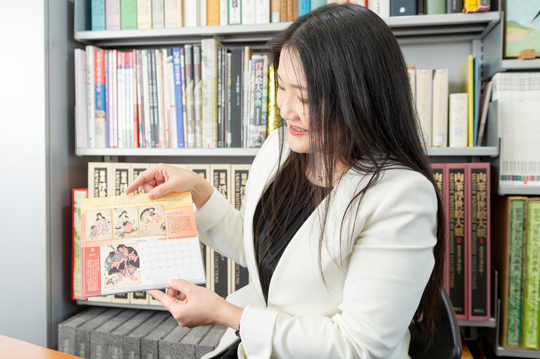 |
絵を描くことが好きだった私は、子どもの時から油絵を習い、将来は美術系に進みたいと考えていました。中学、高校時代は、美術部や演劇部に所属。大学では美術部に加え、友人とバンドを組んでボーカルを担当したりと、表現することが大好きでした。いまでも、私の授業はパフォーマンスみたいだなんて言われています(笑)。興味を持って聞いてほしいという想いの根っこは同じかもしれませんね。
最初は印象派など、西洋絵画が好きでしたが、17歳のころ、印象派の展覧会に行ったとき、会場に展示されていた浮世絵の鮮やかな色彩とデザインに衝撃を受けました。私の好きな印象派の画家たちが、実は日本の浮世絵の影響を受けていたことを、そこで初めて知りました。同時に、「美術史」という学問の存在も知りました。
その頃に出会った浮世絵に、鈴木春信の「風流四季哥仙 二月 水辺梅」という作品があります。夜、少年が梅の木の枝を折ろうとし、横にいる少女がそれを見守っているのですが、少女は石灯籠に振り袖の袂をかぶせて明かりが漏れないようにしています。内緒の「恋」を描いた作品だと気づき、江戸時代の人も、少女漫画をみるような気持ちでこの絵をみていたのかなと思ったとき、時を超越し、江戸と現代が繋がる感じがしたのです。
以来、浮世絵や江戸風俗の虜に。学校帰りに歌舞伎座や国技館にも足を運んでいました。現在役者絵を研究している妹と一緒に通いましたが、10代のそうした経験が、自分の興味を引き出すきっかけになったのだと思います。
ところで、私は「色」にも興味がありました。私の名は「紫」、妹は「茜」。これは祖父が研究者としてフィルム会社で色の開発に携わっていたことが影響しているように思います。名前も日本的ですし、せっかくなら日本の美術史を研究してみようと考えました。中でも当時、研究者が今ほどは多くなかった浮世絵に惹かれ、「おもしろいかも」と直感しました。
その頃は、日本のことを知ることが、世界を知ることにもつながるのでは、と感じて、日本美術を通して、海外に日本のことを紹介できる仕事がしたいと思いました。また日本にいながら日本の良さに気づかないこともあるので、次第に、それを国内から発信していきたいと考えるようにもなりました。
私は幼稚園から大学院まで学習院で学びましたが、幸運にも学習院大学には、浮世絵研究の大家である小林忠先生(学習院大学名誉教授、岡田美術館館長、国際浮世絵学会会長)がいらっしゃいました。小林先生の元で学びたいと、迷わず文学部哲学科に進学。大学3年生のときには「もっと研究をしたい」と、大学院に進むことを決めました。
自分に向けて投げられたボールはできるだけ打つ
 |
そうして教壇に立つようになるのですが、まさか、自分の興味がここまで広がり、教える立場になるとは思っていませんでした。自分としては、目の前のボールを打ち続けてきたという感じで、それがどこに飛んでいっているか、次のボールがあるかどうかもわかりませんでした。ただ、投げていただいたものはできるだけしっかり返そうと思って、ここまできました。
私はさまざまな大学で、美術史を中心に、染織や服飾、江戸文化論など多彩な講義を受け持たせていただきました。その時々で私にとってはチャレンジなのですが、それらすべてが今の研究の基盤となっていると感じます。これまでファウルも空振りもあったかもしれません。けれども自分なりにがんばったと感じた時、何かが残ります。私の場合、「経験」であり、「人とのつながり」であったと思います。だからこそ、若い人には目の前のことを一生懸命にやり続けて何か成し遂げて欲しいですね。
「いまの学生について思うことは?」と聞かれると、自分の大学生時代もいろいろ言われていたと思いますし、そもそもいつの時代も「若者はここがいけない」と言われてきました。江戸時代でもそうだったんですよ。簡単に「いまの学生は」とは言えないなというのが実感です。学生は自身の鏡でもあると思っていますし、私としては一人ひとりをどう見ていくかが自分の課題だと感じています。ただ、彼らが大学を卒業後、「大学っていいところだったな」と思ってくれたらいいですし、できれば在学中に、「限られた時間の大切さ」を知って欲しいですね。
私は「学び」と「遊び」は似ていると思います。共通しているのは好奇心。やる気があれば社会人になってからでも学べます。いつの時点で学んでも「学べるのは楽しいことだ」と思って欲しいと思います。江戸文化に遊び心があふれていたように、自分の学びの中に楽しみや自分なりの遊び心を見つければ、それは一過性のものではなくライフワークになる可能性を秘めています。
子どもは小さな大人、大人は大きな子ども。
大人になっても好奇心を忘れずに学び続けていこう
 |
子どもたちに浮世絵の魅力を伝えるとしたら「コミックスを読むように浮世絵を見るとおもしろいよ!」と伝えたいですね。実際、寝ている子の夢の内容がフキダシに描かれていたりと、コミックスのような浮世絵もあるんですよ。描かれている子どもたちも、やんちゃだったり、おねしょしていたり、女の子がおしゃれをしていたりと、子どもってこんなだったよね、と思いますし、今と変わらないことがわかります。
 喜多川歌麿 夢にうなされる子どもと母 |
江戸時代は子どもが早く亡くなることも少なくなく、家族を置いて江戸に来ていた父親が、「うちの子もこんなに元気だといいな」などと願いつつ、母子を思って浮世絵を買っていったのかもしれません。「子どもが元気でいれば、その社会は幸せ」というのは今も昔も変わりないと思います。
私は「子どもは小さな大人、大人は大きな子ども」だと考えています。子どもの想像力や大人になる過程の推進力はすごい。そういうものを刺激できるように、大人は子どもを見守ってあげるといいのではないでしょうか。そして大人は経験があるからこそ、学ぶことの大切さをご存じですよね。人生の転機を迎え、時間や気持ちに余裕ができたり、あるいは多忙な中でも学ぶことで気持ちに余裕ができることもあります。そうした時に、大人の中にある子どものようなワクワクした好奇心を大切にしていただきたいと思います。
私にとって大切なのは、やはり大学における「教育」と浮世絵を中心とした日本美術の「普及」活動。そしてこの2つを支えている「研究」活動です。やはり自分がもっと勉強しなければならないと思いますし、改めて今、とても学びたいと思います。
この教育、普及、研究という3つを丁寧に続け、好奇心を刺激できるような講座や書き物、展覧会の企画などをしていきたいですね。また浮世絵を育んだ江戸や明治時代と、社会や美術業界など周縁との関わりを、広く捉えて紹介していきたいと考えています。授業や講座でお話ししている事柄をなるべく早く文章化して、より多くの方に精力的にお伝えできればと思っています。そしていつか、自分のイラスト入りで、子ども向けの楽しい浮世絵の絵本を製作できたら素敵ですね。
関連リンク 國學院大學メディアくもん子ども浮世絵ミュージアム『くもんの子ども浮世絵コレクション 遊べる浮世絵 江戸の子ども絵・おもちゃ絵大集合!』 練馬区立美術館
 |
前編のインタビューから -「日本美術はこんなにおもしろい」 |
おすすめ記事
-

トピックスインタビュー
Vol.337
特別対談 ブレイディみかこさん×KUMON
2019年話題のノンフィクション本と KUMONに共通する思いは 「自分の力で人生を切り拓いていける人に」
-

スペシャルインタビュー
Vol.073
特別対談 棋士 藤井 聡太さん
終わりのない将棋の極みへ 可能性のある限り 一歩ずつ上を目指していきたい
-

学習経験者インタビュー
Vol.093
弁護士・ニューヨーク州弁護士
松本慶さん少しずつでも前進すれば大丈夫 「一日一歩」の精神で歩いていこう
-

KUMONグループの活動
Vol.491
輝く!大人からのKUMON2023
―ドイツ語・公文書写・脳の健康教室それぞれの目標に向かって 継続することが いきいきと輝き続ける秘訣
Rankingアクセスランキング
- 24時間
- 月間


















