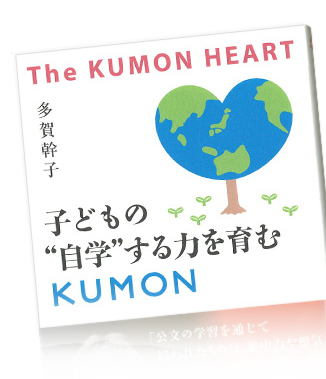アメリカ流“ほめて励ます子育て”に
目からウロコだらけの毎日
 |
子どもを保育所へ行かせると時間が作りやすくなり、仕事の幅が広がっていきました。しかしそんな矢先、夫がニューヨークへ転勤することに。せっかく積み重ねてきたキャリアがゼロになってしまうのは残念だと思いました。
それで長女が愛読していた幼児雑誌の編集部に、「お願いがあります」と売り込みに行ったんです。「子どもがニューヨークの現地校に通うことになりました。日本の幼稚園とはきっといろいろなことが違うはずなので、それをルポしたら面白いと思う」ってね。
じつはその編集部との間では、それまで仕事をしていたわけではなく、ただの一読者でした。そんな先への売り込みなんて、今思えば若気の至りというか、図々しいというか……。ところが編集者はアメリカの幼稚園・小学校体験に興味を持ってくれて、その場で承諾していただきました。ありがたいというか、本当に人に恵まれていたのだと思います。
そうして米国滞在中から現地のことをいろいろ書き溜めているうちに、他の出版社からも声がかかるようになり、『その名はアメリカ大統領夫人(ファースト・レディー)』(徳間書店)や『広い国で考えた狭い国のこと』(PHP研究所)などの刊行に至りました。書籍を出すことの影響は大きく、その後さらにたくさんの執筆依頼をいただくようになりました。
米国での生活は刺激的で、教育に関してもとてもおもしろかった。子どもたちは現地の公立校に行かせていましたが、米国では一人ひとりを大事にして、ほめて育てます。日本では「落ち着きがない」「次の学期に期待します」と通知表に書かれていたような場合でも、米国ではしっかりほめられる。すると子どもは笑顔になる。親の私も「素敵なお子さんをお持ちで、なんて幸運なお母さんなんでしょう」と先生から言われました。先生はほめ言葉を出し惜しみすることなく、良いところをよく見ていてすぐにほめてくれる。 私も子どももアメリカの先生が大好きでした(笑)。
授業では、1つのクラスの子どもたちが能力別に4~5グループに分かれて学び、それを一人の先生が見て回ります。グループごとに教科書も違う。その子の能力にあったところを学ばせていたのです。それを父母も当然のこととしてサポートしている。弱点をしかるのではなくその子の長所を伸ばせばよいとか、子どもと一緒に親も育つべきとか、教育とは一方的に教え込むのではなくcultivate(耕すこと)であるとか、目からウロコがボロボロ落ちました。
米国では5年暮らし、その後一度日本に戻った後、今度は夫が英国・ロンドンに転勤することに。またゼロからのやり直しでしたが、かつて父の転勤であちこち住んで鍛えられていましたし、どこへ行っても人間の営みに大きな違いはなく、仕事に励み家庭の幸せを願って日々懸命に生活しているのだと捉えるようになっていました。
すべての人から私たちは学べる
「知りたい」という姿勢を大切に
 |
私はこれまで、著名人から一般の方々まで、多数の人にインタビューをしてきました。私の場合、インタビューには十分な準備をして臨みます。インタビュー相手に関する書籍や記事はもれなく読み、そしていったん全てを忘れます。すでに書かれているものが頭に残っていると、「こう尋ねたら、こう答えるだろう」という先入観にとらわれてしまうからです。実際にお会いする際には、真っ白な新鮮な目で向かい合うようにしています。
もうひとつ意識しているのは、すべての人に学ぶべきこと、聞くべきことがあるはずで、それを皆さんに伝えたい、という思いを持つことです。お話を聞けてうれしい、楽しいという気持ちが相手に伝われば、どんどん話してくださいます。「お話しするのは初めてだけれど」と言われるとインタビュアー冥利に尽きます。相手の身になって考え、相手との会話を心から楽しむことですね。
子育てしながら仕事をする私に、夫は協力的でした。夫や母の手を借りながら、できる範囲で仕事を続けてきましたが、私にとっては仕事も子育ても両方大事。子どもが元気で幸せな状況だからこそ心置きなく働けるわけで、感謝の気持ちをいつも持っていました。バランスを取るのに苦労もしましたが、仕事を続けてきたのは、やはり人が好き、お話を聞くのが好きだから。すべての人に聞くべきことがあり、それを皆さんにお伝えしたい。おこがましいようですが、それが私の役割ではないかという使命感があります。
人にとって学びは一生。若いころの20年、30年はもちろん大事ですが、寿命が延びた今、若い時の学びだけでは持ちません。人のライフステージは変わっていきますが、そのたびに学ぶ習慣や調べる姿勢がないと、世の中に取り残されてしまいます。「知りたい」という姿勢を持ち、アンテナを高く掲げ、ピンときたものは理解して使いこなせる学習習慣を若いうちに身につけておくこと、「一生自分に学びを課す」積極的な姿勢でいることが大事です。
子育て時代を楽しまないと損
自分の子育てをほめてあげよう
 |
私には息子と娘が一人ずついますが、性差をつけないように、また無理強いをしないように、と心がけて育てました。子どもたちはもう30代ですが、進むべき道に進んでいったと思います。今考えると、親ができることというのはそれほど多くはないと感じます。子育て真っ最中の親御さんは、「親が何か言えばなんとかなるのでは?」と思われるかもしれませんが、子どもは実は自分を良く知っていて、結局は自分の道を自分のペースで歩みます。
とはいえ、親は子どもに「こうしてほしい」と希望は言っていいと思います。ただし「私はこう思う」と、一人称で言うことが肝心です。「あなたはこうすべき」と押し付けてしまうと、子どもは息苦しくなってしまいます。子どもは親が思っているより賢くて、親の言うことを取捨選択して聞いています。親は、子どもは思い通りにならないことを受け入れないといけません。期待しながらも期待しすぎないように自制する。そこに“大人の知恵”を働かせるべきです。
わが子の思春期も大変でしたよ。でもそれは、「ホルモンバランスがそうしている」と思うようにしていました。思春期はいわば“ホルモン漬け”になっている時期(笑)。一番戸惑っているのは子どもでしょう。親として言いたいことはたくさんあるとしても、「おはよう」「おかえり」の挨拶程度で抑えるくらいがちょうどいいのかもしれません。子どもの親離れは止められないし、それは健全に育った証拠です。
お母さんたちには、「自分の子育てをほめてあげて」と伝えたいですね。子育て時代は意外に短い。楽しまないと損です。もちろんつらかったり、悲しかったり、イライラしたり、歯痒かったりすることも、たくさんあります。でもそれらには必ず終わりがあります。子育てを通じて自分が成長していると思ってみてはどうでしょう。
今の時代、母親のプレッシャーやストレスは相当大きいと感じます。抱え込まず、周りに助けを求めてほしいですね。それには人を信じて一歩踏み出してみること。そうしないと何も始まりません。私自身もそうして助けられてきました。私はお母さんたちに、子育てに自信を持ってもらいたいと思っています。そのために、執筆活動を通じてお母さんたちに元気になってもらえるようなメッセージをこれからも送っていきたいと思っています。
関連リンク
ジャーナリスト・多賀幹子さんが見たKUMON|KUMON now!