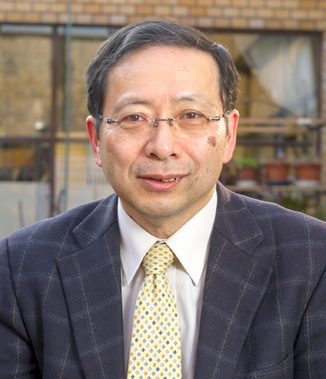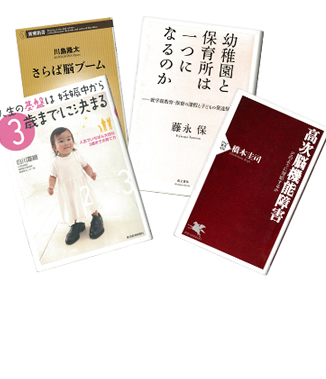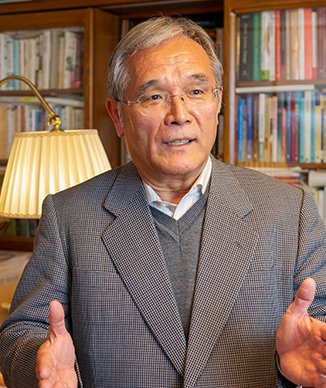【おことわり】この記事でコメントくださっている方たちは医療従事者(公文式学習者のお二人は除く)であり、コメント中には患者様の個人情報も含まれるため、個人情報保護、また医療機関としての守秘義務もあり、詳細に記述できない箇所が少なからずあります。どうぞご了承ください。
患者さんたちの社会復帰の大きなポイントのひとつは
地域連携のサポート
 浅倉部長(作業療法士) |
大分県大分市。JR大分駅から豊肥本線で一駅の滝尾駅から歩いて5分と少し、静かな住宅街の一角に諏訪の杜病院(医療法人光心会)はあります。整形外科やリハビリテーション科をはじめ10以上の診療科がある病院ですが、大分県では高次脳機能障害(以下「高次脳」と表記)の方たちを支援する拠点病院として知られています。
朝8時すぎから三々五々患者さんたちが来院し、9時前には玄関すぐの待合室はほぼ満席です。「おはようございます」、「きょうの体調はいかがですか」など患者さんたちと病院スタッフとの元気なあいさつがそこかしこから聞こえてきます。この方たちの大半は、高次脳をはじめさまざまな病気やケガなどの回復のためのリハビリテーション(以下「リハ」と表記)をするために来院されています。
まず、高次脳の拠点病院としての役割や課題などを、諏訪の杜病院の浅倉部長(作業療法士)にうかがってみました。
「拠点病院そのものの役割としては、高次脳の評価や診断を適切に行うことはもちろん、そのあとリハの訓練で認知機能を高め、代償手段も使いながらさまざまな機能回復をめざします。それと、復職や復学なども含めた退院後のサポートのため地域の支援機関や支援者と連携し、支援体制の構築に努めています。拠点病院はそれらに加え、高次脳への理解を広めるための啓発活動や幅広いネットワークづくりに力を入れています。」(浅倉部長、以下同じ)
「国が定める狭義の高次脳はそのリハも含め、本格的な治療の対象となってからまだ10年ほどです。そのため言葉自体のなじみもまだまだ浅く、症状がお一人おひとり異なることもあり退院後のサポートが大きな課題です。当院に来られる患者さんは比較的若い方の割合が高いこともあり、退院後の目標は復職・復学が多いですね。子育てを含めた主婦業にもどりたいというご希望の方も少なくありません。そのときポイントになるのが身近な地域のサポートなのです。」
「公文式学習者で印象に残っている方がいます。医療機関としての守秘義務があるので、詳しくはお話しできないのですが…。脳炎で集中治療後、当院に来られた方です。身体のマヒなどはないのですが、全般的に高次脳の影響で入院当初は基本的な日常生活も声掛けなどの介助が必要な状態でした。まずは、通常のリハに加え、公文式学習も併用し、注意集中力や作業スピードの向上に努めました。ご本人は、毎日大忙しの入院生活です。1か月ほど経過すると全般的に高次脳に改善を認め、記憶障害が主な症状として表面化しました。そこで作業療法のリハで調理を開始。開始当初は、イチゴヨーグルトを作るときボールにイチゴを入れ、その上にヨーグルトをかけると “あっ、イチゴがない!”という状態。そこで毎夕の病院食をいったんお休みにして、作業療法士といっしょに夕食を作って食べるというリハを追加しました。それに慣れてきたら、一緒にバスに乗ってスーパーへ行き、1週間分の食材を買うトレーニングもしました。そんなリハをくり返しようやく退院を迎えました。」
「けれど、ご本人がたいへんなのはここからです。家事、子育てと自分以外の生活にも目を向けないといけません。退院前には、自宅近くの高次脳をフォローできる病院探し、お住まいの地区担当の保健師さんとの連絡調整、家族への障害説明や指導などを行いました。このように地域のいろいろな支援者を巻き込み、家族を含めた生活支援の体制を整える必要があります。幸いなことにご実家が近く、毎日の料理をご実家のお母さんと作り、自宅へ持って帰るという生活が確立しました。いつも感じることですが、こうした地域の連携があるからこそ、患者さんたちはふつうの生活に近づき、社会復帰ができます。ほんとうに感謝の言葉しか浮かびませんね。」
※高次脳機能障害・・・脳卒中などの脳血管系の病気、交通事故による脳挫傷などの脳損傷が原因で、脳の機能のうち、言語や記憶、注意、情緒といった認知機能に起こる障害を高次脳機能障害と言います。記憶力や注意力の低下、感情のコントロールが困難になるなどの症状も現れますが、その症状は百人百様です。
「高次脳機能障害の患者さんを受け入れる」「公文式もする」という突然の院長の言葉にみなビックリ
 どんぐりの杜クリニック |
ここ諏訪の杜病院では、作業・理学・言語聴覚療法などのリハにプラスアルファとして、希望される患者さんは公文式学習ができます。どんなふうに学習しているのか、ちょっとご紹介しましょう。
病院1階の広いリハ室隣にある言語聴覚室が、毎週火・水・木・金の10時30分から12時まで学びの場に様変わりします。10時30分少し前になると、リハを終えた入院・通院の方たちが入室。ウォーミングアップの音読のあとすぐに、公文式国語、算数・数学の順に、見事な集中ぶりで12時まで学習が続きます(途中休憩あり)。隣のリハ室からは、それぞれのリハに取り組む患者さんたちと療法士さんたちの笑い声や元気なかけ声が聞こえてきます。しかしこの部屋のなかでは、鉛筆の走る音しか聞こえません。その凛としたたたずまいは、学びの場というより修業の場のようにも感じられます。
時期によっても異なりますが、いつも5~6人の方たちが学習されていて、年齢も20代から70代と幅広いです。みなさん高次脳ですが、その原因も症状も千差万別で、学習する教材もそれぞれ違います。身体のマヒがある方もいれば、視野や発語に課題がある方もいます。しかし学習中は障害があることはほとんどわかりません。高次脳の子どもたちも10人ほど学習していて、道路を隔てた別の棟(どんぐりの杜クリニック)で、毎週土曜日にリハとともに公文を学習しています(後述)。
公文式導入までの経緯を浅倉部長にたずねてみると、意外な答えが返ってきました。
 諏訪の杜病院 武居院長 |
「いま当院は高次脳の拠点病院ですが、その受け入れをはじめたのは2005年からで、まだ12年という歴史です。受け入れをはじめたのも、院長の武居から2005年のある日、“高次脳の患者さんを当院で受け入れて支援をするから、いろいろ調べて準備してほしい”と突然言われたことがきっかけでした。病院のドクターを含むスタッフ全員が唖然というか、すごくビックリしたのを昨日のことのように覚えています。2005年といえば、高次脳の支援体制を整えるべく全国でモデル事業が展開されている時期で、医療関係者のあいだでも、その認知度は低いころだったと記憶しています。そんなころですから、そのときは武居院長が何を話しているのか理解できないスタッフがいたかもしれませんね(笑)。」
「しかし、武居の話をよく聞いてみて納得できました。ある日の地元紙に、『脳外傷友の会おおいた』の会長さんの“高次脳は社会的な理解度が低く、支援のはざまにある”というコメントが載ったそうです。それを読んだ武居が居てもたってもいられず、その会長さんに会いに行き、“これはなんとかしなくては!”と思い立ち、先の“…受け入れて支援をする”という発言につながったということがわかりました。」
ちなみに、武居院長の口癖は「陽の当たらない場所に陽を当てる」とのこと。まさに有言実行。
「それで、あわただしく準備し高次脳の患者さんの受け入れをはじめたのです。しばらくして、武居がこんなことを言いはじめました。“高次脳の患者さんには公文がいいらしい。神奈川県の病院(神奈川リハビリテーション病院)では、高次脳の患者さんの家族会が中心になって学習の場を作っていて、公文の会社もサポートしている。だから、うちでも公文をやってみよう”。高次脳の話も突然だったのですが、公文の話もあまりに唐突でしたね(笑)。」
「公文の話を武居から聞いてすぐは、医療の現場に教育を…?と疑問ばかりでしたが、高次脳の認知リハのなかには百ます計算や文章を読むような課題もあると気づき、疑問や違和感はなくなっていきました。反対に、体系だった教材と指導法があると聞いて、心強いとも感じました。ただ、これまでずっと医療として患者さんにリハをしてきたわたしたちが、教育という面でも患者さんに対応する。リハにプラスアルファでの学習とはいえ、それなりの責任の重さを感じ、不安な面があったことはたしかです。」
「公文式学習をすることには、不思議と院内には反対意見はなかったですね。それは、院長の武居自身が“患者さんが良くなるのなら、なんだっていいんだよ。終わり良ければ全てよし!”という考えなので、スタッフたちも“それもありかな”という意識だったのかなと思います。」
「そして、実際に2006年から公文式学習をはじめてみて、その大切さが実感できました。先ほども申し上げた通り、当院に来られる患者さんの多くは復職や復学、つまりふつうの生活にもどることが目標です。けれど、ふつうの生活にもどるためには、病院での医療としての作業・理学・言語聴覚療法などのリハだけでは足りないのです。いい意味での負荷やトレーニングがもっとあれば、復職や復学の可能性がさらに高くなるといつも考えていました。まさしく公文の学習がその負荷やトレーニングになると感じられるようになってきたのです。」
リハビリテーションと公文式学習の共通点
“できることを増やす”
療法士さんの日々の忙しい業務のなかで、公文式学習の指導をする惠藤先生(臨床心理士)と二宮先生(言語聴覚士)のおふたりに、学習を通しての患者さんたちの変化や成長をうかがってみました。惠藤先生は主に大人の方たちの、二宮先生は主に子どもたちの指導を担当されています。
 二宮先生(言語聴覚士) |
 惠藤先生(臨床心理士) |
「個人差はありますが、10枚、20枚と教材に集中して取り組むという、作業・言語聴覚療法のリハに近いトレーニングをしていることになりますから、全体的には集中力や注意力が培われます。それが機能としての記憶や遂行機能の底上げになっていると感じますね。もちろん、学習を続けていくモチベーションとして100点をとることでの満足感や達成感、それらが積み重なっての自己肯定感も育っていると思います。もう少し細かく見ていくと、注意や集中を持続しにくい方は、学習の後半でミスが出やすくなるという傾向があります。そんな方には“学習の後半も集中しましょうね”と声をかけるだけでも注意が持続できてミスが減り、ご本人の自信につながるということがあります。細かいことのようですが、職場に復帰して仕事をするという場面で役立つのではと思っています。」(惠藤先生)
「わたしは主に小・中・高校生の子どもたちを担当していますが、半年、1年、2年と学習を続けていくと、ほんとうに変わっていきますね。たとえば…宿題を“する”、“しない”でご家族との摩擦が大きくなってしまいかんしゃくが出やすかった子が、公文でできることが増えてほめられると学習に前向きになる。すると宿題もやるようになり、かんしゃくを起こす回数が減っていき、やがてはなくなってしまう。また、勉強がイヤだと学校で暴れていた子が、公文で学習する習慣を取りもどすと、見違えるように落ち着いて授業を受けるようになり結果的に学力が上がる、といった変化です。わからないところを質問できないような子が、学習を続けていくと不思議と“教えてください”って聞けるようになる子もいます。モジモジと引っ込み思案だったのに、急にハキハキ話すようになった子もいます。自信がついたのでしょうね。ほんとうに、たくさんの成長があります。」(二宮先生)
「発達障害の子にも似たところはあるのですが、高次脳の場合、大人も子どもも、ある日突然に病気やケガでできないことが一気に増え、困り度もすごく大きくなってしまいます。そして、そのことをご家族も含めた周りに理解してもらいにくい。自分自身もそのことが受け入れられず、さらにフラストレーションがたまってしまう。これは想像しただけでもたいへんなことです。リハは、できなくなったことを再びできるようにしていくことですが、シンプルに“できることを増やす”と考えてもよいと思っています。それも、楽しく、笑顔で、できることを増やすのがいちばんですね。わたし自身も病院全体でも、このことを大切にしています。“できることを増やす”という意味では、公文式学習も同じですね。できることを積み重ねながら、少しずつできることを増やし、レベルアップもしていくわけですから。」(浅倉部長)
さて、最後に学習者の方おふたりに、学習をしての感想や手応えを聞いてみましょう。おひとり目は、中学生のときの事故で受傷。入院治療後、復学を目標に諏訪の杜病院を受診し、ほどなく公文式学習を開始したSくん。どんぐりの杜クリニックに移ってからも学習を続け、成人した現在も続けています。[算数D(小4相当)、国語CⅡ(小3相当)学習中]
「わるいんですけど、公文の学習はあまり楽しくありません(笑)。でも、みんなとプリントをしたっていう達成感がうれしいです。国語はいいですね。誰かと話すとき、きちんと文章として話せるようになったし、このごろは、相手の気持ちを考えるようになったと思います。」
なるほど、楽しくはないけれど、学習効果は実感しているようですね。しかし、Sくんは公文の学習室で教材に向かっているときも、二宮先生と話しているときも終始笑顔が絶えません。「やっぱり、楽しいんじゃないの?」と聞きたい気持ちでした。
おふたり目は、50代のGさん。2年前に交通事故にあい、脳を損傷。高次脳の主な症状は記憶障害。2015年から学習をスタートしました。こつこつとひたむきに学習する姿が印象的です。[数学F(小6相当)、国語FⅡ(小6相当)学習中]
「この病院で公文をやっていると聞き、それも回復へのひとつのトレーニングだと思い学習をはじめました。初めにやったテスト(学力診断テスト)はひさびさで緊張しましたが、教材を解いてみると楽しくできました。いまは、公文の学習が生活の一部になっていて、リハのあとは公文をするという習慣がついています。効果ですか?リハも含めてですが、けっこう正常に近づいていると感じています。」
取材を終え帰り支度をしていると、こんな光景が病院の玄関にありました。高次脳で通院中の小学生の女の子が学習を終えて、お母さんと一緒に浅倉部長、二宮先生、惠藤先生と談笑しています。2時間ほど前にリハビリ室と公文の学習室で見た、一所懸命な顔とはまた違う晴れやかな表情でした。しばらく談笑したあと、その女の子とお母さんは連れ立って病院をあとにしましたが、よりそいながら歩いていく、ふたりの後ろ姿からは、「きょうもがんばったよ、お母さん」「よく頑張ったね。えらいね」という会話が聞こえてくるようでした。