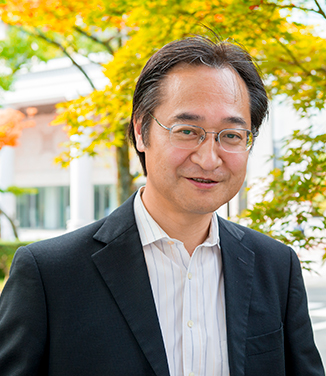誰もが閲覧できるオープンな博物館を目指したい
 |
私がデジタル・アーカイブに熱心なのは、「誰もが自由に有形・無形の文化資源を閲覧できるようにしたい」との思いがあるからですが、それは学部の卒業論文を書くときに体験した、ある悔しさが原動力になっているのかもしれません。
卒論のため、江戸期の歌舞伎作者の自筆台本などの原本を確かめたいと、早稲田大学の演劇博物館へ行ったのですが、学部学生には原本の閲覧は許可してもらえませんでした。それでも何度も足を運んでお願いし、ようやく見せてもらうことができました。
その後、その演劇博物館のある早稲田大学大学院に進学したのですが、私の研究対象は、舞台そのものから日本演劇の歴史的な史料そのものへと変わっていきました。そもそも大学院では、私より歌舞伎や演劇に詳しい院生がたくさんいて、なかなか太刀打ちできませんでした。そこで、くずし字が読めるという自分の得意なことを活かせる分野に進んだのです。
ちょうどその頃、研究室にコンピュータを導入することができたのは幸いでした。これまで手作業でカードに書いていたものを、コンピュータにどんどん入力していく仕事を買って出て、一晩寝ずに入力することもありました。この情報整理が当時の私の役割で、今振り返ると、これがデジタル・アーカイブの始まりでした。地道な入力作業は大変と思われるかもしれませんが、好きなことなので楽しかったですね。
折しも、私の指導教授で、江戸歌舞伎研究者の鳥越文蔵先生が、第5代目の演劇博物館館長に就任されました。鳥越先生は、演劇博物館を開放的にしていくプロジェクトに取り組まれたのです。鳥越先生は、史料好きの私をこのプロジェクトを推進するために博物館所属の助手として抜擢してくださり、まずは博物館の所蔵品の情報共有化に着手することになりました。とはいえ、すべての情報を公開できるようにするには、技術がないと難しく、工夫が必要でした。そこで、コンピュータを活用したデジタル・アーカイブへと踏み出したのです。
大変なものを大変と言わず、「工夫」することが大切
 |
デジタル化の作業はたしかに大変です。ただ、大変なものを大変なように言っては駄目で、「工夫」することが大切でしょう。
工夫のひとつは考え方を変えること。たとえば、海外の博物館に行って、その博物館のコレクションのすべてをデジタル化するというようなとき。テーマの決まったある一つの論文のためにそのデジタル化の作業に取り組むと考えると、その論文とは関係のないものもありますから、「なぜ関係のないものまでも?」と苦痛に感じるかもしれません。しかし、「ここの博物館のコレクションの系譜を見る」というように目的を転換すれば、その作業は苦にはなりません。その目的はコレクションのすべてを見なければ達成できないのですから。
もうひとつの工夫は作業上のこと、具体的にいえばデジタル撮影の方法です。われわれは「すべて」を撮影するので、いちいち「このページのこの部分が必要」などと考えません。だからといって単に撮影すればいいというわけではなく、誰もが使えるように撮らねばなりません。その際、資源の中身をわかっているのとわかっていないのとでは、大きな差が出てきます。
また、デジタル化の問題点として、撮影時の光や現物を触ることにより「資源を壊す」ことが挙げられますが、われわれは訓練を重ねて修復まで学んでいるので、そうしたことを極力避けることができます。そこが業者に任せた場合と異なる点です。
そもそも研究者にとってデジタル化の作業は、生の史料に直に接することができる、絶好の機会です。これほど興奮することはなく、私もいまでも自分で撮影しているほどです。
自分の好きなことを突出させることが
社会への責任を果たすことになる
 |
私が思う「学び」とは、自分で積極的に工夫をし「発見していくこと」です。それは好きだからこそできるのであり、「好き」を見つけるには、基本を押さえたうえで広く物事を見たり体験したりすることが欠かせません。
最近の学生を見ていると、工夫が足りないと感じます。与えられたものそのままではなく、そこに工夫がほしい。最初からできないと思わず、あるものを使って新しい価値を生み出していくことはできないかと考えてほしい。子どもたちにそういった工夫や発見を促すには、親は言い過ぎないことが大切だと思います。
大勢の人の中にいると人間は「自分は人より劣っているのでは?」と思いがちです。でも、誰にでも必ず優れているところがあります。ですから、苦手なものは置いておいて、好きなものを伸ばしてほしい。それが結局、世の中に対して責任を果たすことになるのだと思います。「能力があること」を活かして貢献できるわけですから。「何でも平均以上」ではなく、自分の好きなことを突出させるほうが、世のためにもなるし自分も楽しく生きていけます。
私自身は、「国語が苦手」でしたが、国文学の世界で私のようなデジタル・アーカイブの仕事ができる人はいません。しかし物理学や情報学では、私と同じようなことをできる人はたくさんいるでしょう。また、国文学研究の世界では、英語などの外国語ができる人も少ない。ですから日本文化研究のなかで、デジタル・アーカイブをすることこそが、私が伸ばすべきところだと自覚しています。
私がデジタル・アーカイブに着手した当時は、誰もそこに向かっていない状態でしたが、いまや「文化情報公開」の活動は、世界的に大きな流れになっています。自分のデジタル・アーカイブの技術でその流れにさらに貢献していきたいですね。
ほかに成し遂げたいこととしてあるのが、いくつかのテーマ、とくに浮世絵に関して、世界に散らばっている全作品のデータ化を完成させることです。また古典籍(明治頃以前に日本で出版・書写された書籍)については、日本国内にあるものについては、国文学研究資料館が情報整理を進めていますが、海外にある古典籍は扱っていないので、そこにわれわれが取り組めば、大きな貢献になると考えています。
夢を実現させるには、逆境でも「なんとかしよう」と工夫して、楽しんでやることが大事です。私自身、そうしてきました。それでいまに至っているのだと思いますし、これからも「好き」を楽しんでいきたいと思っています。
関連リンク立命館大学アート・リサーチセンター
 | 前編のインタビューから -デジタル・アーカイブとは? |