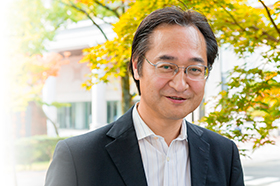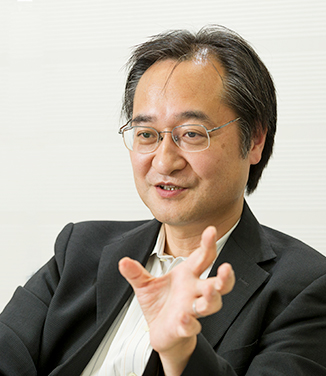埋もれていた文化資源を見つけ、育てていく
 |
私はもともと日本の文化、特に江戸時代の文学・芸術・芸能が専門です。学びのジャンルが広がったいま、文化は情報としてとらえられていて、今は「日本文化情報専攻」の教員として学生を教えています。これは、文学、絵画、演劇などを情報の観点で探求することに加え、「資源」を管理・整理する図書館学や書誌学などの視点も導入した学問です。
「資源」とは、かつては「史料」と言われていたものです。「史料」だと専門家のみが使う「価値あるもの」だけになってしまいますが、そうではなく、いままで知られていないすべてのものを拾い集め、可能性を広げていくという考え方からきています。これは世界的な潮流となっていて、デジタル・アーカイブの世界でも、「文化財」や「文化遺産」ではなく、「文化資源」と表現する場合が多くなりつつあります。
「資源」は世界中に散らばっており、その一つひとつに命があります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた油彩画「モナ・リザ」は資源のトップスターと言えるでしょうが、一方でまだ誰にも見向かれない資源もあります。その埋もれていた資源の可能性を見つけ、磨きあげて育てていくのが私の仕事のひとつで、そういう意味では一人ひとりの可能性を見つけて伸ばしていく教育活動と同じですね。
その実現に役立つのがデジタル・アーカイブなのです。大学では、デジタル・アーカイブによる資源の保存や活用を研究しています。今年も、私が指導している大学院生がイギリスにある大英博物館にインターンシップに行ってきました。彼らは研究室で資料の取扱いだけでなく、デジタル技術を修得して、それを武器にして大英博物館が求める「各種コレクションのデジタル化」に貢献できるのです。こうしたデジタル・アーカイブの教育メソッドを実践的につくっていくのも、私の仕事の一つだと思っています。
日本は過去のどの時代においても、世界でもまれにみる魅力的な文化をもっています。海外からは「あれも、これも素晴らしい」と言われるほどですが、当の私たちはそれをあまり意識せずに生活しています。自分たちが考える「価値あるもの」にしか目を向けず、日本文化のもつ可能性を断切ってしまってはいないでしょうか。
しかし、デジタル・アーカイブによって、埋もれている「日本文化の素晴らしさ」にも光が当たる可能性が出てきます。誰もがどこでも閲覧できるので、片隅に転がっていたものが注目を浴びる可能性があるのです。デジタル・アーカイブは学術研究を劇的に変化させましたが、日本への理解が進むことにも貢献すると思っています。
教わるのではなく、自分で工夫するのが好きな子どもだった
 |
私の生まれ故郷は、北海道はオホーツク海に面する雄武町という林業や漁業、酪農が盛んなところで、私は港のそばに住んでいました。スキーやスケートはもちろん、山で昆虫を捕まえては観察するなど、自然豊かな中でのびのびと育ちました。誰かに教わるのではなく、自分で動いて工夫するのが好きでしたね。たとえば釣りは、名人といわれるおじさんが釣っているのを隣で観察して、うまくなりました。
母の実家は網元で、漁師さんや住み込みで働く方など周りに大人がたくさんいる中で育ちました。そのためか、口が達者で、子どもながらに母を言い負かしたりしていたそうです。
小学5年生の頃に、苫小牧市に移り住みました。これまで住んでいた町に比べれば大都会。工業開発地域で工場が多く、道外から来た人が町の半分を占めていて、その都会的な人たちからずいぶん刺激を受けましたね。
勉強は好きではありませんでしたが、成績はよく、ずっと一番でした。でも道外から来た人たちはレベルが高い。彼らに負けたくない一心で勉強した覚えがあります。好きだったのは数学や物理。苦手な教科はどちらかというと国語でした。苦手だったのに、なぜいま国文学の道にいるのかというと、弱い教科を克服しようとして、結果的に国語に集中して取り組んだからかもしれません。
高校は札幌の進学校へ進み、下宿生活をしていました。同級生には留学経験のある子も多く、私も留学したいと親に訴えたのですが、うまく伝えられず、反対されてあきらめました。高校時代に熱中していたのは、小学校から続けていた剣道です。道代表の一歩手前まで行くなど好成績をあげたのですが、最後の最後で負けてしまって……思い出すと今でも悔しいですね。進路を決めるときは、友人に影響されて国語の教員になろうと思い、公立大学で唯一の教員養成系大学である都留文科大学に進みました。
初めて観た歌舞伎に衝撃を受け、進路を変更
 |
大学では教員になろうと思って勉強を始めましたが、「典型的な教員」に違和感を抱くようになりました。教育者を演じ続けなくてはならない、ということが自分には難しいと思ったのです。
そんなあるとき、たまたま自主ゼミで近松門左衛門の作品をくずし字で読みました。読んでいるうちに、実際に芝居を観てみたくなり、東京の国立劇場まで歌舞伎を観に行きました。いまの四代目坂田藤十郎さんが中村扇雀と呼ばれていたころ、近松作品を上演する「近松座」を結成したのですが、その初回を観ることができたのです。そこで「こんなもの観たことがない!」と大きな衝撃を受けました。すべてが素晴らしかった。これが私の人生の転換点だったと思います。
そこから歌舞伎の勉強をすることに決め、歌舞伎や文楽を見に行ったり本を読んだりして自主的に学びました。好きで勉強しているので、他の学生より詳しくなりますが、当然ライバルも出てきます。
ある学生はたくさんの関連書籍を集めていたので、「負けられない」と、私も集め始めました。やがて6畳の下宿部屋だけでは収まりきれなくなり、大学4年生のときには、同じ長屋の6畳間をもう一部屋借りて、そこを「書庫」にしたほどです。当時、月に10万円くらいは本代に費やしましたね。山中湖畔にある合宿向けの民宿でアルバイトをしてその本代を稼いでいました。
その頃には大学卒業後に教員になるのではなく、大学院で歌舞伎研究をしようと決めていたのですが、背中を押してくれたのが、現在都留文科大学名誉教授の楠元六男先生です。大学1~2年生のとき教えていただいた俳諧の授業に魅了され、親しくなっていきました。私の「書庫」にもよく来てくださり、私にとって兄みたいな存在となっていきました。最終的には楠元先生の勧めで大学院へ行くことを決めたのでした。
関連リンク立命館大学アート・リサーチセンター
 | 後編のインタビューから -赤間先生がデジタル・アーカイブに取り組むようになったきっかけとは? |