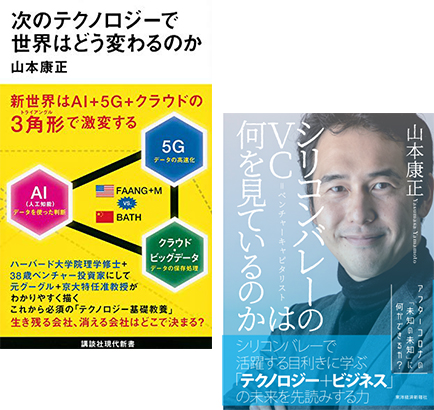ニューヨークで日本の存在感の薄さに衝撃
日本のポテンシャルを世界で活かすには?
 |
京都大学時代、交換留学でニュージーランドを訪問して環境問題に触れました。それがきっかけで、理系と文系がミックスされた分野を学びたいと考え、東京大学大学院に進みました。大学院時代には、外務省でインターンをして、途上国への円借款に触れ、金融の大切さを痛感。それで25歳で世界の金融の中心、ニューヨークへ渡りました。
衝撃的だったのは、経済規模では当時世界第2位だったにもかかわらず、日本の話題がほとんど出ないことです。勤務していた現地の金融機関でも、日本関連の取引高はどんどん減っていき、日本の存在感が薄れていくことに危機感を感じました。もっと学ぶ必要性を感じて、ハーバード大学公衆衛生大学院(パブリックヘルス)に入り、途上国に対する支援や公共投資、感染症対策など、社会課題に対してアプローチする方法を学びました。
ただ、ハーバード大学でも日本人は少数でした。そもそも出願する日本人、挑もうとする日本人が少ないんです。こうした状況を目の当たりにして、「日本がポテンシャルを活かして世界で活躍するにはどうしたらよいか」を考えるようになりました。
ベンチャー企業でも世界を目指そうという日本人はあまりいません。海外に出ていこうという選択肢が視野にないことと、英語力の問題が壁になっているのです。日本人はもっとハングリーに、自分の実力より10倍、100倍にチャレンジするくらいのたくましさがあってよいのではないでしょうか。英語については、「耳がいい」とされる小学生、プログラミング(データサイエンス)についても早めからやっておくべきだと思います。
自分の経験から、将来、留学や仕事で海外に出たいと考えている子どもたちには、「まずは行ってみて」と背中を押したいですね。世界に約70億人いる中、日本の人口は1億人あまり。日本の外にいる69億人を見て、肌で感じたうえで、自分がどうしたいかを決めるとよいでしょう。
気軽に挑戦してダメだったら帰ってくればいい。その悔しさをバネに、さらに英語を勉強するなどすればよいのです。ただ、「日本の常識は世界の非常識」という姿勢は持っていてください。また、学ぶ際に留意しておいてほしいのは、勉強の領域やキャリアは、一方通行の箇所が多いということです。理系から文系に移るのは、比較的簡単だったりしますが、逆は大変です。日本の大学から海外のトップレベルの大学院は大変ですが、逆は比較的入りやすかったりします。
保護者も情報のキャッチアップをして
子どもの「好き」を存分に育ててあげよう
 |
学びは10年、20年後に花が咲くものですから、保護者の方は、すぐに成果が出なくても焦らずに、お子さんを信頼して、お子さんが熱中する習慣、好奇心を持ち続ける習慣をつけてあげてください。言い換えれば、いかに子どもの「好き」を育てるかということです。例えば、「いいな」と思った人が発信しているブログを読み続ける、専門家とメールやチャットでつながるなど、テクノロジーを活用することで可能性はどんどん広がります。
このように今後、テクノロジーの土台の上にいろいろなものが成り立っていきます。オンラインでの授業が広がりつつあるように、学びもガラリと変わり、よりよい学び方が登場してくるでしょう。それを保護者の方がキャッチアップして、「今、教育は、技術は、こう変わっている」と理解していないと、子どもが出会えるものも変わってきます。情報源を学校や先生だけに求めるのではなく、保護者の方も広くアンテナを張っておいていただきたいですね。
一方、子どもたちには、「何が使えて何が使えないか」を瞬時に判断する力を身につけてほしいと思います。普段からデータの裏には何があるか、深読みする習慣をつけるといいでしょう。加えて必要なのは、一人の能力には限界があるので、専門家と議論できるような教養、そして同時に親しくなれる力です。日ごろから違う意見の人と議論し、「なぜそう思っているか」を互いに言えれば、「自分と相手の前提の違い」に気づけます。「根拠は何か」を考えるためには、「なぜこれに関心があるのか」など、何でもよいので記録しておくこともお勧めです。表現力や伝える力も磨かれます。
先行き不透明な中、保護者は我が子の将来も気になると思います。今は本業をひとつに絞れない時代。私は「何をやっているかわからない人が強い」と考えています。「仕事のかかわり方はひとつではない」ということです。私自身、投資家をしながら大学で教えていますし、分野は「金融」×「テクノロジー」というように複数の掛け合わせです。そうなると相乗効果があって楽しいですし、多面的に見られるようになります。
仕事を考えるにあたっては、「自分の好きなこと×自分の得意なこと(好きなだけでは得意とは言えません)×外部環境の将来の需要(現時点ではなく)」という視点を持つといいでしょう。いろんな選択肢を掛け合わせながら働くことが可能な時代ですが、子どもは選択肢を多く知りません。周囲の大人がふんだんに提示してあげることが必要です。
今見ている世界より、
“より広い世界がある”と常に考えて挑戦しよう
 |
子どもたちへのメッセージは2つあります。まず、「かっこいい大人は必ずいるよ」ということです。子どもたちにとって、今周囲に見える大人たちは魅力的に見えないかもしれませんが、“場”が変われば、必ずいます。私自身、ニューヨークで出会った人たちは、ものすごくおもしろい人たちで、とても刺激されました。つまり、今いる世界より、もっと広い世界があるということを常に考えてほしいのです。日本にこだわらず、早めに世界に飛び出すことも勧めたいですね。
大人になれば、間違いなく海外の同じ年代の子と競うことになります。彼らが今、何を考えているかを想像しながら、なるべく良い環境、最高の場所で、いろいろなことに挑戦してください。バンテージ・ポイント(見晴らしの良い場所)から学べば、未来がよりよく見えます。それでダメであればあきらめがつきますが、そうでなければもったいないことになりますから。
生物学でノーベル賞を取りたいと夢見て京都大学に行ったと言いましたが、人は自分が目指す目標より上に行くことはまずありません。選択肢を広げるために、「ハーバード大やMITを目指す」とか、思い描ける最高のことを志してください。
もうひとつは、「今のクラスメイトや赤の他人の目などは気にしなくてよい」ということです。6年後に今のクラスメイトと会う頻度はぐっと減るでしょうし、むしろ二度と会わない人がほとんどです。ずっと続くのは家族ぐらい。他人に何か言われたからといって、進路を変える必要もありません。他人は、あなたに何かを言って、それであなたが判断したことに責任をとってくれるわけではありません。SNSの「いいね」や反応に関係なく、「少し調べれば、詳しい人に聞いてみたら、もっとおもしろい世界があるかもしれない」という自分の好奇心を追い続けてほしいと思います。人生は自分のものなのですから。
最後に私の個人的な夢についてお伝えしましょう。私が実現したい未来は「もったいない」「機会損失」「不条理」などのない世の中です。仕事で成果を出した後、具体的には学校をつくること。暗記教育ではなく、英語教育やディスカッションを中心に、チームワークやリーダーシップを養うことに特化した学校です。医療も良くしたいので、病院もつくりたいですね。
そのためにも、まずは世界に必要とされるベンチャーやテクノロジーを十分に送り出し、成果を出したい。その上で、これまで私が身につけてきた学びを活かして、教育や医療の世界を変えていく。そんなチャレンジをしていきたいと思っています。
関連リンク
 |
前編のインタビューから -投資家として「世の中を変える技術」を応援 |