厚生労働省の資料によれば、児童養護施設の役割は「保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童(特に必要な場合は乳児を含む)を社会的に養護する」とあります。現在、全国に600か所ほどあり約3万人の子どもたちが生活し、近隣の学校に通っています。また、児童養護施設へ入所する子どもたちのおおよそ6割が虐待を経験しているという調査結果もあります。児童養護施設を含め、社会的養護を必要とする子どもたちが生活している施設の詳細は記事末尾の関連リンク「社会的養護の現状について」からご覧ください。
「われわれ園の職員の仕事は、 まさに子どもたちの本業である学習を支援することだと考えています」
窓愛園の近くには筑波大学があり、40年前に園の子どもたちの学習支援のための学生ボランティア組織ができています。40年前といえば、筑波大学が開学してまだ3~4年のころ。長い歴史のあるボランティア活動で、現在でも50人を超える筑波大学の学生さんたちが毎週学習支援に来ています。また、2010年からは、学習支援をさらに強化するために公文式学習(算数・数学)を導入しています。まず、そのあたりのことから上方仁(かみがたひとし)園長にお聞きしました。
 上方仁園長 |
「当たり前ですが、“子どもの職業は学生”ですから、いちばん大切なのは学ぶことです。けれども現実には、園に入ってくる子どもたちは学校の授業についていけないケースが多いのです。そうなると学校に行っても面白くない、授業を聞いているのが辛い。だから園に帰ってきて、ちょっとしたことが原因で暴れてしまうことも少なくありません。だからこそ、この状態を変えなくてはと思うのです。学ぶことを大切にしないとおかしなことになりますから」
「われわれ園の職員の仕事は、まさに子どもたちの本業である学習を支援することだと考えています。というのも、施設の子どもたちが衣食住足りて生活面で豊かになったとしても、それで将来幸せになれるのだろうかという疑問があるからです。やはり、将来の自立を考えれば、基礎学力や学びとろうという姿勢が必要です。また、自分を信頼できる気持ちがあればもっといいでしょうね。そのために、筑波大学の学生さんたちにも来ていただいていますし、公文式も導入させていただきました。とはいえ、一般的にはまだまだ、児童養護施設の子どもたちは学力が低いととらえられているようで、子どもたち自身も学力という面では劣等感をもっています。“窓愛園の子どもたちはみんな勉強できますね”と評判になってくれたらうれしいですし、わたしは何よりもそれが大事なことだと思っています」
「こうお話しすると、それはなかなか難しいのでは…と思われる方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、“園の子たちみんな勉強ができる”という状態はかなりハードルが高いと思います。しかし、可能性は十分あると思うのです。たとえば、園に入ってくる子たちのなかには、知的な障害や発達障害がある子もいますが、園で生活環境を整えることで、メンタル面でだいぶ変わって落ち着いてきて、“えっ、こんなことができるんだ”“ここまでできるようになった。スゴイ!”と、子どもたちの能力やその伸びに気づくこともよくあります。そういった見方で子どもたちに接していくと、どの子も伸びるという確信がもてます。 園の職員たちもそう受けとめているはずです」
学力がつく以上に大切なこと。それは…
“どの子も伸びる”という職員の方たちの想いは、公文式での学習支援でも活かされているといいます。窓愛園の学習支援全般をとりしきり、公文学習の責任者でもある永野佳緒里先生にその手応えをうかがってみました。
 永野佳緒里先生 |
「公文学習の担当をして3年になります。公文で子どもたちの学力が高まったことはもちろんですが、それ以上によかったのは、子どもたちが少しずつですが自信をもちはじめ、“もうちょっと進めると思う”“もっと先をやってみたい”などチャレンジ精神がついてきたことですね。これは、学力がつくという以上に大切なことだと感じています。また、自分の成長や現時点での力量も自覚できているように思います。“早くスラスラ解けているから先の教材へ行こうと思うんだけど大丈夫かな?”と声をかけると、“うん、前よりかなり速くできるようになったから、先へ行きたい”“ここの問題は時間がかかったからもう1回やりたい”といったように、いまの自分がどういう状態なのかを考えて答えられるようにもなってきました」
「そのためでしょうか、ここ半年くらいで特に男の子たちがガラッと変わってきました。「明日はこの教材に進むよ」と言っても、以前は「ふーん…」と興味なさそうだった表情だったのが、“どこ?どこ?これやるんだ!ちょっとむずかしそうだけど、やってみる!”と、つぎの教材にとても興味を示すようになりました。先の教材を見せると“ボク、ここできるよ!”と言ったりすることも多くなりました」
「うちの園の職員は“伸ばすぞ!”という気持ちも団結力も強いので、公文の学習の大きな支えになっていると思います。職員全員が“その子にちょうどの教材はどこか?”ということを、いつも頭のどこかに置いてくれているので、ほんとうに助かっています。まさに、職員全員で子どもたちの伸びをサポートしているような気がします。そして不思議だと思うのは、公文の学習が子どもたちに定着してくるにしたがい、学習時間中はもとより、園の日常生活のなかで騒いだり崩れたりする子が少なくなってきたことですね」
「私自身も変わってきたと思います。以前は、その子の問題や課題に目が行きがちだったのが、その子の良い面を見られるようになり、たとえ問題や課題であっても、こうすればいいんじゃないかと前向きに見られるようになってきていると思います。公文の学習を通して、子どもの見方が成長したのかな…と、最近それをすごく感じています。そんな積み重ねができてくると、“そっか!こうすれば、子どもたちの伸びを後押しできるんだ”と思うことが多くなり、最近は自分の仕事に手応えを感じられるようになりましたね」
日々学習を続けることで、どの子も学年に追いつくことができる
ふたたび、上方園長先生です。
「日本の学校教育制度はよくできていますが、現実には学校の授業についていけなくても進級していき、学年相応の学力がついていない子も少なくありません。そんな子をどこでキャッチアップ(「追いつく」「遅れをとりもどす」の意)するのかが課題だと思っています。反対に、とてもよくできる子にとっては、授業がもの足りないということもあるでしょう。欧米の公立学校では、日本でいう義務教育段階でも留年や飛び級といった制度があるそうなので、長期的な視点で子どもたちを伸ばすということを考えたとき、学校教育制度を見直す転換期に入っているようにも思います」
「国内の児童養護施設はどこもほぼ同じ状況だと思いますが、入所する子の6割ほどが被虐待を体験し、メンタル的に課題のある子もめずらしくありません。また、それとの重複もありますが、子どもたちの3割くらいにはなんらかの障害があると診断されて入所してきます。障害の種類も知的なもの発達系のものさまざまで、そのレベルも千差万別です。けれど、園の子どもたちが公文の教材に向かっている姿を見ていると、この子たちには障害があるのだろうかと疑問に感じてしまいます。事実、うちの園では、スタートする教材内容は一人ひとり違うのですが、1年2年と学習を続けていくと、障害の有無にかかわらず、結果としてみな学年相当の内容まで進んでいます」
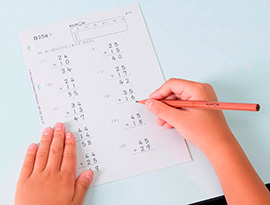 |
「児童相談所などから提供された知能指数(IQ)はかなり低いけれど、できるところからスタートし、やさしいところをくり返しながら少しずつレベルアップしていくことで、2年3年という時間がかかることもありますが、ほとんどの子が学年に追いつきます。これはすごいことです。しかも、楽しみながらキャッチアップしていけていることが素晴らしいと思います。窓愛園でもIQが100以上の子は過去を含めても数えるほどです。しかし、ほとんどの子が学年に追いつき、学年以上の公文の教材をする子もいます。そういう事実を見ると、施設の子どもたちには、このやり方がとても合っているのだと思います」
上方園長先生の言葉を裏づけるデータがあります。現在、窓愛園で公文を学習している子たちは、幼児11人・小学生13人の24人です。驚くのは、その13人の小学生のうち、学年相当の教材に進んでいる子が12人。さらに、その12人のうち学年以上の教材学習者が9人。そして、9人中2人は2学年以上先の教材を学習しています。「“窓愛園の子どもたちはみんな勉強できますね”と評判になってくれたらうれしいです」という園長先生の言葉が現実となる日もそう遠くなさそうです。
ひとつのことができるようになることで、“できる”連鎖が生まれる
最後に、窓愛園の小学3年生の男の子の事例をご紹介しましょう。まず園長先生のお話から。
「一般的にはADHDと診断されると薬を処方されますが、薬だけに頼っていてよいのだろうかと思っています。たとえば、ADHDの子が暴れたりしたとき、それがADHDという障害に起因するものかどうかはよく考えたほうがよいと感じています。園の子どもたちを見ていて、私は原因の半分くらいは学習にあるのではないかと思っています。学校の授業がわかるようになると学校に行くのも楽しくなり、友だちづきあいもうまくできるようになります。反対に、授業がわからない子は辛いだろうなって思います。何を言われているのかわからないのでじっとしているしかない、当てられるかもしれないとドキドキしている。なにを聞かれているかわからないのに、当てられて、笑われて、一日面白くないから、園や家庭に帰って暴れてしまう…。勉強ができないストレスも大きいのではないかと思います」
そして永野先生です。
「病院でADHDと診断され、児童相談所の検査では知能指数がかなり低いスコアだった、当時小1の子がいます。入所してすぐ、棚の上によじのぼり、押し入れに入ったまま出てこない状態が続き、“この子はたいへんだな”“伸ばすのがむずかしいかな…”と思っていましたが、園の生活に慣れるにしたがい、少しずつ落ち着いてきました。公文もはじめのうちは拒否していましたが、できることをするので、だんだんと学習ができるようになってきましたね。ここ1年くらいは、園でも学校でも、その生活ぶりがだいぶ変わってきて、何より心が安定しているなと感じられる日が増えました。公文の教材でも、カタカナ・ひらがなは完璧に読み書きができるようになっています。ですから、いまは園長先生も私も“この子もっといけるんじゃないか”と思えるようになりました」
「この4月彼は小学3年生になり、本を読む楽しさを知ってから、図書館でよく本を借りてくるようになりました。盲導犬とか動物関係の本が好きで、教科書で出てきたらすごく一生懸命読んでいて、漢字が読めないところは“フリガナをふって”と言ってきます。はじめは絵本とか幼児向けの本ばかりだったのが、ここ1~2ヵ月は小学生用の『かいけつゾロリ』とか図鑑、『盲導犬クイールの一生』といった本を借りてきますし、理解できないところはすぐに聞きにきます。興味をもって知りたいと思ったことへは貪欲に人に聞いて知ろうとするようにもなりました。何週間か前、園のテレビで山岳救助隊の活動を紹介する番組をいっしょに観ていたら、質問攻めにあいました。そういうところは彼がいちばんかなと思うし、持ち前の好奇心や素直さが彼をどんどん成長させているのかなと思います。そして、それは私たちにとっての大きな喜びでもあります」
「ふり返ってみれば、彼の成長ぶりは素晴らしいです。入所したてのころは、たとえば公文の学習の時間は騒がずに教材に向かってくれるだけでいいと思っていましたが、いまはまったく自然にそれができています。たし算に入ってからは、指を使いながらもがんばって問題に向かっている。でも、しばらくすると、指を使わずにたし算をやっている。そんな場面を見ていると“少しずつ、だけどしっかりできるようになっている”“自力で解けるようになっている!”と感じます。それは小さなことだけど、そういう小さな伸びが大きな成長になることもわかりました。ですから、もう彼はぜんぜん大丈夫じゃないかと思います。いまは、“わかんない、わかんない”と言っていたときの彼をなつかしく思い出します。もっともっと伸びていってほしいですね」
関連リンク 社会福祉法人 窓愛園 社会的養護の現状について(平成28年4月)|厚生労働省
 |
子どもたちに学ぶ喜び、成長する喜びを 施設での公文式 児童福祉施設 児童福祉施設での学習支援は、創始者公文公(くもん とおる)自らの働きかけから始まりました。 詳細をみる |
























