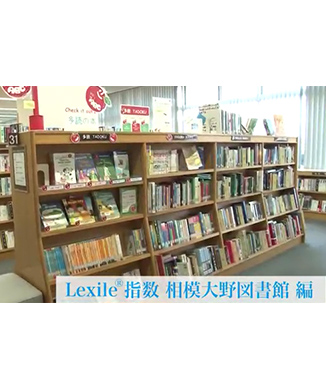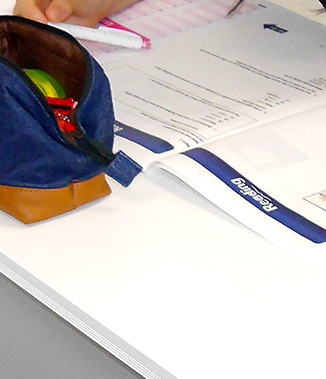お互いが学び合う「半学半教」の気風
–まず、御校の教育の特徴、育てたい人材像についてお聞かせください。
私どもの学校は、ご承知のように慶應義塾大学までの一貫教育を行っていますので、在学中に受験がありません。高校入試や大学入試といった受験のための学習から離れて、どの科目も基礎をまんべんなく身に付けること、そして学問の本質を探究するというところで、将来、実際に役に立つ合理的な思考ができる人間を育成することを目指しています。英語に関してもそういった観点で、ただ入試問題の点が取れればいいということではなく、四技能を総合的に学んでいこうという方針です。
慶應義塾にはお互いに切磋琢磨する「半学半教」という考え方があります。半分学んで半分教えるという言葉の通り、お互いに教わったり教えたりという学習共同体のようなクラスコミュニティを構築しています。先生からの学びだけではなく、生徒同士でお互いに学び合えるような教育を実践しています。
–英語科目における半学半教とはどのようなイメージなのでしょうか。
私の授業での一例を紹介しますと、テキストの巻末にある英文を暗唱して検定をするという取組みがあります。英語が得意な子、頑張って早々にマスターした子にはメンターの資格を与えます。まだ検定に合格していない子は、そのメンターの子のところに暗唱を発表しに行き、メンターは先生の代わりに時間を計りながら暗唱を聞いてあげて、合格だったら記録カードにスタンプを押してあげるのです。
人に頼んだり友達に聞いたりというのは放っておかれるとしづらいものですが、こうして生徒同士でお互いを補完し合えるような工夫を取り入れることで、教え合うことが当たり前になります。わからないことを人に聞くことは悪いことではない、自分だけがわかっていればいいのではなく、人に教えることは自分のためにもなるのだという学びの姿勢やメンタリティまで到達するのが理想だと思っています。
英語力で区切ることはしない
–御校の英語教育とはどのようなものなのでしょうか。英語科の教育の全般についてお話を伺えればと思います。
英語に限らず、授業は少ない人数で行った方が、生徒の話す時間やコミュニケーションも増えてきめ細やかな指導につながると思います。そういった少人数制のメリットをふまえて1年生は1クラス24人、2・3年生は通常の1クラス40人を分割して、それぞれに教員が入り授業を行っています。ティームティーチングやライティングの授業など、内容に応じて変則的になることもあります。
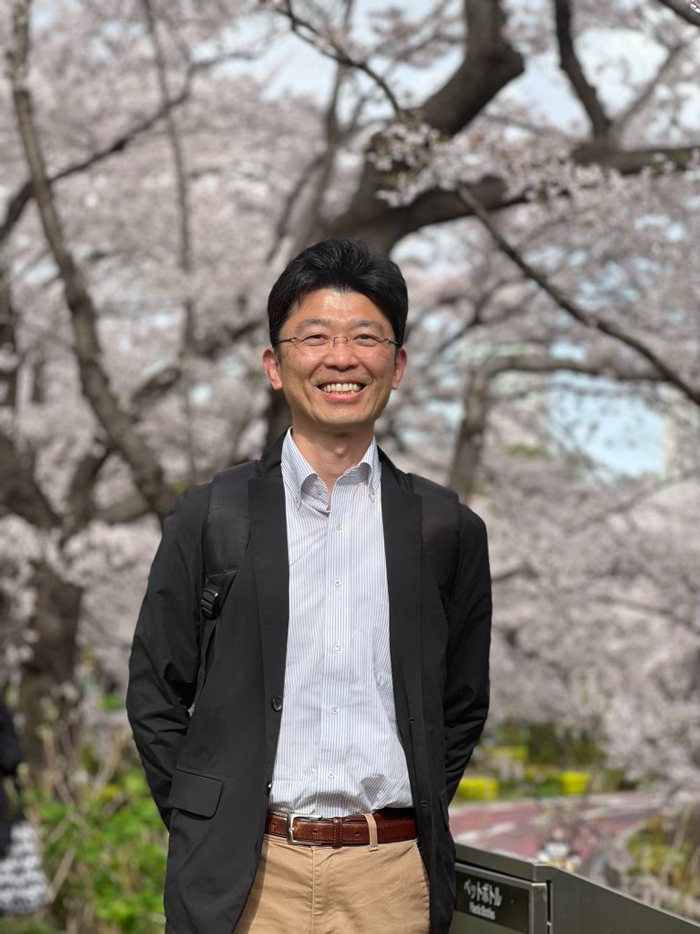 跡部 智 先生 |
また、インプットがないとアウトプットは増えないということで、英単語や英文法を覚えたりリーディングやリスニングで英語の情報を頭に入れたりといったインプットに注力しています。特にここ数年はコロナで会話やペアワークが制限された分、ライティングの指導に力を入れていますね。中学3年生の時点で、大学1年生でも通用する程度の基本的なライティングはカバーしています。ほかにも、いろいろな英語の文章に触れることで、読むことに対する抵抗を減らそうと、多読の取組みも行っています。
学校によっては、習熟度別のクラス編成をしているところもあると思います。もちろん幼稚舎で6年間英語教育を受けてきた子、帰国子女などもいますが、あえてレベル分けはしていません。先ほど述べた学習コミュニティというなかで、自分の得意な科目は人に教えてあげて、苦手なものは得意な人から教わるようなやり方から相乗効果が得られるのではないかという考えです。「あなたは下のクラス」といったようにラベルを付けることが、モチベーションにおいては逆効果であるという海外の研究結果もふまえたうえでの、学力で階層化はしない方針です。
TOEFL Primary®/TOEFL Junior®へ転換した理由
TOEFL Primary®/TOEFL Junior®を導入した理由
–これまで御校で活用されていた英検®から、なぜTOEFL Primary®/TOEFL Junior®に切り替えたのでしょうか。
これは運営上のことになりますが、英検®の場合、申し込みベースで費用負担が発生するなど、料金体系の面で学校として実施する場合に限界がでてきたという状況があり、代替テスト導入を検討していました。一方、TOEFL Primary®/TOEFL Junior®は事後請求で、受験者のみの費用負担でリーズナブルな料金体系です。試験の運営面でも、複数日程の授業中に科目を分けて実施が可能等、非常に融通が利きます。同じTOEFL Primary®/TOEFL Junior®を系列校である慶應中等部も導入していることも、切り替えに至った要因となりました。
また、TOEFL Primary®/TOEFL Junior®は、学習指導要領に沿った英検®や、学習範囲内の定着度を測定する定期テストとは目的が異なり、米国の等身大の学校生活や授業で普段使われている言葉や文法が試験内に使用される、試験範囲のないテストです。出題内容の異なる同じテストを受験しても尺度が同じであるため、いつ受験してもスコアの信頼性が高いことも選択肢にあがった理由のひとつです。最終的に、先ほども述べた生徒の発達段階に応じた内容、受験者の等身大の生活に即している点が導入の決め手となりました。
— TOEFL Primary®/TOEFL Junior®に期待するのはどんなところでしょうか。
単に合否ではなくスコアやレベルで比較できるので、これから回数を重ねることで自分の英語運用力の伸びを追っていけるところは期待しています。
また、本校の生徒には高校入試、大学入試がなく、世の中で言われている英語を勉強する一般的な動機付けがなくなってしまっている面もあります。そんな中で、将来留学したいという目標を持って英語を学ぶ生徒にとっては、こういった試験でスコアアップを目指すことはモチベーションとなるのではないかと考えています。
英語力の部分だけではなく、生徒の内面的な成長につながっているという実感もあります。大人が受けるTOEFL iBT®もそうですけども、4時間、5時間とコンピュータに向かって英語のテストを受けるというのは、かなりのハードワークです。英語力以外の忍耐力や体力も必要になってくると思います。そういう意味では、先に進むため・夢を叶えるために、越えなければならないハードルのひとつとして受けてほしいという思いもあります。
–将来、グローバルに活躍する人材となるための最低限の英語力というのはTOEFL®では測れるというふうにお感じになってらっしゃるということでよろしいでしょうか。
そうですね。加えて、グローバルな人材を育てていく以上は世界の方向性と乖離しないようにすべきであり、義務教育、公教育を担うという点においては、世の中のメインストリームに沿ったものである方が良いと思っています。
今回TOEFL Primary®/TOEFL Junior®を選んだ理由のひとつに、本校の英語指導が目指す方向性が大学につながる一貫教育校であることにあります。発達段階に応じたアカデミックな内容を目指しており、それはTOEFL®テストの出題の狙いと同じです。TOEFL Primary®/TOEFL Junior®は、リーディングの本文やリスニングの内容に触れること自体が異文化理解にもなります。こうした方向性の試験は世界のメインストリームであり、これは英語で受講し議論することを目指す生徒にとって、大学入試対策以上の英語学習の動機になると考えています。また、テスト結果は単に合否ではなくスコアやレベルで受験毎に比較ができますので、回数を重ねることで自分の英語運用力の伸びを追っていき、結果のフィードバックで弱点を克服していけるのではないかとも思っています。
この他考えられるTOEFL Primary®/TOEFL Junior®の具体的な効用は、リスニングが1回しか読まれないのでかなり集中して取り組まなければ得点につながらないことです。聞こえなかったからといって聞き返すことはできませんし、ディレクションもすべて英語であるという点で、たとえば実際の留学生活でのコミュニケーションに近いと考えられます。
即応的に対応できる力というのは、場数を踏んでいく中で獲得していくもの。こういう「慣れ」や「土台づくり」の観点からも、TOEFL Primary®/TOEFL Junior®を受験することは、長期的な目で見たときのメリットとなりうると考えています。大学生や社会人になったときに、試験を通じて培った力が発揮されるのではないかと期待できるからです。
—TOEFL Primary®/TOEFL Junior®を御校の英語教育の中でどのように活用されているのでしょうか。
まだTOEFL Primary®/TOEFL Junior®を実施し1年経っていませんので、これからの英語指導にどう生かしていくかは私たちも議論を重ねているところです。テストを通じて見えてきた生徒たちの英語運用能力や熟達度を、どういった形でふだんの授業に活用していくのがベストか、さまざまな可能性を探っていきたいと思っています。
今年度は2年生と3年生の生徒全員がTOEFL Primary® Step 2を受ける他、全生徒対象に年3回、学期に1回、生徒が受けたいタイミングで受験出来るよう希望者受験を実施する事が決まりました。また、希望者受験では、Step 1、Step 2、Juniorから生徒が選択出来る様に3タイプ選択制にします。今後は実際にテストを受けてみた子どもたちの反応や手ごたえについてもよくヒアリングして、より効果的で意義のあるものにしていきたいと思っています。
関連リンク TOEFL Primary® TOEFL Junior® 入試での活用もますます進展! Lexile®(レクサイル)指数とは? TOEFL Primary® TOEFL Junior® 問題集(くもん出版) TOEFL Primary®/TOEFL Junior®公式サイト 慶應義塾普通部