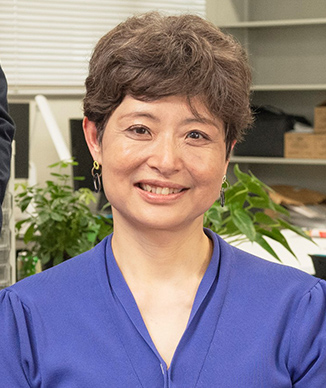吉田 和浩(よしだ かずひろ)
長野県生まれ。獨協大学外国語学部英語学科を卒業後、商社に就職。海外コンサルティング企業協会の研究員に転じ、英国のサセックス大学にて開発学修士を取得。その後世界銀行に入行し、アフリカ局人的資源エコノミストとしてアフリカ各国の教育プロジェクトを担当、人間開発ネットワーク副総裁室業務官、国際協力銀行開発セクター部社会開発班課長などを経て、2006年4月より広島大学教育開発国際協力研究センターに着任し、13年4月には同センター長に就任。SDGsの第4目標「教育」に関わる国際的調整組織であるSDG-Education 2030 Steering Committeeの共同議長を2020年までの2年間担当。
「見えない」化が進むコロナ禍は、SDGsとしての取り組みを見直すタイミング
 |
吉田和浩先生(以下、吉田):コロナ禍と呼ばれるようになって2年近く経ち、仕事の仕方も変わって移動や交流の機会がだいぶ失われていることがニューノーマルになりつつあります。生産性とか目に見える部分だけならそれもいいんじゃないかという雰囲気もありますが、より「見えない」化が進んでいる部分が少なからずあるとすれば、見直すべき部分もありますね。
これまでも感染症が流行するたびに学校が犠牲になってきました。学校再開をどう判断するか、いざ再開したけれど来ない人もいる、その都度の対応を情報としてストックした経験値はあるけれど役にたっていなく、同じ間違いやロス(教育上の損失)を繰り返しています。教訓になっていないんですね。
科学技術の進歩により、タブレットなどを活用すれば、学校が閉鎖している間も、個々の能力や個性を引き出すインタラクティブ(双方向・対話型)な授業ができるようになったでしょう。あるいは学校に行きたくなかった子どもたちが周りの目を気にしないで学習継続の機会が保証されたとか、うまくいったこともたくさんあります。その一方で、社会的弱者がより追いやられ、教育どころではなくなるなど、悪い部分が広がったとも見ることができるわけです。
社長室長 徳永(以下、徳永):我々もコロナ禍により、特に海外においては、現時点で教室に通えないという事例が多々あります。教育の機会が危機的状況にある今、いかに学習継続を図ることができるか、また今までSDGsとして取り組んできたことを見直すいいチャンスになればと思います。
吉田:この2年ほどのロスが3年後に回復することはまずなくて、悪い部分の影響はより長い間、もしかすると一生ついて回るかもしれません。オイルショックやプラザ合意、リーマンショックとか、経済や海外に起因するショックが起こるたび、対応しては数々失敗しています。
「何とか元に戻そう」という動きは今までいいことだけをしていた前提ですけど、実際はSDGsとして走り出した5年の間にうまくいかないことが数々あったところに、より重いものとしてコロナ禍がずっしり来ているのが現状です。
徳永:「元に戻すだけで本当にいいのか?」という言葉が非常にヒントになります。元に戻すだけではなく、分析して、自分たちの強みや弱さを知って次にどうするのか見極めないと教訓が活きてこないわけですね。
「グローバル エデュケーション モニタリング レポート」によると、2020年3月から2021年9月までに教育に対する影響を受けた子どもの数は約16億人とのことで衝撃を受けました。
吉田:ほぼ全員といって過言ではないでしょう。
学校教育が唯一の手段ではない。支援の選択肢はいろいろあってよい
 |
徳永:学校閉鎖を受けた子どもが1億人、読み書きできなくなった子どもが10%も増えています。先生が尽力しているEFA(エデュケーション フォー オール)から改善した部分もあったはずなのに、重層的に問題が重なって、保護者も子どもも苦しんでいるという状況です。この課題解決においてどのようなアプローチがあるとお考えですか?
吉田:コロナ禍対策の中心に「学校教育がすべて」という考えがあることがそもそもの問題だと思います。ひとつの価値観で社会を束ねるような教育がかつての特徴だったとすれば、恐らく、見たくないものは見ていなかったのでしょう。だから、いじめや不登校、ひきこもりの統計が取れなかったのだと思います。私たちの世代は、そこに息苦しさを感じた人が学生運動を起こしたり、やんちゃな振舞いをしましたが、社会は迷惑がりながらもそれなりに許容力があったと思います。でも今の時代、型にはまりきれない人たちは仕組みや制度の中に居場所がなくなってしまうんですね。いろんなところで問題が生じている事実を認識してくれないと、原因究明もできないし、次のステップに進む解決策も見つかりません。文科省が決めるのはカリキュラムと到達点であって、支援の選択肢はいろいろあっていいのではないかと思います。
徳永:KUMONもまさにそういう存在であればと思っています。
吉田:公文公さんが何十年も前におっしゃったメッセージは今も輝いています。国連憲章のように70数年前に作られたものも、全然さびついてないけど実現もしていないという部分もあります。社会が変われば解釈や実現の仕方も、変わっていくはずですよね。
徳永:時代は変化しているのに、教育や育て方は変わっていないことには私も非常に違和感があります。いろんな育て方があるというのは、先生のご示唆の通りですね。
自分で考えてチャレンジする姿勢はSDGsにおいて重要な要素
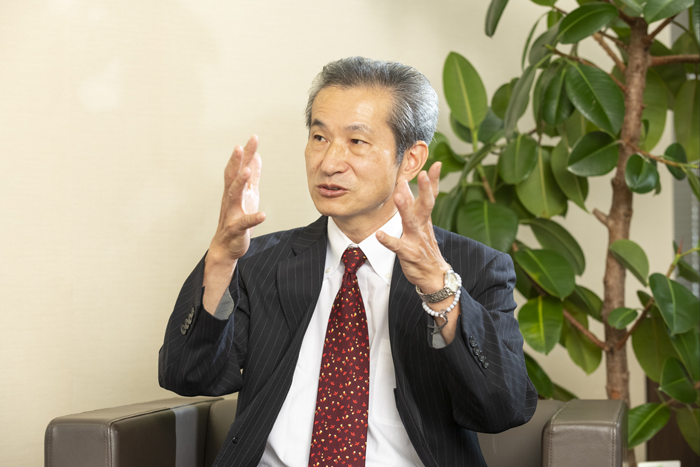 |
吉田:「子どもは村じゅうみんなで育てるもの」、他人事でなくみんなが関わるという考えは、有効な見方だと思います。学校を終えて社会に出て行けば、会社がまたイチから叩き直して教えてくれて、結局誰もが生涯学習をしてきたわけです。しかし、人間として凝り固まってくると「自分は正しい、自分さえよければいい」と、この考えから離れてしまいます。そこをもっと考えましょうというのがSDGsのメッセージでもあるんですね。
徳永:一企業が持っているリソースは限られていますし、社会の課題解決を行っていく仕組み作りの重要性を感じます。すぐに効果がでるものではないけど、まさしくそれがSDGs4.7(※)ですね。
(※すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識とスキルを獲得する)
公文式学習は、講師によるスクール形式の一斉授業ではありませんから、学習者は自分で100点にするまで考えていく必要があります。どんどん先へ進み、まだ習っていないことを学べることで達成感を得られる、失敗を臆することなく未知の内容にチャレンジする精神が培われるという認識をいただけるようになってきました。これはSDGsの論点では非常に大事な要素になるのではないかなと考えています。
吉田:間違いなくそうだと思います。SDGs4.7って、簡単にこれだという答えが見えるものではなくて、読み手によって解釈が異なるものだと思いますし、ナレッジとかスキルで止まるものではなくて、価値観やアティテュードといった、もっと実践に近いものなんです。さらに2030年が来たから終わるものでもないし、具体的にどういう行動を取るのか、皆が考えていくことが大事だし、ある程度の許容性があるものだと思います。
子どもが学んでいく上では皆が先生。分野や企業をまたいでの協力が不可欠
 |
吉田:SDGsの枠組みを作っていくプロセスやステアリングコミッティに参加していると、それぞれの委員が「先生の代表です」「NGOの代表です」というように、自分の選挙区のようなものを背負っているんです。
でもティーチャーが教科を教える役割しかしていないわけではないし、子どもが学んでいく上では、みんなティーチャーだし、エデュケーターなんです。教育が公共財だからと言って民間企業が入ってきたらいけないわけではないし、民間なくして政府が成り立っているわけでもありません。後ろに背負っている選挙区の利益のようなものを下ろさなければ、本当の議論になっていかない気がします。
徳永:教育においてはいろんな人とのコラボレーションや協力関係が欠かせないと思います。コロナが広まり始めた当初に、このような状況になることを想定していた人はいなかったと思います。でも人間が知っていること、解決できることは限られているから、公共も私企業もいろんな分野や産業の人が協力していかないと難しい、一筋縄ではいかないと思います。その一方、すでに実績が表れている部分もありますから、この流れは止めたくないですし、またアドバイスをいただきたいです。
吉田:失敗を重ねていくといろんなことが見えてくると思います。SDGsに限らず、教育の問題を教育の中だけで見るのは難しいですね。教育が相手にしているのは人間ですし、人間を組織の縦割りのようには捉えられません。人が育っていく過程では、経済も健康も教育も環境も全てが重なり合っていて、お互い影響を与えながら生きています。
子どもを見ていれば、分野や企業をまたいでの協力が不可欠なことは明らかですし、点と点で存在していたものが、密接すぎるくらい重なって繋がっていることが知れば知るほど増えていくはずなんです。これを機会に、より共同事例が具体例として増えていけば理想的ですね。
徳永:そうですね、人間は実社会で育っていますから、ひとつの刺激だけでは成立しません。私たちもいろんな刺激を与えられるような、人の成長に関われる企業でありたいと思っています。
関連リンク 広島大学 教育開発国際協力研究センター 広島大学 教育開発国際協力研究センター長 吉田和浩先生|KUMON now!スペシャルインタビュー