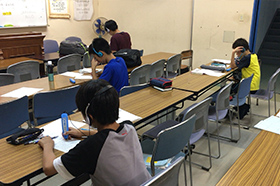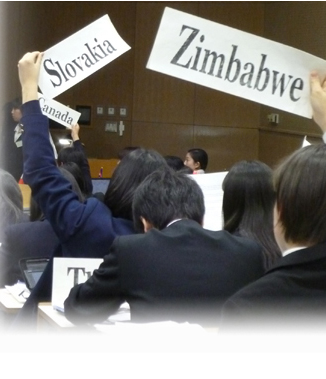中学1年生は小学校での「差」を埋める大事な時期
子どもたちそれぞれに合わせてのスタートが「救済」に
 久住校長 |
まず初めに、公文式を導入した経緯と現在の目的、実際に導入してみての子どもたちの様子について、久住祐嗣郎校長先生、進路指導部長の石橋義人先生、今年度から公文式学習の指導責任者を務める大石怜先生にうかがいました。
―― 現在は1年生全員に「英語」が導入されていますが、どのようなことが狙いとなっているのでしょうか?
久住校長: 本校は宣教師が設立した学校で、現在では海外に系列校が小学校、中学校、高校、大学あわせて約6000校あります。そのために日本の三育高校を卒業後、欧米の系列大学に進学する生徒が毎年1割ほどいます。それもあって、もともと英語教育には力を入れてきました。その中で、系列の各小学校で行われている英語教育にはやはり差がありますので、それを埋めることを目的として公文式学習を導入しました。公文式ではそれぞれ子どもたちがどこまでできていて、どこでつまずいているのか、それに合わせてスタートすることができるという点に良さを感じています。
―― 公文式学習の印象はどのように感じられていますでしょうか?
久住校長: 私が公文式学習の担当を務めた際、公文の方から言われたのは「大きな丸をつけてください」ということでした。ですので、公文と言えば「大きな丸」というのが最初の印象で、そのほかにも子どもたちにやる気を起こさせるための工夫が凝らされているなと感じました。
石橋先生: 私は自分自身が合理的に勉強するタイプで、実は最初は公文式学習に対しては「まどろっこしいな」という印象がありました。でも、実際に自分自身が公文の担当をすることなりまして、学期ごとに目標枚数を掲げたり、子どもたちの頑張りに応じて「頑張り賞」を与えるなど工夫してみたところ、子どもたちが意欲的に取り組むようになったんですね。今ではとてもいい学習方法だと思っています。
それぞれの「つまづき」を見過ごさない
「やる気のスイッチ」の後押しに
 石橋先生 |
―― 実際に導入しているうえでの手ごたえをお聞かせください。
久住校長: 全寮制の本校では、金曜日と土曜日以外の週5日は、放課後の活動を終えて夕食後、夜7時15分~9時の時間帯は寮での学習時間となっています。それを継続することで「学習習慣」を身につけさせることが狙いなわけですが、その中で週に3回30分ずつ行っている公文式学習が果たす役割というのは大きいと感じています。
―― 具体的に公文式学習が果たす役割について、どう感じられていますか?
石橋先生: まずは先述したように、個人差を埋めることができるという点が挙げられると思います。また、1年生全員に義務化することで、最初は苦痛に感じる子もいるかもしれませんが、継続することによって「自学自習」の力が身に付くことは、これまでの子どもたちの様子から感じています。 大石先生 |
大石先生: 担当になってまだ数か月なので、まだ把握できていない部分も多いですが、それでも公文式学習の様子を見ていると、その日の担当の先生が各生徒に対して1対1でコミュニケーションをとりながら対応しているので、教員と生徒との密な関係ができていいなぁと感じています。
―― 公文式の学習効果を感じられたエピソードはありますか?
石橋先生: これは1年生ではないのですが、英語が苦手な中学3年生の生徒がいまして、どうしようかと考えた際、公文式学習を提案したことがありました。実際、公文式学習をやり始めると、少しずつ英語を理解するようになりまして、テストで2学期には80点以上をとれるようになりました。もともとその子にあった「できるようになりたい」という気持ちが、公文式学習によって育まれ、また何が自分はできて、何ができないかが明確にわかったということが大きかったのだと思います。
久住校長: 子どもたちはみんな「できるようになりたい」という気持ちはあると思うんですね。そのやる気のスイッチが入った時に、「じゃあ、これをやってみようか」というその子にちょうど合った教材を渡せるという意味合いは非常に大きいと感じています。
―― 今後も公文式学習を続けていこうと考えられている一番の理由は何でしょうか?
久住校長: 学習というのは継続していく中での積み重ねが重要だと思います。ですから、どこかでつまずいてしまった子どもたちに対しては、彼らを救出する手段が必要なわけです。それを授業のワークでそのまま進もうとしてもなかなか難しい。でも公文式では、自分ができるところまで戻って、つまずいたところを乗り越えることが可能です。子どもたちのつまずきを見過ごさないためにも、今後も公文式学習を続けていこうと考えています。
「勉強って楽しいんだ!」に気付けた公文式
理解してから次に進むから「わかる」「できる」
 左からAさん、Kさん、Sくん |
次に、生徒の皆さんに中学校に入学してから約3か月間、公文式を学習してみての感想をうかがいました。
―― 公文式学習をやってみて、いかがですか?
Aさん(取材時は高校1年生相当の公文式英語JⅠ教材を学習中): 私は小学校の授業でも公文式英語が取り入れられていたので、小学1年生から学習をしています。公文のいいところは、単語や発音を覚える力がついて、英検を受けるにもとても大きな助けになっているなと思います。昨年、小学6年生で英検3級に合格したので、次は準2級に挑戦したいと思っています。
Kさん(取材時は中学1年生相当の公文式英語GⅠ教材を学習中): 私は中学校に入って初めて公文式をやったのですが、公文のプリントはいきなり難しい問題ではなく、少しずつ難しくなっていって、1枚ごとにレベルが上がっていくので、それがとてもいいなと思います。
Sくん(取材時は中学2年生相当の公文式英語HⅠ教材を学習中): 僕は中学校入学に向けて、小学5年生から公文式をやっています。僕は「E-Pencil(イー・ペンシル)」で学ぶのがいいなと思っています。「E-Pencil」で英語を聴いていると、わからない単語もあるけれど、場面が思い浮かぶような感じで音楽や会話が進むので、楽しく取り組めています。
―― ほかの教材とは違う、公文式ならではの特徴を教えてください。
Aさん: ふだんの授業での教科書は、みんなで同じところをやるけれど、公文式では自分自身に合ったところから始めることができて、理解してから次に進めるので楽しいです。それに頑張ればちょっと上のレベルにも挑戦できるので、そういうところが良いなと思います。
Kさん: 公文式のプリントは、一人ですいすい進めることができるので嬉しいです。私はすぐに飽きてしまう性格で、小学生の時は勉強もあまり好きではありませんでした。でも、公文は楽しく進められるので、「あ、勉強って楽しいんだな。もっと勉強したいな」って思えるようになりました。
Sくん: 僕も自分に合ったレベルから始められるところと、やっぱり「E-Pencil」で英語を聴くことができるというところがほかの教材とは違うなと感じています。
「やらなければ」から「自分のためにやろう」へ
やる気アップで膨らむ将来の夢
 女子寮での学習の様子 |
―― 公文式学習を始めてから、自分自身に変化を感じていることはありますか?
Sくん: 苦手だった「be動詞」「一般動詞」が理解できるようになって、ちゃんと言えたり書けたりできるようになりました。
Kさん: 授業で「Do」を習った時、最初どういうふうに使うのかよくわからなかったのですが、公文式でそこまで追いついたら自然とわかるようになりました。公文式のプリントには「Do」を使った例文がたくさん書かれてあって、すごく理解しやすかったです。
Aさん: 自主的に勉強するようになったと思います。正直、始めたばかりの小学1、2年生の頃は嫌で仕方なかったんです。宿題も泣きながらやっていた記憶があります。でも、4年生くらいの頃から楽しいなと感じるようになってきて、最初は「やらなければいけない」だったのが、今は「自分のためになるからやろう」と思えるようになりました。
 |
―― これからの目標を教えてください。
Sくん: まだ「5W1H」の使い方が覚えられていないので、それをできるようにしたいです。あとは単語ももっと覚えたいです。
Aさん: これから受験のことも考えると、英検は大事だと思うので、それに向けて公文を頑張りたいのと、将来海外旅行に行った時に人に頼らずに自分で英語で会話できるようにしたいなと思っています。
Kさん: 2年後の2020年東京オリンピックの時には、家族で観に行こうと言っているので、その時に海外から来た人たちに道を聞かれたりしたら、英語で答えてあげられたらいいなと思っています。あとは将来的にはキャビンアテンダントや通訳など、英語を使った仕事に就きたいと思っているので、頑張りたいです。