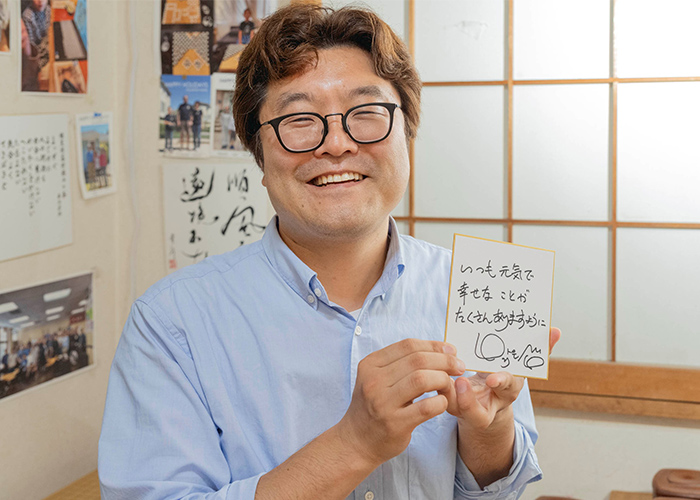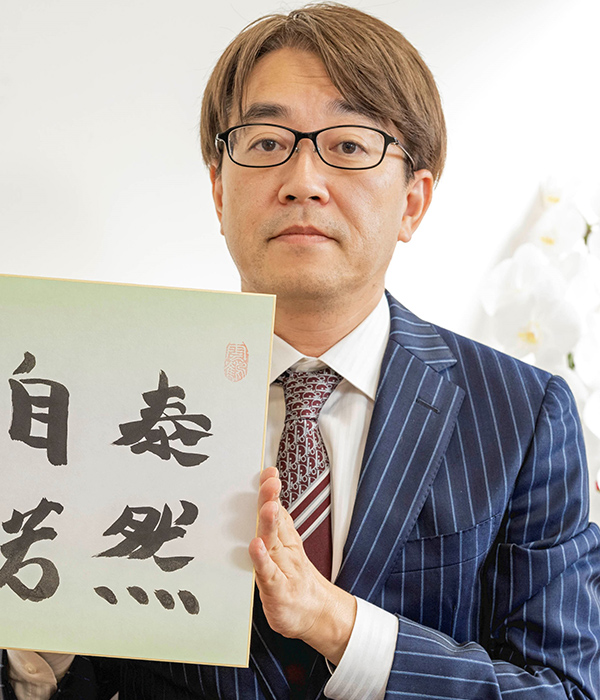合宿や山登り、映画鑑賞も
「生きる力」を養う道場

洪道場は囲碁の世界で「日本一になる」「世界一になる」ことを目指すと同時に、囲碁を通じて人として成長してもらいたいと考えて、道場以外での活動も取り入れています。
2006年からは毎年、年3回ほど合宿を実施。子どもが親元を離れて成長するきっかけになっています。例えば、時間の大切さもわかるようになります。「寝なさい」といっても子どもは寝ませんが、「朝は7時半に起きないと何かが起こるよ」と言えばちゃんと起きます。「何か」とは私の説教なのですが(笑)。
合宿では囲碁の勉強の時間だけでなく、自由に過ごせる時間もつくっています。メリハリをつけてストレスがなければ、子どもたちはケガもしませんし、遊びを十分した後は、子どもたちは集中力を発揮しますよ。
楽しい思い出ができればいいなと思っているので、合宿以外にもいろんな活動をしています。山登りや海にも行きますし、異文化体験として子どもたちと韓国に行くこともあります。そして東日本大震災後は、洪道場のある杉並区から40㎞先の横浜などまで歩く体験をイベントとして実施しています。災害に遭遇しても生き延びて欲しいので、自分の体力を知る機会になればと思っています。大事なのは、「行ってこい」ではなく、私も一緒に行くこと。道場では掃除も私と一緒にします。

また洪道場ではときどき朝礼を行います。マナーについての寸劇をしたり、「対局への心構え」を皆で読み上げたりします。「一番怖い敵は自分自身であることを知ること」「正しい礼節が勝運を呼び込むこと」など18の心構えがあります。私は読書が好きなので、著名人の書籍を参考にしたりもします。
実はこれらの項目は、私自身に不足していて「失敗した」と思っていること。しかしその失敗を生かして、子どもたちに大切なことを伝えることができているので、失敗することは悪いことばかりではありません。むしろ失敗は成長であり、失敗を積み重ねた先に未来が開けると考えているので、子どもたちには囲碁でも臆せずにどんどん打ちなさいと伝えています。
究極のことを言えば、囲碁は生きるために必要なものではありません。しかし挨拶をしっかりすることや、自分自身の頭でよく考え、判断し、決断することなど、囲碁を通して「社会で生きていく際に役立つこと」が身につけられるのではないかと思っています。
そんなふうに子どもと一緒に時間を過ごしていると、子どもの手(着手)や字の書き方を見ただけで、悩みがある子どもはすぐわかります。そんなときはその子を呼んで、食事やお茶をしながら話を聞くこともあるんですよ。
子どもたちには、仲間でも技術でも何でもいいのですが、洪道場で得たことを生かして、自分の人生を歩んでもらえればと願っています。
自主性や積極性は
「伸びる子」の共通点

プロになれる子の共通点は3つあります。ひとつ目は「努力する才能」がある子。自分の意思で碁盤の前に座る積極性があり、夢がしっかりある子です。ふたつ目は、親が応援してくれる子です。両親の方向性が同じで気持ちよく応援してくれること。そして最後は、囲碁を学ぶ環境がある子です。
学ぶ環境という意味では、最近はAIの登場で囲碁を勉強する環境はよくなりました。しかし、それを使いこなせるかどうかが肝心です。また、一人で頑張るのはやはり難しいので、一緒に歩んでくれる仲間がいることも大事です。そのほか、伸びる子は、自主性や積極性がある、あいさつがしっかりできる、指示待ちではなく応用ができるという傾向があります。
洪道場を立ち上げてからの20年間でいろいろな子どもたちと出会いました。中でも印象に残っているのは、中学生で囲碁を始めた、ある男の子です。プロを目指すのは小さい頃から始めたほうがいいので、多くの道場では中学生の初心者は断るのですが、洪道場ではやる気のある子は受け入れています。彼もそんな一人でした。でもやはり、小さい頃から始めた子と比べるとなかなか厳しい。すると高校生になった彼は、「学校をやめて囲碁に集中する」と言うんです。私は彼の人生に責任を取れないと、よく考えるよう言いましたが、彼は「親も説得した」と引かずに高校を退学しました。そして道場に始発で来て、夕方6時までずっと囲碁の勉強をする生活を、1日も休まずに1年半続け、ついに、日本棋院でプロ棋士を目指す院生のトップになりました。
ただ、プロ試験には通らず、彼はその瞬間、囲碁をやめると決断しました。私はあと1~2年やったらプロになれるのでは? と伝えたのですが、本当にすぱっとやめてしまったのです。その決断はすごいと思いました。

彼はその後、大検を経て難関大学に合格。大学卒業後は外資系企業に勤務していたのですが、好きな日本酒の蔵元の社長に入社希望の手紙を送って、現在はそこで働いています。彼の積極的な行動は本当にすばらしく、私が誇りに思う生徒の一人です。
彼は洪道場にも時々遊びに来てくれます。私は「プロ棋士になれなかったのは自分の教え方が不十分だったのでは」と反省の思いを彼へ伝えたことがあります。すると、「囲碁を長時間座って勉強する経験を通して、仕事も苦にならないようにしてくれました」と返してくれました。この一言はありがたかったですね。
10年後には都内全小学校で
囲碁と触れ合う機会を

洪道場の開設当時に掲げていた「日本一になる」「世界一になる」というミッションは、道場出身者が主要な日本タイトルをすべて獲得し、クリアしました。でも初心を忘れずに、これからも自分の夢を目指す子どもたちを応援したいと思っています。そのため最近は、道場の指導者(師範)の会議を充実させ、道場生一人ひとりの状況を共有しています。
さらにこれからは、プロ棋士が囲碁のスキルを生かして活躍できる場を広げていきたいと思っています。囲碁はオセロと混同されるなど、認知がまだまだ不十分です。日本の囲碁人口は、1980年代には1,200万人でしたが、今は100万人もいないかもしれません。囲碁のイメージを変え、囲碁人口を増やしていきたいと思い、2023年には、GOMARUという株式会社をつくりました。そこでは私の教え子の棋士の名前をつけた選手権を、その棋士の出身地で催したりしています。
一方、自治体と一緒に活動を広げていくには非営利法人の方が推進しやすいため、NPO法人洪道場囲碁普及会も立ち上げました。現在都内9か所の小学校で囲碁を教えていますが、これを都内の全公立小学校に広げるのが目標です。10年くらいかかるかもしれませんが、ものごとをコツコツ進めるのには自信があります。周囲の方々と協力しながら、これまでの20年間同様、これからの20年もコツコツ取組んでいきたいと思っています。
20年後、私が63歳になった時には囲碁人口が300万人になっていて、教え子たちもいい活動ができている ――そんな夢を描いています。

子どもたちに伝えたいことは――自分の夢を考えてみてほしいですね。今の自分が一番好きなものは何か。長所は何かを考えてみてください。どんなものでもOKです。そしてそれを、保護者は否定しないでほしいと思います。
一番怖いのは、「こんなこともできないの?」「どうせ無理でしょう」という言葉。こんな言葉を言われたらやる気をなくしてしまいます。私もそんな言葉がのど元まで出かかったり、答えを言ってしまいたくなったりすることがありますが、我慢して「もう少し考えてごらん」と言います。そうして自分で考えられるようになった子が、「生きていける力」を得ることができるのでしょう。
くもんの先生に伝えたいことは――すでにされていると思いますが、「愛をもって教える」ことでしょうか。わが子だと思って大事に接すれば、叱ることもほめることもできますよね。ぜひ、夢を実現しようとする子どもたちを、一緒に育てていきましょう。
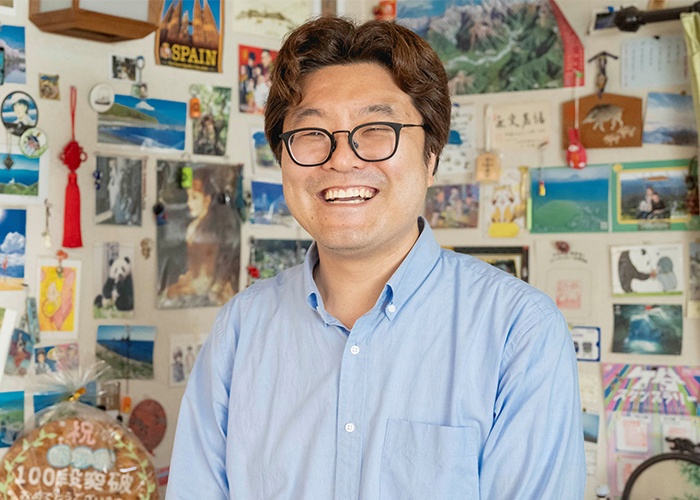 |
前編のインタビューから -盤上に広がる無限のドラマ 「1日を大切に」が囲碁の本質 |