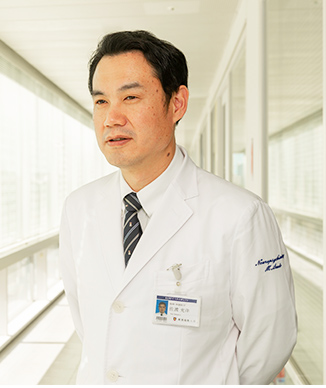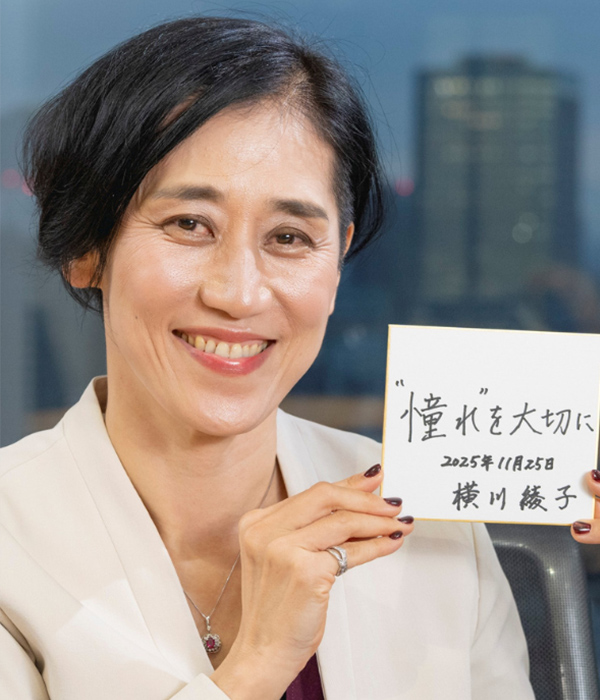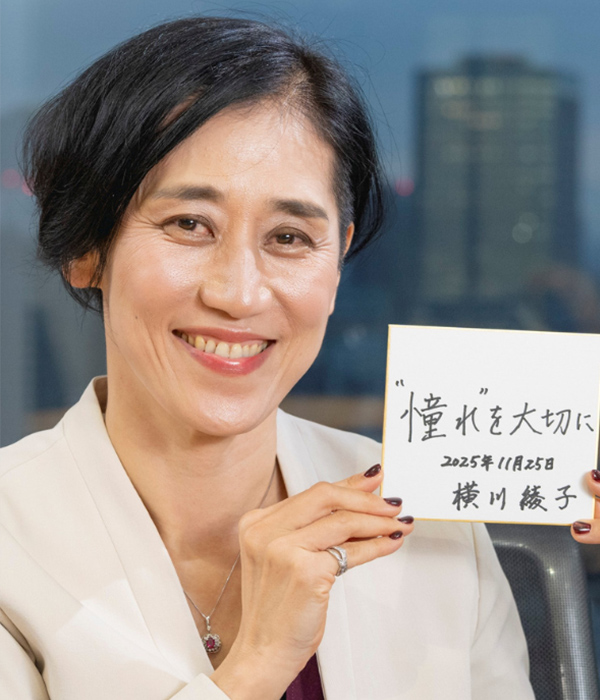自分の興味を探索するため、他大学のさまざまな講義を聴講
 |
私は生まれは新宿ですが、体が弱かったこともあり、3歳の時に環境のよい北海道に引っ越しました。父は管理会計の研究者でありながら、いくつか事業も営んでいました。ぼくはチェロや絵を習ったりスキーをしたりと、子ども時代はいろんなことをしていました。ちょっと変わっていたのは、家庭内のDVもあったためか「あの世」に興味があり、お墓の絵ばかり描いていたことです。心の縁(よすが)を求める不安定な人間だったのだと思い返します。
中学生になると、文章で表現することが好きになり、詩を書くようになりました。当時は精神科医になりたいと考え、大学は医学部を受験しましたが、失敗。浪人のときに文転し、中央大学商学部に進みました。公認会計士サークルに所属しながら絵本作家の個展の絵に展示会ごとに詩をつけて絵本を出版したり、他大学の友人と雑誌をつくったりと、20代前半はクリエイティブワークに励んでいました。
商学部では最初は環境監査などを学びましたが、社会問題に関心があり、会計学よりも「変わったことをする人」と、「それをどう組織化するか」という経営組織論に興味が移りました。じつは大学時代は、他学部の授業のほか、哲学や仏教、言語学など、他大学で行われているさまざまな授業を聴きに行っていたのです。どの学問であれば社会の問題解決ができるか、何が一番おもしろいか、「人間のための学問とはなにか」を探していたのですね。
卒業後は、恩師に大学院に行くことを勧められ、北海道大学大学院に進学しました。北大に決めたのは、現在青森大学学長の金井一賴(かずより)先生の授業を受けたかったからです。さまざまな論文や書籍を読むなかで、「この先生の授業は面白そうだ」と感じたのが決め手でした。金井先生のほかにもさまざまな先生に導かれて、いまがあると思っています。その意味では先生と縁をもつのはとても大事。教師の仕事は「知的な誘惑」だといえるのではないでしょうか。
大学院を卒業後はコンサルティングファームに就職するつもりでしたが、幸いにも日本学術振興会(JSPS)の特別研究員に採用され、研究者の道を歩むことになりました。
学問は、肯定的な感情やエネルギーが生まれうるための基盤
じつは、父は事業に失敗したりして、私が10代のころから自宅には弁護士や経営者などいろいろな人の出入りがあり、学生ながら自分も対応して、日米でいわゆる修羅場も経験しました。そんな経験もあるので、経営者と間近にやりとりするようになった今、重要な案件にも萎縮せずに学問の立場からはっきり発言ができるのだと思います。
その意味では父の影響は大きいといえますが、そんな事情もあり、母も姉も大変だったと思います。ただ、“修行”の機会というのは、いろいろな形で現われると思うのです。そうなったとき大事なのは、起きたことに対する反応です。表面はオバケに見えたり天使に見えたりしますが、何にせよ、「そこにいかに向き合うか」が人生の本質だと思います。形がネガティブであればあるほど、しっかり向き合うべきでしょう。
 |
加えて、私の場合、助けられたのが「学問」でした。さまざまな大学に行ったり言語表現をしたりと、学問を通して得られた潜在的な素養が、私の生きる方向性となり、人間社会に切実な「知的誠実さ」を培うことを探求する、いまの私があると思っています。決して簡単なことではありませんが。
学問は、国や地域を越えた共通言語であり、「人類の知恵の蓄積」です。さまざまな危機を乗り越え、古代から伝わってきているもの。本来、継続すべき人類の一番の「富」です。そして、「死を思うこと(=メメント・モリ)」は、むなしいことではなく、「生きていること」、「以前に生きてきた人」、あるいは「これから生まれてくる人たち」をつないで重ねて理解し、感謝など肯定的な感情やエネルギーが生まれうるための基盤といえるのではないでしょうか。
実際私がそうであったように、一見すると悲劇的にみえるイベントでさえもギフトと捉え、次に託す、託そうとする。これは人類的なミッションであり、そういうスケールで学問を捉え、語ることが重要です。狭い意味での富、つまり、経済的な価値の仕組みのために学問があるのでは決してないのです。
「学問」が骨格となって支えているのが「学び」です。「学び」がなぜうれしいかというと、先人たちの知恵が自分に伝わってそれが活き、かつ次世代に伝えられる。その可能性を身体的に感じることができるからなのです。
“手軽に見えることを鵜呑みにしない体の感覚”を大切に
 |
私には息子と娘がいます。親と子という役柄はありますが、小さいころから同じ目線で、対等に話しています。群れとして一緒に生きているものとして、支え合ったり学び合ったり分かち合ったりしています。いま考えていることやお金のことも含めすべてオープンに話しています。親子の関係は一瞬ですが、長い人生ストーリーにおいて、深く影響し合うもの。縁があったことを感謝し、子どもたちには「うちに来てくれてありがとう」と思っています。
いまの若者や子どもの振る舞いを否定的に捉える人もいますが、それは私たち大人がそういうような振る舞い方をしていることの正確な写し鏡でしょう。また、大人も含め、金銭的に数えられるものを超える理想や崇高なもの、何が大事なのか、といったことを話す機会が減ってきているのが心配です。そういうことをしらけずに話し合える信頼関係や場を築くことが大切だと思います。
もうひとつ、日々において大切だと思うのは、「手軽に見えることを鵜呑みにしない体の感覚をもつ」こと。たとえば朝起きて、自分の肉体と意識が立ち上がるときに出てくる、「今日はこうしよう、こうしたい」という本能的な感覚や言葉に耳を澄ますのです。
起きてすぐスマートフォンを起動し、画面に反応する“反射ゲーム”をしてしまうのは、そのシステムの家畜として自分をおとしめていると思います。“設計されているもの”とつながないと、“自分が生きること”の編集ができない。そんな習慣だけになってしまったら、“生きもの”として危険ではないでしょうか。
人がより良く生きるために、社会や会社が設計されることが重要なのです。システムが維持されるために人間が歯車の一部として回っている状態や「語り口」はいびつです。とはいえ、日々働くにあたり、そうしたシステムがないと進めないのも事実。システムは道具だということを見誤らないようにすべきでしょう。
そんないびつさを改善できるような方策を、研究、あるいは学生や企業との対話を通して探求し、次の時代を背負う子どもたちに「申し訳ない」と言わざるを得ない教育・研究環境にならないようにしたいですね。そして、「言葉」や「知の価値」が限りなく軽くなってしまっている学びの現場がまっとうになるよう――これはけっこうタフなミッションですが、一大学教員として精一杯できることを毎日努めていきたいと思っています。
 | 前編のインタビューから -アントレプレナーシップとは? |
おすすめ記事
-

学習経験者インタビュー
Vol.093
弁護士・ニューヨーク州弁護士
松本慶さん少しずつでも前進すれば大丈夫 「一日一歩」の精神で歩いていこう
-

KUMONグループの活動
Vol.510
公文式英語で世界とつながる経験をきっかけに
将来を一つひとつ切り開くことができた 間違いをおそれずに挑戦しよう
-

学習経験者インタビュー
Vol.087
ピアニスト
中川優芽花さん「まずは行動して、失敗して、学ぶ」 プロセスは 音楽にも勉強にも大切なもの 失敗しても、すべての経験は力になる
-

スペシャルインタビュー
Vol.073
特別対談 棋士 藤井 聡太さん
終わりのない将棋の極みへ 可能性のある限り 一歩ずつ上を目指していきたい
Rankingアクセスランキング
- 24時間
- 月間
© 2001 Kumon Institute of Education Co., Ltd. All Rights Reserved.