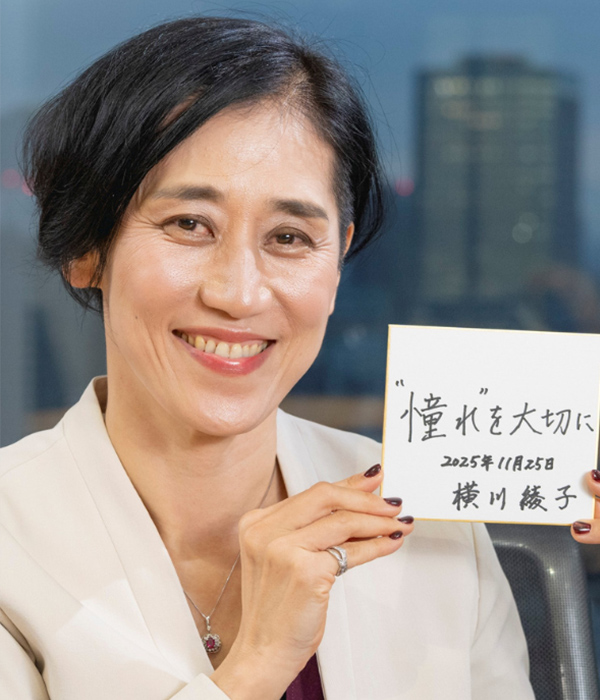舞台を通して見える、今の時代の子どもたち
大人がすべきことがわかってくる
 |
もう40年近く各地で公演を続けていますが、いつの時代も観客である子どもたちの反応が、わたしたちを奮い立たせてくれます。忘れられないのは、37年前、アンデルセン作の「にんぎょ姫」を上演したときのエピソードです。
魔女から人間の足をもらったにんぎょ姫は、王子様が他の女性と結婚したら海の泡となって消えてしまう、と魔女から告げられていました。それを承知で王子様のおそばにいたのですが、王子様は隣国のお姫様と結婚することに。“このナイフで王子様を殺せばあなたは生きられる”と、手渡されたナイフを手に、にんぎょ姫は悩みます。そのシーンで、観客の小さい女の子が「殺して!」と声を上げ、いつのまにか「殺せ!」の大合唱になっていたのです。もう、驚きましたね。「愛とは見返りのない行為」というのがこのお芝居のテーマなのに、子どもたちがこんなことを言うなんて、大人のわたしたちの責任ではないか、と。
もっとも今の時代の子どもたちは、自分の気持ちを抑えてしまうようで、「殺せ!」とも言わないのね。逆にそうした沈黙の方が恐ろしいと感じます。子どもたちの反応は、いつの時代も、その時々の子どもたちの置かれている状況を映し出していることに変わりありませんから。そして、その反応から、わたしたちがすべきことがわかってきます。
そうこうして、親孝行や友情や勇気など、観客の反響を見ながらテーマを設定し、上演を続けていると、やがて各地から支援者が現れるようになり、劇団結成10年後には、応援団的なかたちで「青少年の心を育てる会」が立ち上がりました。わたしたちの活動に賛同してくださった各界のそうそうたる方々が、理事として支援してくださるようになり、今年は30年という節目を迎えます。
よろこばせることが自分のよろこび
それがパワーの源
 被災地にて“やなせたかし作品”の読み聞かせ |
演劇を観るというのは、いわば他人の人生を見るということ。客観的に見るということで、たとえば「あの人はこんなこと言っていたけど、本当はこうかもしれないな」と思いやることができるようになっていきます。そうしたことを積み重ねていけば、人間同士のつながりが薄くなってきている今の時代も、少しずつ変わっていくのではないでしょうか。
親孝行をテーマにしたミュージカルでは、親孝行とはどういうことかわからない子でも、ミュージカルの中で表現すると、効果的に伝わるようです。他の人のやっていることや言葉は、素直に受け止められるんですね。そうでないとお説教になってしまいますから。親子で来て、自由に観て自由に考えて、帰りに「親孝行ってほかにどんなことがある?」とか話しながら帰る。それで親子の会話が増えればいいなと思います。
劇場は素直になれる場でもあります。あるとき、見るからに不良っぽい男子高校生が、上演後に「涙って感動する時にも出るんですね」と言ったのです。「そんなこと、初めて知ったの?」という驚きとともに、演劇によって素直な気持ちになれたんだなと、手ごたえも感じました。
時代は変わっていきますが、何が一番お客さまの心に響くかを考えると、それはやはり“ことば”なのです。そのことばに音楽を加えると、より響きます。わたしたちはそこをはずさないでやっていこうと決めたのですが、そんな折に、マンガ家であり絵本作家のやなせたかしさんに出会い、やなせ先生の作品をミュージカルとして上演するようになりました。東日本大震災後には、陸前高田市の奇跡の一本松をテーマにしたミュージカル「松の木の歌4部作」を各地で公演したり、先生の詩を朗読して、地域のFM局の方にレクチャーしたりすることもありました。
どこからそんなエネルギーが出てくるかって?自然とエネルギーが出てきちゃうんです。「やらなきゃいけないな、うん、やりたい、やろう!」と思うんです。うーん、使命感っていうより「自分がやりたいな」と思うんです。これを伝えたい、そうしたらみんなが元気になるなって。やなせ先生は「よろこばせることがよろこび」と、表現してくださいましたが、そのとおりかもしれません。
“思い”で雰囲気を拡げるのが役者の仕事。劇場という空間で燃焼して自分の言うことをしっかり伝える。その“役者が出したエネルギー”に共感すると、劇場はその色に染まります。それは役者たちへのたったひとつのごほうびでもあるんです。
「かわいいね」と、まず抱きしめよう

わたしは子どもがいないので、子育てについて自分の体験としては語れませんが、「かわいい子ね!」と思って抱きしめるところから始めればいいのではないかと、よく思います。人は抱きしめられると安心します。安心すると優しく嬉しいエネルギーが身体中に広がって、深い呼吸がわいてきて、リラックスできる。「かわいい」と本当に思えば、声も態度も変わります。子どもは感覚が鋭いので、ちゃんと見ていますし、伝わります。イヤイヤやっていると、すぐ見抜かれますから。
向き合っての会話も大事。芝居ではよく言われるのですが、しゃべるときにおへそとおへそを向き合わせると、会話になります。おへそが反れていたら会話にならない。要はストレートに向き合うことではないでしょうか。大きな声を出すことも、自分の意思を他人に伝えるコミュニケーションの第一歩。ぜひ挑戦してもらいたいですね。
失敗も大事だと思います。なぜなら、その失敗を踏み台にして生きることができるから。「これで失敗したのだから、別の方法でやってみよう」と、他のアイデアが出てきますよね。でも最近は親も失敗させないようにし過ぎだと感じています。「育てる」なんてしなくても「見守って」いてあげればいいんじゃないでしょうか。
わたしもそうだったように、幼いころ親から注意されて残っている言葉ってそうたくさんはないでしょう?はっきり記憶しているのは中学くらいからで、そこまでは親が自分の人生の中で“生きていくために大切だな、必要だなと思った知恵を身につけさせる”。それで十分なのではないでしょうか。親御さんがもっと自信を持ったら良いと思います。
ミュージカルのパンフレットの鼎談で、やなせ先生とNHK元会長・川口幹夫氏(当会三代目会長)と3人でお話をしたとき、私は「わたしたちのミュージカルの対象は0歳から99歳までなので、ターゲットは?と聞かれるととても困る」というご相談をしました。川口氏は「テレビ番組でもね、企画書には必ず年齢層や性別と言ったターゲットが必要です。しかし必ずしも当たるとは限らない。むしろ特定の個人を想定した方が番組としてあたる」とおっしゃいました。やなせ先生も「自分の中で規制をつくらないで」そして「稲垣さんがやりたいと思うこと、ステキだと思うことを……」「やればいいんですね?!」と私。「そう!!」とお二人。うれしかったですね。そして自分がやりたいと思うこと、素敵だと思うことをしっかり見定めて、ゆっくり歩いていけたらと思っています。
今の私のキャッチフレーズ。これは昨年の暮れに初演したミュージカル「小公女セーラ」のそれでもあるのですが、“夢見る力は、生き抜く力”。こんな時代ですもの。お互いに大きくて力強い夢を追いかけましょう。
関連リンク
劇団目覚時計
青少年の心を育てる会
※3月30日(水)に青少年の心を育てる会主催のイベントがございます。
詳細については、こちらのサイトでご確認ください。
 |
前編のインタビューから -愛があふれる家庭で育った子ども時代 |