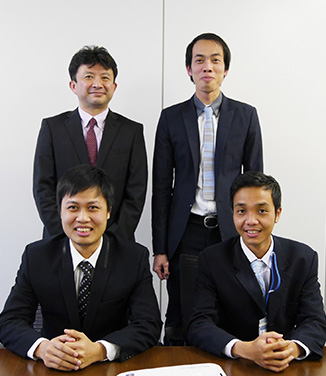社員の基礎トレーニングとして、公文式の算数・数学を導入
 |
BHIJホールディングス株式会社は、北米に本社のある外資系企業の日本法人で、コンファレンスセンターと呼ばれる会議室専門の施設を運営しています。現在、同社の運営しているコンファレンスセンターは、東京都の品川と有明の2か所。施設内のカフェ・レストランの運営も行っています。
BHIJホールディングス株式会社では、7年前からほかの企業に先駆けて公文式の算数・数学を社員研修の一環として業務の位置づけで取り入れてきました。導入の決め手は「脳のトレーニング効果」だったといいます。7年間の導入を経て、学習を通じた社員の状況の把握や、社員の仕事の仕方の変化などさまざまな効果が表れているそうです。
現場から離れていても、公文式学習を通じてスタッフの様子がわかってくる
同社の管理部長として、社員の人事・総務・経理・庶務の業務を一手に引き受ける鈴木傑さんに、導入の経緯を説明していただきました。
 本社管理部 部長 鈴木傑さん |
―― 社員教育に公文式を取り入れようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
私自身が、実際小学生のときから高校を卒業するまで、公文式の算数・数学を学習していました。ただ、今回導入したきっかけはそこではなく、役員からの提案でした。しかし、公文式を企業研修で使うなんて聞いたことがありません。どこに問い合わせをすればよいかわからず、公文の代表番号に電話をしてみたところ、「ちょうど法人向けの事業が立ち上がったところです」ということで、担当部署から折り返しご連絡をいただきました。結果として、私どもが企業での導入第一号となり、2010年の9月から学習をスタートすることになったのです。
―― 役員から「公文式をやってみてはどうか」という提案があったというのがユニークですね。
そうですね。実は私どもの会社は、全世界では1万人の従業員がいるのですが、日本法人は約50名です。少ない人数で接客と事務仕事の両方をこなす必要があるので、頭をフル回転させないとつとまりません。そのなかで、OJT以外でどのような基礎研修が必要だろうかと考えていたところに、役員から「脳を活性化させるという目的で、公文式をやってみてはどうか」という提案があったのです。それを聞いたときには、大胆な提案だと思いました。今までに企業でそういった事例はないし、はっきりとした効果があるのかどうかはやってみないとわかりませんでしたしね。ただ同時に、非常に面白そうな提案だと思いました。私自身も子どもの頃に公文式で学んだ経験があり、学生時代には採点のスタッフもしていたので、公文の教室の雰囲気はわかっていました。ですから、あの教室を会社でやればいいのかとすぐにイメージできたことは確かです。
役員から「公文式を社員教育に使おう」という発想が出てきたのは、弊社の企業風土も大きく影響していると思います。実は弊社が日本で事業を始めた1999年の時点では、日本にはコンファレンスセンターという施設はありませんでした。前例のない新しいものを創造してきた会社ですので、経営陣にも新しいことにチャレンジしてみようという考え方があるのです。
―― あえて「算数・数学」を取り入れたのはなぜですか?
公文の担当者から、算数・数学の教材には、脳のワーキングメモリを活性化させる効果があるという話をうかがって、非常に共感したからです。弊社では、自分の仕事しかしないのではなく、全体を見ながら足りないところを見つけてすぐに応援に行けるような体制を心がけています。そもそも、お客さまからすれば、このスタッフは料飲部で、このスタッフはコンシェルジュだなんてわかりませんしね。それで、一人ひとりの能力をアップするために、公文式の学習をやってみることにしました。
―― 研修の対象者や学習の頻度などを教えてください。
去年までは業務の繁忙期ではない毎年8~9月と1~2月頃に週1回の学習日を業務時間内に設けていました。学習日になると研修対象者に品川のオフィスに集まってもらい、1時間程度学習してもらいます。研修対象者は現場の中心的な存在となるスタッフです。いつも4~5名の体制で学習を行っています。基本的には、学習は一度始めたらずっと続けます。退職や産休・育休・時短勤務にならない限りは「卒業」することは特に考えていません。
―― 公文式の効果について、感じられていることはありますか?
私も学習日のときに、文京区の本社から品川のオフィスまで移動して、受講者の答案を採点しています。それで、採点をしていると、本人たちの癖や傾向性がとても出ることに気づきました。その人に一貫した癖もあれば、その日にだけ出る癖もあります。たとえば、精神的に落ち着いていないと、すごく乱れた文字で答案が書かれていたり、まるまる半ページが空欄になったりするんです。そういうときは「大丈夫?」などと声がけするようにしています。普段は現場から離れているので、実際に現場で働くスタッフの様子はわかりませんが、公文を通じてスタッフの様子がわかってくるという側面があるのだなと実感しました。
仕事に追われていると、自分で参考書を買って勉強しようと思っても、つい後回しになってしまうものです。でも、公文式なら翌週の学習日に提出しなければならない宿題が出るので、皆さん自然と「やらなければ」と思うようですね。宿題に書かれた学習時間の記録を見ると、夜10時、11時という日もあり、忙しくてもなんとかやりくりして学習時間を絞り出そうと各自で努力していることがよくわかります。
導入して7年ですが、続けることのよさを実感するようになりました。国語や英語を取り入れることも検討してみたのですが、今はとりあえず算数・数学に絞り込んでやろうと決めました。去年までは繁忙期を避けた時期に週1回という頻度で学習日を設定していましたが、今年からは繁忙期のときも月1回にペースダウンしながら、空白期間がないように学習日を継続して設定するつもりです。もし、それで半年かやってみて効果がありそうなら、秋からも同様に空白期間を作らずに学習日を設定しようと考えています。
継続することが力に。暗算が得意になり、
仕事にも役立つ
 コンファレンスサービス部 マネージャー 高橋昌史さん |
2010年に会社で初めて公文式を導入したときから、算数・数学の学習を続けている高橋昌史さん。普段はコンシェルジュとして、お客さまへのサービスを担当しています。高橋さんに、実際公文式で学んでみての感想をうかがいました。
―― 公文式で学んでみて、いかがですか?
最初に学習の話をいただいたときは、大人向けのプログラムがあるのかと思っていました。しかし、小学生の範囲から始めたので驚きました。でも、実際にやってみると、昔習ったのに忘れてしまったことをどんどん思い出して、その知識をさらに積み重ねていくことが楽しいと感じています。ある程度自分がやりたいと思ったときに都合よくできるというシステムもとてもよいと思います。
―― やってみて自分が変わったと思えるところはありますか?
暗算の力が上がり、それが仕事でも実際に役に立っています。たとえばお弁当をこの部屋とこの部屋に入れると、何個余るのだろうかというのを、ほかの人よりも素早く答えられるとうれしくなります。また、現在は教材に時々出てくる文章問題を解くと、文章問題は頭を使うからか、仕事でも“ひとつ先の次の一手”を考えられるようになってきました。学習を始めてから7年たちましたが、「やる気オーラが出てきている」と言われるようにもなりました。今後は、せめて高校の範囲までは進んでみたいと思っています。昔学校で教わったのに、今できないというのは恥ずかしいですしね。
公文を始めて仕事の段取り力が上がった
 料飲部 濱町真弓さん |
会議中の飲み物やお弁当などの手配を担当している料飲部の濱町真弓さんは、学習に意欲的に取り組んでいて、進むスピードも速いそうです。
―― 学習の進め方はどのような形ですか?
なるべく週1回の学習日には出るようにしていますが、どうしても出られないときは、お休みの日に子どもと一緒に公文の学習をしています。「1か月で30枚、できれば1日1枚やるぞ」という目標を自分で決めて、目標を達成すべく頑張っています。
―― お子さんと一緒に学習しているんですね。
もともと、わが家では子どもが公文式を始めたのが先だったんです。その後、私が会社から声をかけていただき、私自身も学習するようになりました。今は子どもから「お母さんは1日1枚でずるい。僕は5枚なのに」と言われますが(笑)、こちらは子どもに追いつかれそうで焦っています。でも、親子ともにいい刺激になっていることは確かです。
やってみて自分が変わったと思えるところはありますか?
なんとなく後回しにしてきたことをやろうと腰を上げるのが、以前ほど苦ではなくなってきました。公文では、たとえ苦手な内容でもやっていかないとたまる一方なのですが、仕事も同様にやらないとたまっていく一方ですからね。あと、出勤する少し前に1~2枚やってから出勤すると、その日の仕事は上手に段取りが組めて、スムーズにこなせるようになるんです。逆に、夜寝る前にやってしまうとちょっと頭がさえてなかなか寝つけなかったりするんですけどね。
鈴木部長は、「暗算が強くなったという直接的な効果だけでなく、脳が活性化するという効果も感じてくれているのはありがたいですね。さらに、仕事の段取りがよくなるという効果まであるとは思いませんでした。これはうれしい誤算です」とお話ししていました。
昨今の労働市場は人手不足なうえ、働き方改革も声高に叫ばれています。サービス業は、AIロボットにとってかわられるかもしれないという危惧すらあります。そういった社会の風潮の中、優秀な人材をさらに優秀にするのが企業の課題です。公文式は、そのような人材のトレーニングとしても、予想以上に効果的だと実感していただいているようです。
関連リンク
企業での公文式 人材育成支援
東京コンファレンスセンター