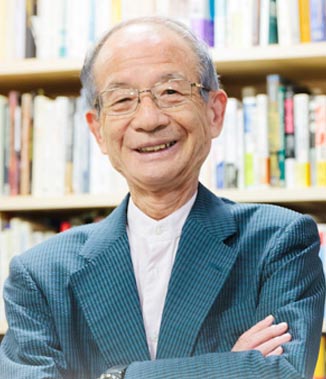先生の可能性を最大限に伸ばし、教室の土台をつくる「育成職」という仕事
 東京本部 育成チーム 西條智幸 |
まず、私たち「育成職」の役割についてお話しします。「育成職」は、新しく公文式教室を開くことが決まった方の、「研修」から「教室の開設」、そしてその後の「教室における生徒指導・運営のサポート」を約2年にわたり担当します。公文の先生になることを志望する方々は、「教育を通じて地域や社会に貢献したい」、「子育てと両立しながら仕事がしたい」、「ライフワークとして長く子どもの成長に関わることができる仕事がしたい」など、さまざまな想いをもって公文の先生としての仕事を選択してくださいます。
私たち育成職は、そういった先生のライフスタイル、バックグラウンドを理解した上で信頼関係をしっかりと築き、公文式学習を通して子どもたちの可能性を伸ばす仕事に喜びややりがいを感じていただけるようサポートしています。そして、教室が開設された地域の方々から「公文の教室に行きたい」「○○先生に会いたい」と思っていただけるような教室の土台作りをお手伝いしています。
指導の現場を経験したからこそわかる先生の気持ち
私は2006年に公文に入社しました。そして配属先で、研修の一環として半年間、実際に自分自身が指導者として教室を運営しました。無我夢中の日々でしたが、この時「自分の関わりにより生徒が変化・成長するやりがい」を知ることができました。その後は、公文式教室の先生方のサポート業務を担当。そして入社から5年目、会社が運営する直営教室を受け持つことになりました。ここでの教室経験が、いま「育成職」として働く自分にとって大きな財産となっています。
-「教材準備」の大切さ -
私が公文式教室の指導者として一番力を入れて取り組んだのは「教材準備」です。公文式学習法の特長として、「個人別学習」「自学自習」「学年を越えて進む」があり、それを実現するためにスモールステップで構成された「教材」があります。教室では、先生が一人ひとりの“ちょうど”を見極めて、教材を準備します。その“ちょうど”の教材に取り組むことで、子どもたちは「少しがんばれば自分の力で解ける」問題をくり返し学習し、やがて学年を越えた内容を学習できるようになっていくのです。
このように、“ちょうど”を見極めて教材を準備するためには、子どもたちの日々の状態をしっかりと把握していなければなりませんし、教材の知識も必要です。入社後、教室経験が浅かった頃は、実際に現場で教室を運営頂いている先生方や先輩社員にアドバイスをいただきながら、教室運営をしていましたが、“ちょうど”の見極めの甘さが原因で、生徒がその日の教材で達成感を感じることができないまま帰らせてしまったこともあります。
公文式の創始者である公文公(くもん とおる)の言葉の一つに、「悪いのは子どもではない」というものがあります。この言葉が幾度となく頭をよぎりました。それでも生徒さんは週2回必ず通ってきてくれますので、先生である私には待ったなし。子どもたちに損をさせず、より伸ばしていくために、私自身もどんどん指導力を磨き、前進していく必要がありました。
-チームで教室を運営することの大切さ-
教室を引き継いで半年がたち、生徒数も増えてきたころ、自分一人で教室運営の何もかもを抱え込んでいては、子どもたちのための指導力向上や教室運営ができないという現実に直面しました。そして、一人ひとりの子どもたちの学習計画、教材の準備や採点、学習の記録、保護者の対応など、教室におけるさまざまな仕事の優先順位をつける必要があると感じました。そこで「指導者にしかできないこと」と「スタッフに任せていくこと」を明確にし、指導者とスタッフがひとつのチームとなって一緒に子どもたちを伸ばす体制を作り、以前よりもスタッフとのコミュニケーションと連携を図るようにしました。教室で起こる生徒の変化や成長をスタッフとともに喜び、わかち合うことで、複数の目で生徒を見守る体制ができ、スタッフもそれまで以上にやりがいをもってくれるようになりました。
このときの直営教室経験では、公文の先生という仕事のやりがいと素晴らしさはもちろんのこと、より近い目線で先生の気持ちを理解することができたと思っています。2013年からは「育成職」を担当することになりましたが、教室で得た実体験を糧とし、先生の良き理解者であり、パートナーであることを目指して日々仕事をしています。
一緒に教室をつくり上げていくパートナーとして
 |
公文の先生は、日々いろいろなことに悩んでいます。社員の立場で教室を見て課題を感じることがあっても、私たち育成職はいきなり課題を指摘するのではなく、まず先生の話に耳を傾けます。なぜなら、先生の一つひとつの行動には、子どもたちのことを考えた上での意図や想いがあり、それをきちんと受け止めることがとても大切だと思うからです。それを理解した上で、KUMONの看板を掲げている以上、公文式の原点に立ち戻りながら、必要な改善に、ともに取り組んでいくのです。
私自身も教室を担当していた時にこだわって取り組んでいた「教材準備」に関して言えば、子どもたちがつまづきやすい箇所や初めて学ぶ箇所の確認などを、お手本を見せながら先生と一緒に取り組んでいきます。また、教室を運営していく上で欠かせない保護者やスタッフとのコミュニケーションについても、保護者面談やスタッフミーティングに同席するなどして、教室の運営基盤がしっかりと出来上がるまで関わっていきます。
私は、先生とのコミュニケーションの際には、それぞれの先生が本来持ち合わせていらっしゃる「強み」を見極め、しっかりと活かせるようにすることが大切だと考えています。人は自分のマイナス面には敏感ですが、良い面についてはなかなか気づかないものですので、先生の良いところや活かすべきところはきちんと共有します。時には一緒に立ち止まり、現状や課題を認識するため話し合いもします。そして私の想いだけでなく、先生が納得するまですり合わせを重ねるようにしています。
私は小さいころから野球をしてきましたが、たとえて言えば、野球の「ヘッドコーチ」的な役割ですね。コーチは、試合で選手が最高のパフォーマンスができるようにサポートをします。ヘッドコーチはそのコーチたちのとりまとめ役。公文式教室でいうと、先生が最高の状態で子どもたちの指導にあたれる、そのために必要なスタッフとのチーム作りを進めるということです。教室開設から2年後、先生方は私たち育成職の手を離れ、いよいよ自走体制に入って行きます。そのときに、教室という「チーム」で運営をできている状況であれば、安心して地域の担当者にバトンタッチをすることができます。
「公文の先生」という顔を持った教育者になる。そこに立ち会えることのやりがい。
育成職として、私はこれまで20人以上の新任指導者に関わってきました。公文の先生になることを切望し、ご家庭の事情が許すまで6年間近く待ち続けた方が、ようやく教室をオープンできたときは、非常に感慨深いものがありました。その教室の記念すべき初めての学習日、一人目の生徒さんが教室に入って学習を始める瞬間、先生の目に光るものがあったことは忘れられません。
 |
教室での子どもたちの成長と同様、育成職は先生の成長も目の当たりにします。この仕事の醍醐味の一つは、「先生が成長していく過程に立ち会えること」だと他の育成職社員も口をそろえて言います。新任指導者にとっては、何もかもが新しく、そして新鮮なことばかりです。そのため、本当に小さな一つの出来事でも先生の考え方や価値観が変わることが多く、教室開設から2か月もたつと先生の表情も、“公文式を通じて子どもを伸ばす喜びを感じている教育者”の輝きに満ちた顔になるのです。
私の夢は、自分がこれまで関わってきた先生方が、アドバイザーと呼ばれる経験豊かな指導者として後輩に自身の経験を伝える立場になる日が来ることです。それが叶えば、次は新しい世代の先生を一緒に育てていくことができるからです。公文には次の世代に技術と経験をしっかりと継承し、育てていくという文化があります。その一端を担っているという自負と責任とともにこれからも先生方と歩んでいきたいと思っています。
関連リンク くもんの先生募集