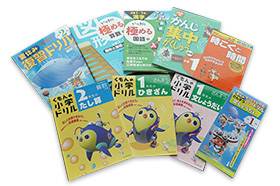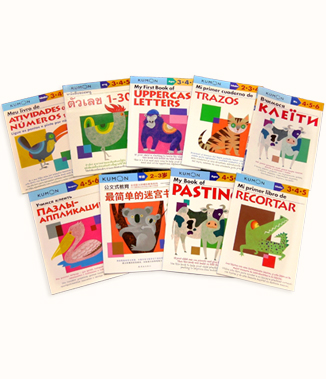Q.くもんの小学生向けドリルが誕生したきっかけを教えてください。
 くもん出版 編集部長 泉田義則(※肩書は当時のものです)
くもん出版 編集部長 泉田義則(※肩書は当時のものです) |
くもんの小学生向けドリルが誕生したのは、1989年のことです。最初に発売された「くもんの小学ドリル計算シリーズ」は四半世紀の間、変わらず好評をいただいています。
小学生向けドリルの出版に至った一番の理由は、家庭学習にも公文式のメソッドである「子どもの“できる”を大切にした、自学自習の学習方法」を取り入れて、子どもたちの学習に対する意欲向上に貢献したいという思いがあったからでした。そのため、ドリルを制作するうえで大事にしたのは、いかに公文式のメソッドを応用したものにできるか、ということでした。
公文式教室では先生がいて、子どもの学習のようすを見てコミュニケーションを図りながら、教材を進めていくことができます。しかし、一般のご家庭ではそうはいきません。だからこそ、いかに子どもたちがやりたくなり、自力で学び、「できる!」という自信が湧くドリルにできるか。
ドリル制作にあたっては、モニターの子どもたちを対象にパイロット版のドリルを試してもらい、実際に子どもが解いているようすを見て、検証しています。子どもの手が止まり、順調に解けないような箇所があれば、難易度をなだらかに調整するなど、もっといいものに修正をしていきます。公文式教室の教材制作者が心がけている「子どもから学ぶ」という視点。ドリルの制作においても、そのことを常に心がけています。
Q.くもんの小学生向けドリルの特徴を教えてください。
一般に、ドリルには「評価型」と「習熟型」と大きく2種類のタイプがあります。「評価型」は、いま何ができて、何ができていないかを評価をするもの。一方「習熟型」は、いま何につまずいているかをあぶりだすのではなく、解き進めながら力をつけることを目的としています。「くもんの小学ドリル」は、公文式教室と同じようにがんばったらできるという達成感を得ながら、少しずつステップアップしていく「習熟型」のドリルを目指しています。
私たちは基礎を大切にしています。例えば、『くもんの小学ドリル1年生のたしざん』では、初めてたし算の計算式が出てくるのは15回。14回までは、数の並びについてくり返し学習します。これは、たし算をスムーズに進めるには「数の並びがきちんと理解できていることが必要」という公文式算数教材の考え方にのっとったものです。また、学年があがった時にも必ず前の学年の復習から始めます。2年生であれば1年生で習った一けたのたし算、ひき算のページがまず用意されているのです。
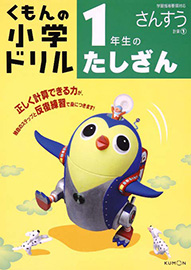 |
 |
 |
これは単に解ければ良いという考えではなく、必要な基礎を正しい順番で積み上げることで、確かな力を得てほしいという思いからです。この“下積み”こそが、学年があがって難しくなったときにつまずかないために大切になってきます。公文式の「できた!」「わかった!」は、表面上のものではなく、しっかりとした土台の上にある力。それをドリルにも、取り入れているのです。
Q.途中でつまずかないように、どんな工夫がされているのですか?
 |
くもんのドリルは、公文式教室で使用している教材と同じように“スモールステップ”で構成されています。次のページを開いたら、教科書のように全く新しい内容のものが出てくるのではなく、少しずつステップアップしていきます。また反復練習も取り入れているので、知らず知らずのうちに、少しずつ力が高まっていくことを目指しています。この“少しずつスラスラと”が、真の力を育んでいきます。
ご使用いただいた保護者からのアンケートでも「1枚1枚進むごとに、たし算が楽しく思えているように見えました」「最初はすごく簡単でしたが、少しずつ難しくなり、ちょうどいい加減だったので、最後まで楽しく学習できました」といった感想をいただいています。公文式が目指す「子どもたちが意欲的に学習習慣を身につけること」が、ドリルでも実現されているというのは、本当にうれしいことです。
Q.子どもに苦手分野が出てきた場合はどうしたらいいでしょう?
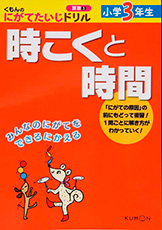 「にがてたいじドリルシリーズ」
「にがてたいじドリルシリーズ」各540 円(税抜) |
くもんの小学生向けドリルは、15種類のシリーズがあります。「にがてたいじドリルシリーズ」は、「うちの子は、計算はできるけれど、時計が苦手です」という声が多く聞かれたことがきっかけで生まれました。その単元だけを学習したいという声にこたえた訳です。例えば、小学1年生から3年生でならう算数の「時こくと時間」の単元をピックアップし、一冊にまとめています。
実は子どもが何かの単元でつまずいた場合、その原因が前の学年やその前の学年にひそんでいることが多分にあります。「にがてたいじドリルシリーズ」が2、3学年前の内容から始まる理由はここにあります。また、子どもが嫌になって途中で投げ出さないように問題量やレイアウトにもこだわりました。子どもにとって、1冊をやり終えるというのは人生が変わるくらいの大きなできごとです。達成感によって生まれる自信こそが、後に学習意欲へとつながっていきます。
*記事末尾にお子さまの課題・目標別にオススメのドリルを示した一覧表がありますので、ご参照ください。
Q.夏休みにオススメのシリーズはありますか?
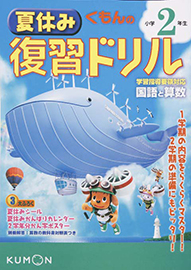 「くもんの夏休み復習ドリルシリーズ」
「くもんの夏休み復習ドリルシリーズ」各540円(税抜) |
 「くもんの夏休みもっとぐんぐん復習ドリルシリーズ」
「くもんの夏休みもっとぐんぐん復習ドリルシリーズ」各440円(税抜) |
保護者の皆さんにとって、一番心配なのが夏休みの過ごし方ではないでしょうか。長期間の休暇ということで、一学期で身についた学習習慣が乱れてしまうケースは少なくありません。しかし、逆に言えば、しっかり、じっくり学習することができるのも夏休み。一学期の復習をきっちりとしておけば、二学期の学習へもスムーズに入ることができます。
まず、学習習慣をつけたり、維持したりするのにオススメしたいのが「くもんの夏休み復習ドリルシリーズ」です。1日1ページという量なので、無理なく毎日、学習を続け、1学期の内容をしっかりとおさらいすることができます。
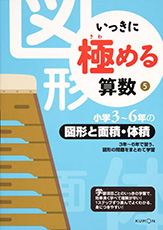 「いっきに極めるシリーズ」
「いっきに極めるシリーズ」1000円〜1200円(税抜) |
また、夏休みを利用して、苦手分野の復習をする、あるいは得意分野を先取りして学習するためにオススメなのが「いっきに極めるシリーズ」です。通常、学校の教科書では、例えば「図形」を習うにも、3年生から6年生まで4年間をかけて少しずつ学習していきますが、学年を越えて一気に習得できるようにしました。まさに学年の枠を超えたドリル。活用の方法はさまざまで、1、2年生のお子さんが、3年生で習うことを“先取り”で学習することもできますし、逆に6年生が中学受験のための総復習として活用することもできます。
お子さんの“できる”から生まれる自信や意欲を育み、次への大きな一歩を踏み出してほしい。くもんの小学生向けドリルは、そんな思いを込めて制作しています。
関連リンク くもんの小学生向けドリル 商品ラインアップ|くもん出版 くもんの小学生向けドリル お子さまの課題・目標別オススメのドリル一覧表 KUMON PARK オープン!|KUMON now! 幼児ドリル全面改訂|KUMON now! 外国語版ドリル「Kumon Workbook」|KUMON now!