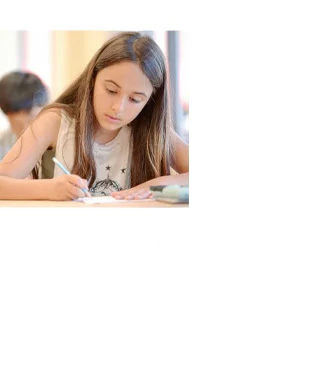国は違っても、教材は同じ
 実際に子どもが問題を解く様子を確認する参加者たち |
今年海外からこの会議に参加したメンバーは、19人。それぞれの国や地域で、社員や指導者の教材知識や指導力を向上させる役割を担っています。「世界数学担当者会議」がスタートした当初から毎年参加しているメンバーもいれば、今年初めて参加するというメンバーもいました。会議中は日本語、英語、中国語、ポルトガル語、韓国語など複数の通訳が入ります。話す言葉が違っても、このように一堂に会して議論ができるのは、KUMONの数学教材は世界で同じ内容のものが使われているから。
数学教材の指導部リーダーとして、今回初めて会議に参加した南米公文のファビアナ。彼女はKUMONに入社して18年です。その大半の期間は、公文式教室の運営サポートに関わる仕事をしてきました。立場は変われど、扱っている教材は同じ。彼女は、これまでの経験をもとに「今回の会議では、B~D教材(小2~小4レベル)の指導について詳しく学んでいます。ここでの学びを15あるブラジルの支局の指導担当社員にいかに早く届けるか、が自分の大切なミッションの一つです」と話してくれました。その強い使命感の原動力は、「これまで教室で出会ってきたたくさんの子どもたち」だと言います。
会議でも貫かれる「子どもから学ぶ」スタイル
KUMONでは「子どもから学ぶ」という考え方を大切にしています。教材指導について学び合うこの会議でもその思想は貫かれています。日本の教材制作の担当者が、単に教材の構成や意図を説明するだけでなく、実際に子どもがその教材を解いている様子を皆で一緒に確認し、子どもを観察する観点をすり合わせていきます。
入社5年目の南米公文の数学指導担当・へナタは、「子どもが教材を解く様子を確認し、議論しながら学ぶのがいい。先ほどビデオで、最初はたし算を指を使って計算していた子が、何回かの復習を経て、時々指を使う程度になった様子をビデオで確認しました。実際の子どもの様子を合わせて学ぶと、知識だけをインプットするより、深く理解することができる。教材知識と子どもの能力を結びつけて考えられるようにしたい」と語ってくれました。彼女の視線の先にも、やはり子どもたちがいます。「KUMONの教材は素晴らしい。でも教材だけでは一人ひとりの子どもたちを十分に伸ばすことはできません。ブラジルの指導者たちにも私と同じように学んでもらい、ブラジルの子どもたちにKUMONで数学の楽しさを感じてほしい」と言います。
異なる国への情報伝達というチャレンジ
 盛り上がるグループディスカッション |
アジア・オセアニア公文は、12の国と地域の公文式教室をサポートしています。展開の歴史も現在の状況も大きく異なる中、各国の数学指導担当のサポートをしているのは、アジア・オセアニア公文のフェンフェン。彼女は、この会議に参加しながら“いかにこの学びを持ち帰り、どのように伝えていくか?”を常に考えていました。「状況が異なる国々の社員や指導者に対して、共通のトピックスは何かを考えることが大切だと思っています。いろんな解釈ができるテーマでは、うまく伝わらない。同じ認識を持てるトピックスを探しています。そのトピックスを突破口に、地域全体でステップアップしていけるようにしたいと考えています」と言います。
この会議を主催している日本の数学教材部の小玉は、「この会議は今年で9年目。継続して開催しているからこそ、参加者や各地域の取り組みのレベルが上がっている手ごたえを感じています」と語ります。その陰には、日本の数学教材部のさまざまな努力もありました。数学教材の指導に関する情報や指導者向けの講座資料を英語にして提供したり、実際に現地の教室を訪問したりと、各国の担当者とコミュニケーションを重ねてきました。「この会議の参加者は、各国の公文式指導者の算数・数学教材の指導力向上を図る上で、重要な役割を持った方々。これからも皆でレベルアップしていけるよう、努力を重ねたい」と小玉は語ります。
公文式教室での教材の指導を通じて、「一人ひとりの子どもの可能性を最大限に伸ばす」という公文の理念を実現するために、担当者たちは今日も学び続けています。