お笑い芸人になりたかったが
「文化をつくる」演劇に魅了
前編で少しお伝えしましたが、私はもともと、お笑い芸人になりたかったんです。お笑いが流行っていた1990年代、私は名古屋の高校生でした。思春期によくある「ここに俺が求めるものはない!」という思いから、東京や大阪に出たいと思っていました。
でも親からは大学に行けと言われ、それなら演劇の学校に行けば、お笑い芸人になるための勉強になるかなと考え、演劇学科のある大学を受験しました。幸い合格し、入学すると今度は、演劇の魅力に取りつかれました。

それまで私が想像していた演劇は、古くて堅くてつまらないものでした。ところが小劇場ブー厶だった当時、友人に誘われて、野田秀樹さんや三谷幸喜さんなどのお芝居を観に行ったら、「こんなにおもしろいんだ! ちゃんと勉強をしよう」と、演劇に夢中になりました。
あの頃の演劇は、当時の若者の文化や時代を強く反映していて、かつ、若者の鬱屈や「どう生きるか」というテーマを、すごくエネルギッシュに訴えかけていた。演劇が世の中を動かし、若者の文化をつくっているのを肌で感じられた時代でしたね。もちろん今でもそういう側面はあると思います。
当時の私は役者をしていましたが、野田さんや三谷さんのように、「作・演出」として、一人で戯曲と演出を手掛けるのがブームでもありました。そこで私も戯曲を書いてみたところ、役者をやるよりも評判が良く、次第に劇作家になろうと考えるようになりました。そして大学卒業後、劇作家を募集していた青年座という劇団に入団しました。当初は「僕は演出はやりません」と言っていたんですが、新人1年目の勉強として現場で学んでいくうちに、「演出って楽しいな」と思うようになったんです。以来、演出家の道を歩んでいるわけです。
そうやって紆余曲折を経た私が思うのは、「あまり自分の人生を決めなくてもいいのでは」ということです。いや、何にも決めないのはダメで、ある程度の方向性は必要ですが、自分が何かを「やりたいな」と思ったときにそこに向かえる体力を蓄えるなど、「土壌」をつくっておくといいと思います。
公文式のおかげで暗算が得意に
娘は成績アップし本好きに
私は小学2年生から公文式教室に通っていました。引っ越ししたので1年でやめてしまいましたが、ひたすら計算問題を解いていた記憶があります。おかげで暗算は今でも非常に得意です。仕事でも大道具に必要なスペースやモノの数などが、細かくパッと頭の中で判断できます。これも公文式で鍛えられたおかげかもしれません。
私の娘たちも公文式で学習していました。長女は年長から中2まで国語と算数・数学を、次女は小2から2年間、算数・数学を続けていました。長女によると、公文式のおかげで計算が早くなり、中学校でも先生にほめられたとか。次女は計算力のおかげで、苦手だった図形が得意になったと喜んでいました。ふたりともテストの点数が上がり、公文式教室の先生に感謝しているそうです。
また次女は公文式教室で本好きになりました。国語は学習していませんでしたが、家族が迎えに来るまでの間、教室にある本をずっと読んでいたからだそうです。自分ではまだ学習をしていない保育園の頃から、姉が学習している間、公文式教室で待ちながら、絵本を読んでいたようです。

私は作品をつくる際、世の中や社会、そこに生きている人と向き合っていかなければいけないと思っています。そのために、常に新しいことを吸収し、自分自身をアップデートすることを意識しています。
子育てでも、自分をアップデートさせるのは大切です。小さい頃は「これやって」と言えば、言うとおりにやっていた子どもも、成長すると次第に親の言うことを聞かなくなり、そうすると「なんでやらないんだ」とイラっとしますよね。でも「そういうものなんだ」と受け止めて、自分の考え方をアップデートしていかないといけないんだな、と思います。
このことは、社会を取り巻く環境や、若者や社会人の認識の変化などに対しても同じです。「変化」をダイレクトに感じ取って、常に自分をアップデートしていかないと、表現や創作はできません。人生すべて、日々学ぶことばかり。常に自分を新しくしていかなくてはならないと思っています。
演劇は「唯一の芸術」になる可能性も
「人間を描く」ことを続けていきたい
「継続していく」ことは、すごい力になると思います。私自身の生き方もそうですし、娘たちの勉強を見ていてもそう思います。だからお子さんたちには続けることを大切にしてほしい。
でも、花開くのはちょっと先かもしれません。教育は種まきだと思うのですが、種をまく方も疲れてしまうことがあります。でも花が咲いたときに、それまでの人生が報われた気がするはずです。ですから、お子さんがそのときは理解が至らなかったとしても、その子の中では蓄積されているので、待っていてあげてほしいです。
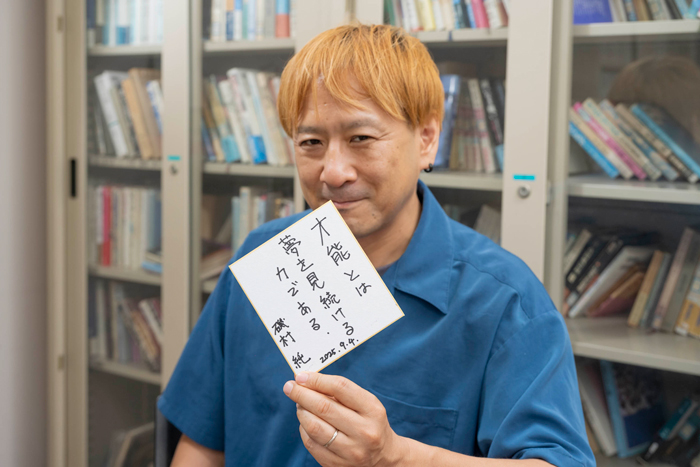
「才能とは夢を見続ける力である」
私は演劇学校や大学、市民ワークショップなどでも教えていて、言いたいことを伝えるのが難しい状況に直面することがあります。でもそんなとき、相手が何かひとつでも「こうだ!」と理解があると、双方ともに、とてもうれしい。これが教育の喜びですよね。諦めずに水を与え続けることは大事ですが、あまり与え過ぎると腐ってしまう。今はどんな塩梅(あんばい)か、様子を見守ることも必要ですよね。
私が「演出をやろう」と思ったのは26歳の時。やや遅いです。さらに、周囲から「演出家」と言われ、自分でもそう名乗れるようになったのは40歳ぐらいから。早くはないです。でも、やっていればなんとかなる。だからこそ続けるのがとても大切だと思います。
私はこれからも、関わる人たちと対話を重ねながら、皆が安心して舞台をつくり上げていける現場づくりをもっと進めていきたいと思っています。一方で、一人でも多くの人たちに、お芝居の魅力を伝えていくにはどうしたらよいかも考え続けています。
今後やってみたい舞台は具体的にいくつかあります。例えば、日中戦争の時に戦場に送られた、芸人さん達による慰問団の話です。慰問は戦意高揚のためですが、そんな「お題目」をかいくぐり、芸人さん達が漫才を通して、自分達の言いたいことを言っていたことがあったそうです。そんな芸人さん達の「生き方」を描きたいですね。
私は善人ばかり出てくるお芝居が好きではなくて、人間の面白さやおかしさ、ちょっとマヌケなところを描きたいと思っています。そして観た人が、「自分もそうだな」「この人はこうだな」などいろいろ思う中で、そのお芝居のテーマにしていることを感じてくれればうれしいですね。
今は生成AIで絵も描けるし、動画までつくれてしまう時代です。「映像の俳優」はAIにもできてしまうでしょう。また舞台演出も、いろいろな情報をAIに学ばせれば、すごい演出をするかもしれません。でも、舞台俳優だけは絶対AIに置き換わらないと思います。ものすごく高性能なアンドロイドが出てきたら別でしょうが、目の前に実在する人間が出てきて何かをつくり上げるものとして、演劇が唯一の芸術になる可能性もあります。ぜひ、リアルな舞台のエネルギーを受けに、劇場に足を運んでみてください。
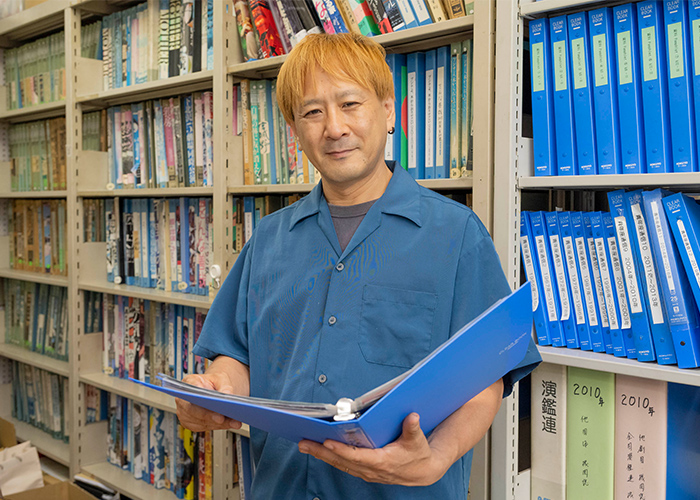 |
前編のインタビューから -役者やスタッフと対話し 作品を先導していく仕事 |
























