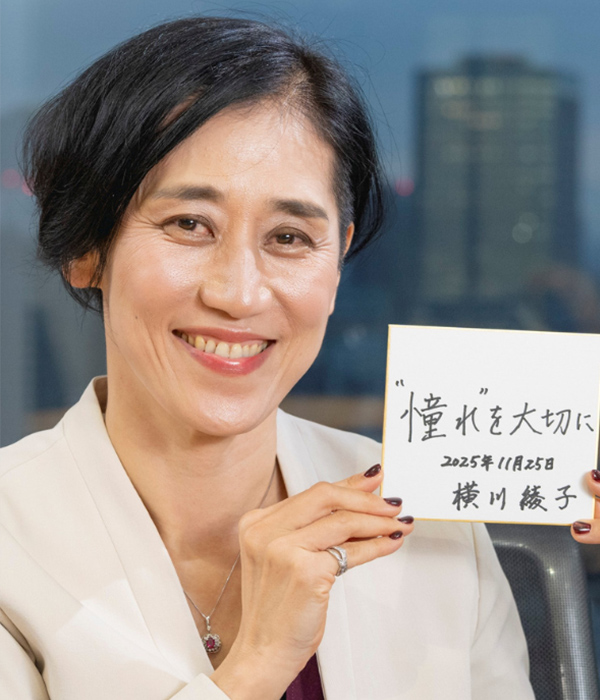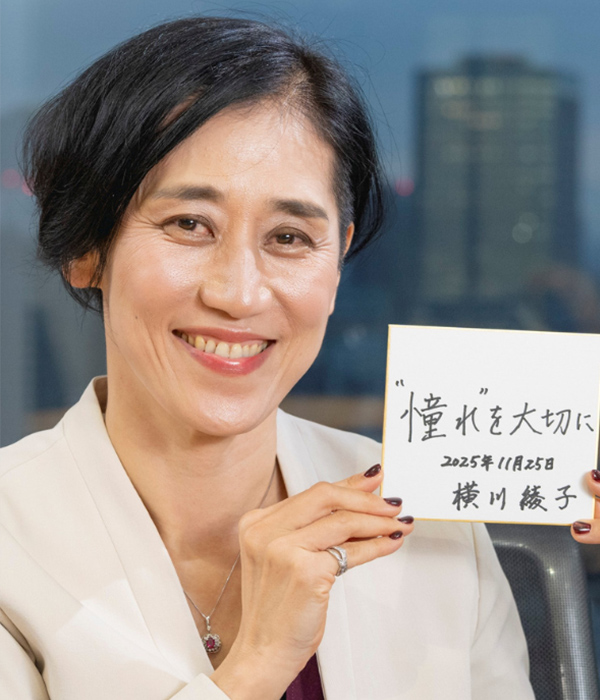役者やスタッフと対話し
作品を先導していく仕事
皆さんはお芝居を観たことはありますか。私は、最初はお笑い芸人になりたかったのですが、友人に連れられてお芝居を観に行って、夢中になりました。その後の紆余曲折を経て、現在はお芝居を演出する演出家として活動しています。
ひとつのお芝居には、役者はもちろん照明や音響など、いろいろな人が関わっています。皆、芝居の中で、それぞれ実現したいことや思いがあります。そうしたことをひとつの方向に調整して先導していく。それが演出家の仕事だと考えています。

演劇では「台本」のことを「戯曲」と言います。私は演出家として、劇作家に戯曲を書いてもらう段階から関わる場合もありますし、戯曲や役者、スタッフが揃ってから声がかかる場合もあります。いずれにしても、役者やスタッフと対話を重ね、関わっている人全体のエネルギーを上げる現場づくりを大切にしながら、ひとつの作品をつくり上げていきます。もちろん、相性の合わない人もいることもありますが、そんなときは逆に「面白いものができるかも?」と考えます。
集団でものをつくるというのは、一人でつくるよりもより強い表現力が生まれ、観客に訴えるエネルギーも高まります。私たちはそれを有名な童話になぞらえて、「大きなかぶ状態」と言っています。一人でかぶを引っ張るよりも、皆で引っ張るほうが、早くしっかり抜けますよね。皆でやると、自分が思っている以上のものが生まれてくるんです。その瞬間に立ち会えたときは「あぁ、この仕事をやっててよかったな」と、心が満たされます。
対話の中では、自分から意見を言えない人もいるので、発言できる環境づくりをしています。最初に「誰がしゃべってもいい。途中で意見が変わってもいいし、わからなくなってもいい。常に言わなくてもいい」と時間をかけて伝え、それを稽古場でも実践していくんです。これは「哲学対話」という対話のルールを参考にしていて、とくに「意見を否定しない」ことを大事にしています。
それでも現場がうまくいかないことは、やっぱりあります。そういうときは、その場で答えを出そうとすると詰まってしまうので、時間を置いたりします。すると流れが変わるんです。
広島を訪問以来
8月6日と9日に黙祷

この11月には、私が演出を担当したミュージカル『バウムクーヘンとヒロシマ』を広島市で上演します。今年は広島・長崎に原子爆弾が落とされてから80年。物語の舞台は広島なので、このような節目の年に広島で上演するのに意義ある作品だと思います。
原作はくもん出版が2020年6月に刊行した児童書『バウムクーヘンとヒロシマ』です。イッツフォーリーズという劇団がミュージカル化し、2023年に東京、2024年に岡山でも上演されました。
広島県には似島(にのしま)という島があります。第一次世界大戦中、この島には捕虜収容所があり、そこにはカール・ユーハイムというドイツ人の菓子職人が収容されていました。彼は1919年に広島県物産陳列館(現在の原爆ドーム)で開かれた、ドイツ人捕虜による作品展示即売会に参加。日本ではじめてバウムクーヘンを紹介し、大変好評を博したそうです。そんな実話から着想を得た、バウムクーヘンがつないだ平和の物語です。

私は似島にも行きました。広島港から船で20分ととても近い。戦中の歴史遺産が点在し、戦争とは切っても切り離せない島だと感じました。この島に2回行ったうち1回目は、当時12歳と6歳だった娘ふたりも連れていきました。彼女たちは小さい頃から、8月6日と9日の原爆が投下された時刻と15日の終戦記念日に黙祷するような子たちで、戦争の跡地を神妙な顔つきで見ていました。私は彼女たちに黙祷を強制したことはありませんが、私がするのをまねて習慣になったのかもしれません。
私が黙祷をするようになったのは2009年、原爆を題材とした舞台の演出のために広島に取材に行ったことがきっかけです。慰霊祭にも参加し、知人の案内で佐々木禎子さん(2歳で被爆、10年後に白血病を発病し、病床で千羽鶴を折り、回復を祈りながら亡くなった少女)が入院されていた病院など、通常の観光ルートでは立ち寄らない場所をたくさん回りました。
また、広島で演劇活動をしている人たちと話す機会もありました。その方々は、被ばくについて家族から聞いている話を聞かせてくれたんです。今でも被ばくの事実と向き合っている、ずっとそんな思いを抱えて生きているという話を、私と同い年くらいの人たちから聞きました。東京で会った時はそうした話はしませんが、その土地にいるからこそ話せることがあるのだと気づきました。
ニュースや本などではわからない、その土地に行かないと感じられないことがあると実感し、原爆や戦争について「忘れないようにすること」という意識が強くなりました。それ以来、私は“その日”に黙祷するようになりました。聞かされていることよりも、能動的に現場に調べに行ったほうが、深く知ることができると感じた出来事です。
「観て楽しむ」のが芝居
だからこそ心に残る作品を
私は「演劇は演劇のために役立てばいい」と思っています。もちろん「何かを伝える」ための演劇も否定はしませんし、結果的につくり手の思いは伝わってほしい。でも演劇は観て楽しむもの。作品として面白くなければ…との思いで、舞台をつくっています。
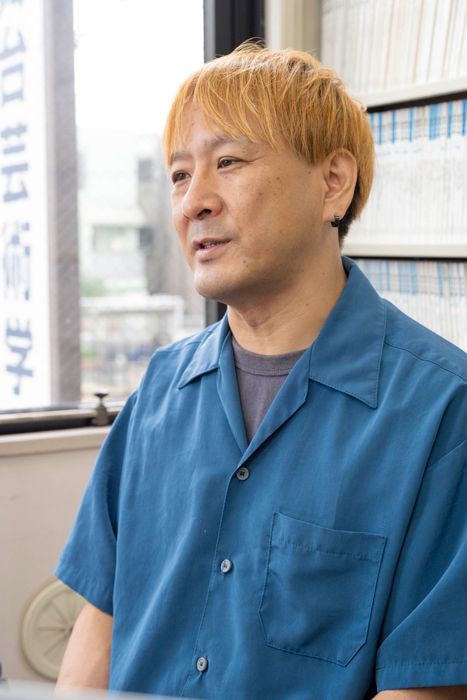
メッセージを主張しすぎると、引いてしまうお客さんもいると思うんです。お芝居を観て楽しんでほしい。その上で、「あれはどういうことなんだろう?」と気になって、そのことを自分で調べる「きっかけ」にしてくれればと思います。
とくに子どもは敏感です。例えば、戦争が「してはいけないこと」であることは皆知っている。それを「いけない」と言われれば、その瞬間は「そうだな」と思うでしょうが、それで終わっちゃう気がするんです。
でもお芝居が印象に残っていたら、そうしたことを日常で忘れそうなときに、「あ、そういえばあのお芝居でこんなこと言っていたな」と思い出すかもしれません。そうなれば、その子の生き方に一石を投じたことにはなるのかなと思います。そうして波紋が広がればうれしいですね。
私も戦争を体験しているわけではありません。しかし私が子どもの頃には、戦争を体験している大人が身近にいました。私の通った学校には零戦(ぜろせん)のパイロットだった用務員さんがいて、いろいろ話してくれた記憶があります。
先日は、初めて父に戦争のことについて聞きました。当時父は愛知県丹羽郡扶桑町に住んでいて、岐阜に陸軍の飛行場がありました。8月15日に夕陽の中、飛行場に向って飛んでいく戦闘機を見て、「負けたんだ」と思ったそうです。当時3歳の父の記憶にそれが残ったんですよね。父の表情から、当時のなんとも言えない雰囲気が伝わってきました。
今、戦争体験者はかなり少なくなってきています。資料や映像で残されているものを見ることもいいと思いますが、実際に戦争を体験した人から直接話を聞くと、その時の表情や雰囲気がダイレクトに伝わってきます。だからこそ、体験した人の言葉で紡いでいくことが大事なのでは、と思っています。
反戦を舞台上で表現するのも、演劇ができることではあります。しかし直接的に訴えるよりも、「戦争になるとこんなに悲しいことが起こる」という状況を舞台で描くことで、より説得力のある伝え方ができると思っています。
演劇はテーマだけが一人歩きするのではなく、全体を通して完成するものです。舞台が始まってから終わるまで、お客さんは登場人物と同じ時間を生きています。役者とお客さんと一緒に人生を生きる中で、その舞台のテーマが強く共有できればと思っています。
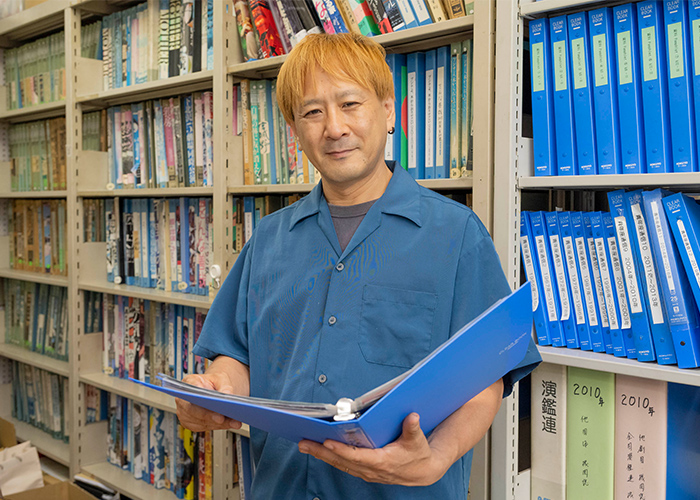 |
後編のインタビューから -お笑い芸人になりたかったが 「文化をつくる」演劇に魅了 |