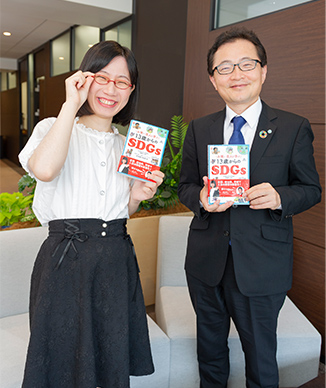脳科学者・京都大学教授
中村 克樹(なかむら かつき)
京都大学ヒト行動進化研究センター長・高次脳機能分野教授。京都大学大学院理学研究科修士課程修了後、国立精神・神経センター神経研究所モデル動物開発部部長などを歴任。著書に『人生100年時代の脳科学:元気に歩むために知っておきたい脳の50話』(くもん出版)ほか。
NMB48
水田 詩織(みずた しおり)
1998年生まれ。愛媛県出身。2016年にNMB48研究生として加入し、その後正規メンバーに昇格。ゴリラやサル愛を公言し、公益財団法人日本モンキーセンターのアンバサダーに就任。初の著書『サル好きアイドルが飼育員さんに聞いてみた』(くもん出版)を刊行。
「言葉」と「笑顔」は
人間ならではのもの
水田:サルはしゃべれませんが、例えばフクロテナガザルは、お互いギュッと寄り添っているので、私たちみたいに「愛」という思いをもっているのかなと感じますが、どうなんでしょうか。

中村:もちろん愛情はもっていると思います。でも喉の構造が人間とは違うので、言葉は絶対に操れません。ただサルの仲間同士でコミュニケーションを取ります。例えばベルベットモンキーは上から敵が来たのか、下から敵が来たのかを、鳴き分けてまわりの仲間に伝えています。
水田:鳴き分けられるのは、小さい時からそれを聞いていて覚えるということですか。
中村:そうです。仲間がそうやって鳴いているのを聞いて学習しているんです。コモンマーモセットも親が鳴いているのを聞いて育たないと、いつまでも赤ちゃん言葉みたいなままなんですよ。
水田:言葉について思うのは、私たちはそれを使えるし、それでコミュニケーションを取れているので大切にしていきたいということです。せっかく話せるのだから言い争いに使うのではなく、よいことに使いたい。そのことを、私はおサルさんから学びました。
中村:素晴らしいですね。サルは話せませんが、いろんな表情やジェスチャーをして、それが非常に強力なコミュニケーションの道具になります。
私が「やっぱり人ってすごいな」と思うのは、笑うことができること。サルは喜ぶことはできますが、人間の笑顔のようなものはないんです。水田さんが笑ったら私もつられて笑顔になるように、「笑顔の共有」はサルの世界ではありえません。でも人間は同じ感情を共有することができて、よりよい人間関係がつくれます。「言葉」も「笑顔」も人間に与えられたすごいコミュニケーションの道具なんです。
水田:おサルを見ていて「笑っているのかな」と思うことがあるんですが、あれは違うんですね。
中村:「イー」と歯を見せる行為ですね。あれは「グリン」といって、「私はあなたに刃向かうつもりはないです」という服従のサインです。ケンカを未然に防ぎます。多分人間は、それを進化させて「ほほえみ」ができるようになったのでしょう。

水田:私もこれから、もっといっぱい笑います!
中村:いいですね。水田さんも、うれしいときなど自然にほほえむと思いますが、つくり笑いをするときもありませんか。本当に笑うときと、つくり笑いをするときでは、神経支配が違っているんです。それくらい社会で生き残るためにはつくり笑いも大事だということで、脳のシステムが進化したのでしょう。
水田:ステージやファンの方と接するのは楽しいので、自然に笑顔になりますが、そうしたお話をうかがうと、つくり笑いも楽しんでできるような気がします。毛づくろいもすごくかわいい動作ですが、あれも愛情表現ですか?
中村:ひとつのコミュニケーションですね。人間でいうとマッサージに近いものですね。頻繁に毛づくろいしていて仲がいい場合もあるでしょうが、気に入られたくて毛づくろいすることもあるんですよ。
水田:サル社会にもそんなことがあるんですね。
中村:Aという個体がBに近づいたら、Bは必ず遠ざかっていくという関係もあります。コモンマーモセットは一夫一婦制のとても珍しいサルですが、研究所でお見合いさせると、絶対イヤみたいな態度を示すのもあれば、そうでない場合もあります。
水田:いったい何を見てそう感じているんでしょうね。
中村:そこまでは私もわかりませんが、間違いなく好き嫌いがあると思います。コモンマーモセットは子育ても面白くて、絶対赤ちゃんを渡さないという母ザルもいれば、授乳のときだけ仕方ないから引き受ける母ザルもいます。何が違うのかがわかれば、人間の子育てにも応用できるかもしれませんね。
サルもヒトも
「すぐほめる」が大事
水田:ボスザルはどう決まるんですか。
中村:全部が全部ではないですが、順位の高さが年功序列で決まる場合もあります。オスの場合は、最近はボスザルと言わずにアルファメールと言います。「強いサル」という意味です。オス同士どちらが強いかというのは、真ん中に餌を投げれば、一方が逃げてもう一方が食べるのでわかります。

昔風のボスザルの群れもあり、ボスのオスと、やや若いオスが勝負して入れ替わったりしますが、群れによって同じルールではないですね。例えば「サル」という形で小麦を撒くと、サルたちみんな寄ってきて、隣とぶつかり合うぐらい近づいてもケンカしない群れもいます。一方、知らないサルが入ってきたら、まるで「お前どこのもんじゃ」というかのように、威嚇するような群れもあります。
水田:群れによってだいぶ違うんですね。オスとメスでもいろいろありそうです。
中村:例えばサルの仲間のオスは大きい犬歯を持っていて、よくあくびをします。あれはただ眠いだけじゃなく、「俺はこんなでかい犬歯を持っていて、体がでかくて強いんだぞ」というのをアピールしてメスに選んでもらうためです。オスが近づいてもメスが嫌がることもしばしばあります。言い方は悪いですが交尾して失敗したときのロスが大きいので、メスはできるだけ強くて健康そうなオスを選びます。
水田:オスよりメスのほうが強い立場…人間の夫婦も奥さんのほうが強いイメージがあります。
中村:そうかもしれませんね。サルも人間も、間違いなく長生きするのはメスなんです。
水田:サルは相手に好かれたいと意識して行動することはあるのでしょうか?
中村:「ナンバーワンに好かれたい」という行動をとる場合があります。例えばこの研究所でも、ある人とチンパンジーが1対1でいると良好な関係だったのに、そこに親分(人)がやってきたら、豹変して良好な関係だった人に攻撃し始めます。その親分に好かれたいという行動をとるんですよ。
水田:それって人間でもありますよね。そのほかに、人に似ているところはありますか?
中村:自分が「かなわない」と思った相手には従順になることがあり、我々はそれを利用します。例えばほかの人からは一切餌を与えないようにして、私からだけ与えると、「この人は大事な人」つまり親分のようになるので、逆らわなくなります。
研究のためにサルにボタンを押してもらうためには、うまく誘導することが必要ですが、こちらの思い通りにならないときに叩いてしつけては逆効果となります。安定して何かに導くには、叱る、怒るではなく、ほめることが大切。人も同じですよね。そしてこれは脳の仕組みですが、ほめるのも叱るのも、直後にすることが大事です。日本の学校はテストをしたら、答案の返却までに時間がかかりますが、公文式はできたら直後にほめますよね。これはすごく大切で、そうしないと脳が学習しないんです。サルにもできたらすぐにごほうびをあげます。基礎的なことはサルで研究できるんです。

水田:私も後輩をすぐほめるようにします!
中村:ぜひ、そうしてください。例えば電車に乗っていて子どもが騒いでいたら、親は「静かにしなさい」と叱ることはあっても、「今日は静かに乗ってたね」とほめることはあまりないですよね。いいことをしたらすぐほめてあげてくださいね。
しんどいときこそ
おサルに会いにいってみよう!

水田:私は動物園では飼育員さんとサルとの関わりをよく見るようにしています。飼育員さんはサルのことを生き物として対等に接しているなと感じていて、そういうところにも目を向けると、動物園がより楽しくなると思います。先生は、動物園などでサルを観察するときのポイントは何だと思われますか。
中村:日本モンキーセンターのようなところで、ほんの数頭しかいないサルを見て「変わった顔形をしているサルもいるんだな」と思うのはもちろんいいと思いますし、頭数がいる動物園に行くのなら、ご飯の時間に見に行くのがお勧めです。いろんな動きが観察できるからです。
チンパンジーなら多摩動物公園、ゴリラなら上野動物園に頭数が多く、群れを見ることができます。群れだといろんなことが起こるし、エサをもらえるときのほうが「あいつとあいつがけんかして、あっちの方が強いんだ」ということも見えてきます。
水田:時間によってサルの行動が違いますよね。だからこそ、時間を変えて通いまくっています。裏の部屋に帰った時間帯を狙って行くこともあります。裏の部屋だとガラス1枚だけでよく観察しやすかったりするんです。
中村:本当によくご存じですね! 水田さんは、いろんな意味でサルという動物がどんな動物かを広めてくれています。「人間ってこうだよね」と考えることにつながるチャンスを広めてもらっていると思うので、非常にありがたいです。
私は最近、自分の未来を描けずに絶望する人がいることが気がかりなのですが、絶望するのは人間だけなんです。過去があって現在があって未来があることをわかっているからで、これも脳が段違いのレベルで進化した結果です。脳の進化によるマイナス面ですが、別の考え方があるよと伝えていけたらと思います。

水田:私もおサルさんに出会う前は悩みがちでした。でも、おサルを見ていて「自由に生きてもいいんじゃないかな」と気づいて、変わりました。
中村:そうだったんですね。おっしゃるように、その時々は自分にとって重大な問題でも、一歩二歩引いてみれば、「それほどたいしたことはないな」と受け止められる。そんなふうに考えられるようになればいいなと思います。
水田:悩みがちな人に、おサルさんの世界を知ってもらったら、絶望することも減ってくるというか、考えが改まることがあるんじゃないかなと思います。
中村:そうですね。例えばゴリラをじっと眺めていたら、「こいつは何考えてんのやろな」と思ったりしますよね。そうしていると、日頃追い詰められている自分から解放される時間がもてますよね。
水田:本当にそう思います。悩んだり「なんかうまくいかないな」と感じたりするときがあったら、ぜひおサルを見に行ってほしいです! 今日は本当にありがとうございました。

<対談を終えて 感想>
水田:脳科学者である先生との対談なので、難しいお話になるのかなと、少しドキドキしていましたが、とてもわかりやすくお話ししてくださって安心しました。私はおサルのことなど、いろいろ考えることがあるのですが、自分だけが考えているわけではないと知り、うれしかったです。おサルさんの新たな魅力をたくさん知ることもできて楽しかったです!
中村:サル好きという、そんな変わったアイドルの方がいるなんてと最初は不思議でしたが、サル愛がすごく伝わってきました。サルの名前もすっと出てきますし、知識も豊富。「そんなところまで観察しているんだ!」と、とても感心するコメントがいくつもあって驚きました。
やっぱり「好き」が大切ですね。教育に携わっている立場としては、一生懸命「教える」のではなくて、覚えてほしい対象を「好き」になってもらうことが一番大切。ですが、それが一番難しいんです。その意味でも大事なことを教えていただきました。水田さんには、これからもどんどんサルについて発信していっていただきたいと思います。
 |
前編のインタビューから -サルを知ると ヒトのことが見えてくる! |