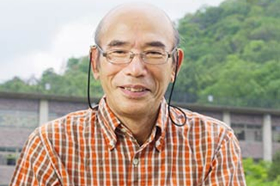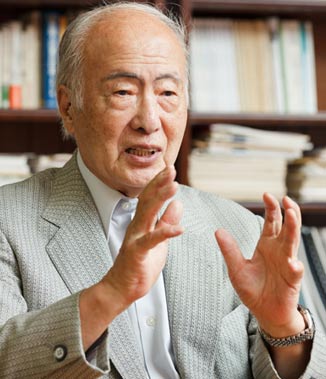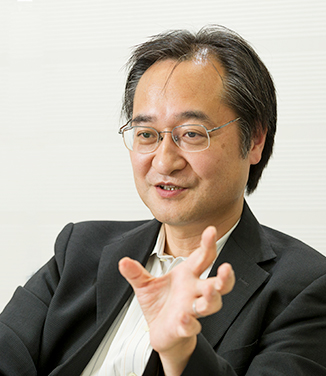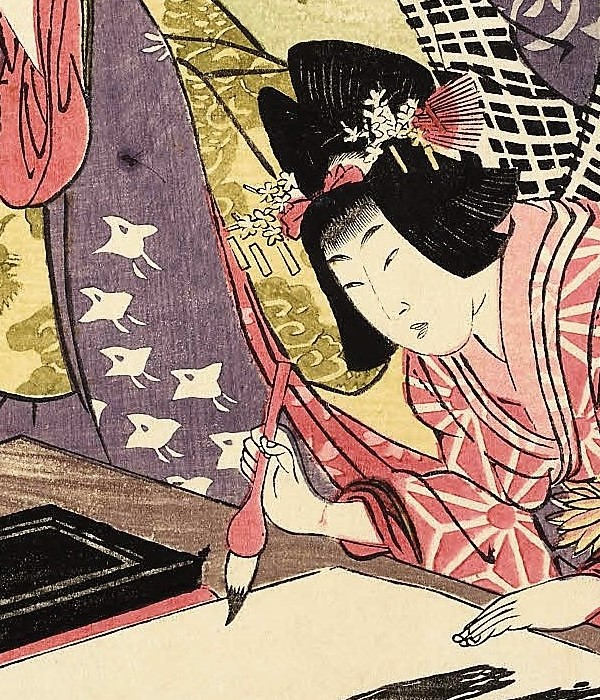子どもが「勉強がむずかしい」と思うのはなぜ?

私は教育心理学が専門ですが、いま特に関心を寄せていることが3つあります。1つは、学びに困難をかかえる子をどう支援すればよいかということ。なぜ子どもが理解できないのか、それを問うと、学校など教育現場の教師は「その問題がむずかしいから」と言います。たしかにそうなのですが、では、「なぜその子にとってむずかしいのか」。こう問うと、答えられないことが多いのです。つまり、「なぜむずかしいのか」の理由がわからずに授業をしていることになります。私はその原因をはっきりさせれば、学ぶことが楽しいと感じる子がもっと増えると考えています(後編で紹介)。
2つめは、学習活動による高齢者の認知機能の維持と改善の研究です。人間の発達からすると、高齢になると認知機能は低下する一方とされていますが、われわれの研究では、音読や算数などの学習課題を毎日すると、認知機能は維持されるどころか、むしろ改善するとの結果が出ました。このことから「脳の機能は環境によって変化するのではないか」と考え、検証しているところです。
3つめは、発達障害の子どもたちへの支援です。特に自閉症の子は、諸説ありますが、脳機能の発達不全だと言われています。とすれば、脳機能を改善すれば、自閉症特有の問題行動は少なくなり、社会に適応できるようになるかもしれないと考えています。これは学部生の卒業論文として指導しながら研究を続けていますが、1~2ヵ月関わりを続けるだけでも、脳機能などが改善するという驚くべき結果がでています。ただし、現状では対象となる子どもたちの数が少ないので、もっと研究を進めていく必要性を感じています。
勉強とはまるで無縁、伸び伸び過ごした子ども時代

私は熊本県の田舎町で育ち、勉強とはおよそ無縁の子ども時代でした。小学校入学時は自分の名前も書けなかったのではないか、と記憶しています。休み時間には学校のそばの川で魚採りに夢中になって授業に戻らず、担任の先生が探しにきてくれたこともありました。いま考えると、なんとものんびりした時代でした。
当時はテレビもなく、ラジオから流れてくる外国からの特派員レポートを聴くのが楽しみで、大人になったら特派員になりたいなんて思っていましたね。とはいえ、それに向けて勉強していたわけでもなく、中学も高校も地元の公立校へ進みました。
私の父は早くに亡くなり、教師だった母が姉と私を育ててくれました。母から「勉強をしなさい」と言われたことはありませんでした。それでも、子ども用の本がなかなか買えない時代にあって、月刊の学習雑誌や本はよく買ってくれました。学校の図書室にもよく通い、偉人伝やシャーロック・ホームズなどの推理小説をよく読んでいました。
そんなのんびりとした生活だったせいか、高校受験を控えた中学3年生の夏、英語がほとんどわからないことに気づき、このときはさすがに焦って、1年生のころからの教科書を取り出してすべてやりなおしました。塾なんてない時代ですから、自分で工夫してやるしかない。やり方には問題があったかもしれませんが、懸命にやったのがよかったようで、なんとか英語がわかるようになりました。そうして高校に入ると、英単語の試験で1番になり、英語の先生から「もう英語の勉強はいいから他の教科を勉強しなさい」と言われたほどです。努力が報われた思いで、とてもうれしかったですね。
大学は、人への関心があったので、人と関われそうな教育学部に進学することにしました。教師だった母の影響を無意識に受けていたのかもしれませんが、教師になるつもりはなく、大学卒業後は漠然と公務員になろうかと考えていました。父が早くに亡くなったので、安定した職業に就いて、母に楽をさせたいという気持ちもあったのかなとも思います。
国家公務員上級職の試験には、心理学の科目があります。そのため、大学2年からは心理学の講義をまじめに受けるようになりました。そうすると、心理学の面白さのとりこになり、大学3年になると心理学の自主的な研究会をつくり、そこでの研究活動に没頭するようになりました。
この研究会でとても印象に残っている出来事があります。そこでは学部生はもちろん、大学院生も発表するのですが、ある院生の発表に対し、当時学部の3年だった私が生意気にも意見してしまいました。「社会心理学の原理からすると、理論的に全く違う仮説ができるのではないでしょうか」と。否定や反論を覚悟しての意見でしたが、意外にもその院生は「なるほど。そうなると2種類の仮説ができて研究の幅がさらに広がるね」と、笑みまで浮かべて喜んでくれたのです。これは研究を続けるうえで、大きな励みになりました。
家庭裁判所の調査官時代、心理学の原理に当てはまる少年に出会う
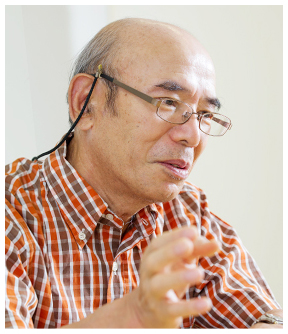
大学4年のとき、家庭裁判所(以下「家裁」)調査官の試験を受けて合格。卒業後は家裁に勤めることになりました。そこでの私の仕事は、例えば家裁に事件送致されてきた少年本人や保護者や家族などを対象に、少年が非行に至った動機・成育歴・生活環境などを調査し、どんな処分が適切かを判断するための基礎資料を作ることでした。
1ヵ月間に何十ケースも受け持ちますし、非行にからむ調査ということもあり、時間的にも内容的にも、なかなか大変な仕事でした。どうしてこんなことが起こるのかと悲嘆に暮れたり、暗澹たる思いになったりもしました。そのなかで、学生時代に学んだ心理学の原理にピタッと当てはまる少年に出会いました。じつは、この出会いが私を再び心理学の研究の道へと引き寄せたのです。
その少年は窃盗をくり返しており、母親と警察や裁判所に行くこともたびたびでした。調査のために何回かその子と話していると、あることが見えてきました。「窃盗をすると、母親が自分に注意を向け、寄り添ってくれる」。それが、少年にとっての「ご褒美」になっているようなのです。これは心理学でいう「部分強化効果」ではないかと思い当りました。
部分強化効果とは、わかりやすく言えば、「ある行動に毎回、ご褒美を与えるよりも、たまに与えたほうが、何度もその行動を続けるようになる」ということです。この少年の場合、窃盗をすると母親が自分に寄り添ってくれるので、母親の注意を引きたいがために、何回も窃盗をくり返してしまうという、やりきれない悲しさを感じるケースでした。
この少年のケースはとても印象的で、いまでもよく憶えています。この少年との出会いがきっかけとなり、学生時代に読んだ心理学者ハンス・アイゼンクの著書『犯罪とパーソナリティ』を思い出し、心理学をもう一度研究したくなりました。実際に少年が起こした非行を心理学で理論的に説明できるのなら、心理学でそういう少年の心の内を解き明かし、非行を防いだりできないものか、なにかサポートできないものかと考えたわけです。そして大学院を受験することにしました。
調査官として勤めていたのは2年間でしたが、ここで担当した何百という案件を調査した経験が、これまでの、そしていまの私の研究に影響を与えているのはたしかです。少年たちに話を聞いて調査をしても、なかなか真実は見えてきません。だからこそ、調査や審判は慎重にあるべきだと思いますし、単なる調査に終わらず、目の前の一人ひとりに、どうすればどんな支援ができるかを考えることが必要だと学びました。現在の研究でも、「目の前の一人ひとり」を意識して、どうプラスの方向へと変えていくかを考えるのを大切にしています。
 | 後編のインタビューから – 子どもたちを勉強ぎらいにさせないために、吉田先生が考えていること |