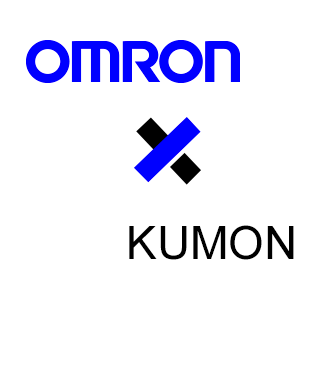|
| 日本航空株式会社 運航本部 787運航乗員部 副操縦士 櫻井聡史さん |
―― パイロットというお仕事についてきかせてください。
私は今、ボーイング787型機の副操縦士として国際線乗務に携わっています。パイロットの仕事は飛行機の操縦だけでなく、安全で質の高い運航のために他にもさまざまな業務があります。
まず飛行機が出発する前には、飛行ルートや高度、そして機体に搭載する燃料の量などの「フライトプラン」を作成する運航管理者とともに、その日の気象条件などを確認しながら、フライトについての打ち合わせを行います。
そして飛行機に移動した後は、乗務する機体の整備状況の確認を整備士と行い、機内では客室乗務員と、搭乗されるお客様の情報や飛行航路における揺れの予測状況などについて共有します。
この後ようやく操縦室での業務が始まります。コックピットでは機長と副操縦士の二人体制で操縦にあたります。一人のパイロットが一連の操縦を主に担当し、もう一人はその操縦が正しいかをモニターする役割と、航空管制官との無線でのやりとり、また機器へのデータ入力やルート入力などを行います。
飛行機の操縦は、地上滑走→離陸→上昇→巡航→降下→着陸という流れになりますが、巡航中であっても快適で効率のよいフライトになるように、最新の気象情報をもとに最適な高度を考え続けています。
着陸したあとは、地上スタッフとフライトについての振り返りを行い、ようやく任務完了となります。パイロットの業務は、実際の操縦はもちろんですが、じつは「8割が準備で決まる」と言われています。
 |
| JALボーイング787型機 |
―― どのようにしてパイロットになられたのでしょうか?
パイロットというと工学系の出身だとイメージされやすいのですが、私の場合、大学と大学院では発展途上国の農業開発に関する研究をしていました。日本航空の自社養成パイロットは理系文系を問わず受検することができます。私は就職活動のときにこの制度を知り、幼いころに漠然と憧れていたこの仕事を目指すことにしました。
とはいえ素人がパイロットになるのですから、それまでには長い道のりがあります。
私の場合は2005年に入社して、まず1年間、新千歳空港で地上業務の研修を行いました。その後、約半年間勉強漬けとなり、操縦士の国家試験を取るための座学を行いました。
学科試験に合格したら、今度はアメリカに研修の場所を移して、小型機に乗務しての操縦訓練が始まります。まずは単発プロペラ機1年。次に双発プロペラ機、さらに計器飛行の訓練をして、ようやく日本に帰国します。
このあといよいよ大型機での訓練が始まります。まずはシミュレーター訓練と実際の飛行機の操縦を繰り返し、飛行機の型式限定での運航免許が取得できます。その後は実際にお客さまが搭乗された飛行機での乗務訓練を重ねてようやく副操縦士になれます。私の場合はここまでに5年かかりました。
―― パイロットになるまでにはたくさんの積み重ねが必要なのですね。
訓練に入ってからは毎週の小テストに加えて、節目には「チェック」と言われる試験が行われるのですが、もしそのチェックに二度不合格になると、パイロットへの道は閉ざされる、というとても厳しい面があります。
パイロットになるための訓練やテストは厳しいものですが、同じ目標をもって過ごしてきた同僚たちとの連帯感には支えられました。当社のパイロット養成制度は、一つひとつの訓練をクリアすることができれば必ず資格がとれる絶対評価です。入学試験のように、誰かが受かれば誰かが落ちる相対評価ではないので、仲間同士で助け合いながら頑張れる。お互いが切磋琢磨できることは大きな原動力になりましたね。

―― パイロットの仕事のやりがいや魅力はどのようなところですか?
航空機のパイロットの資格は、毎年更新試験を受けなければなりません。シミュレーターと実機での技能審査や航空身体検査が義務づけられているのです。国際線に乗務するためには航空英語能力証明の取得も必要ですし、パイロットでありつづけるためには、学びと体力の維持向上に日々努めなければいけません。
ただそうした厳しい中でも、大きな喜びがあります。国際線を飛んでいると、180度以上視界が開けたコックピットの窓からは、「地球の表情」の素晴らしさを目のあたりにできます。たとえば、アラスカ上空では壮大な自然や景色が広がります。シベリア上空では夜間のオーロラに遭遇することがあります。こうした経験ができるのは、パイロットならではですね。
飛行機が飛んでいるのは自然の中ですから、たとえ同じ運航ルートだとしても、気象条件などで一つとして同じフライトはありません。ですから、それをやり遂げたときには大きな達成感があります。飛行機を降りたお客さまが、ボーディングブリッジからコックピットに向かって手を振っていただけることがあるのですが、そういう姿を見られると「いい仕事をしたな」と思えます。一つひとつの乗務ごとに達成感があるというのは、パイロットの仕事の醍醐味だと思います。
―― パイロットに憧れる子どもたちへのメッセージをお願いします。
パイロットになるためには、学力や体力はもちろん、人とのコミュニケーション能力など、バランスよくいろいろな力を身につける必要があります。旅客機というのは、運航管理者や整備士など、たくさんの人たちが関わることで初めて飛ばせるので、パイロットはさまざまな人に耳を傾けて情報を集めて、ときには決断する力も必要となります。
私はサッカー部でしたが、サッカーを通じたチームプレー、また最後まであきらめないガッツはとても大切な素養になりました。パイロットは命を預かっている仕事ですし、どんなに困難な状況に追い込まれても、必ず安全に目的地まで送り届ける使命がありますから。
また、私は公文式で年長から小学校高学年まで学びましたが、そのときの経験はパイロットになるまでの過程に通じるものがあるかもしれません。目の前の課題をこつこつと真剣にやっていくと、次のステップへ進め、知らぬ間に実力と自信がついています。それは、将来必ず自分を助ける道具になります。子どもたちには、そうした道具をたくさん持ってほしいと思います。

関連リンク
日本航空株式会社