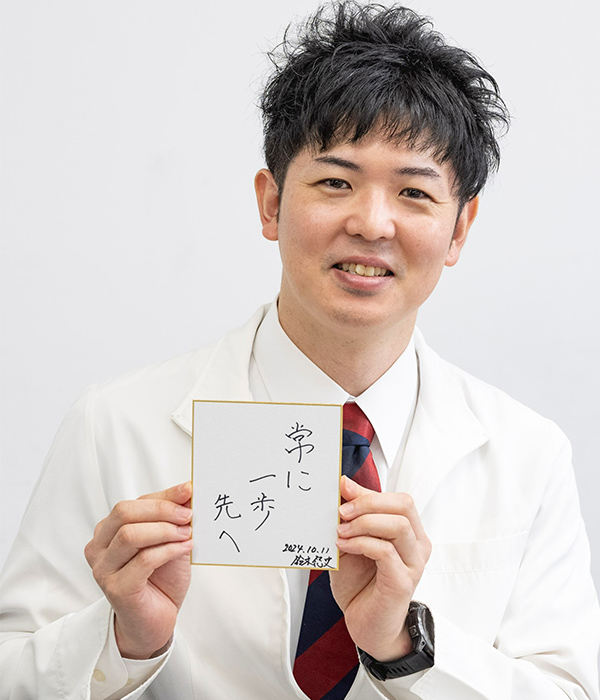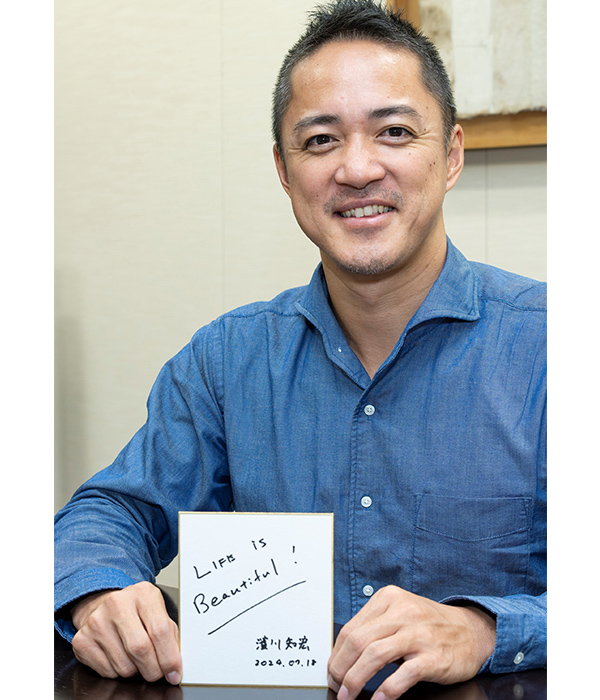27歳で大学受験に挑戦
仲間に支えられて合格

「よく卒業できたな」と思うほど高校では成績が悪かったことと、大学進学という周りの期待に反発していた私は、ほぼ全員が大学へ進む進学校にいましたが、卒業後は大学には進まず、すぐに働くことにしました。
そして時が経ち、3人の子育て中だった26歳のとき、最愛の父にがんが見つかりました。父はがん発覚後わずか数か月で亡くなったのですが、入院中は看護師さんたちをとても信頼していて、よく「ありがたい」と言っていました。看護師さんは薬剤によって安心させるのではなく、症状の変化で予測を立てて、父を安心させてくれていたのです。この体験から、「私もそういうことができれば、人が病気になるもっと前から役に立てるかもしれない」と考え、看護師になることを父に誓いました。
島根県立大学短期大学部看護学科(当時)を目指し、父の初七日の前には大学センター試験の過去問に取りかかりました。1年目は赤本(大学入試の過去問集)を使って独学で猛勉強しましたが、合格点の半分も点数が取れず不合格でした。そこで2年目は、「自分に合わせた適切なやり方、自分を高い集中状態にもっていける声掛けや適切なテキストをセットアップをしてくれるバディとアシストがあれば私はできるんだ」とKUMONの経験から考えた私は、予備校へ通うことにしました。
予備校では講師の方へ、「私のレベルに合わせてテキストを提示して欲しい」とリクエストしました。それを地道にくり返しやっていけば学力が伸びることはKUMONで体験していたので「やればできる」と思ったのです。しかし予備校に入るには数十万円が必要です。その費用を稼ぐため、私は託児所付きのセールスレディになり、昼は労働、夜は家族に子どもを見てもらって通学しました。そんな生活を1年続けた結果、27歳で大学に合格することができました。

合格へのアシストという意味では、予備校に通っていた10歳くらい年下の仲間の支えも大きかったです。ある子が学習している私のノートを見て、「これは勉強になっていない。こんなんじゃ合格できないよ」と諭してくれた上、周囲にも声をかけてくれ、皆が効果的な学習方法を教えてくれました。せっかく講師の方が私に合うテキストを選んでくれていたのに、その使い方が正しくなかったんですね。中学・高校とまともに勉強していなかったので、学習の仕方がわかっていなかったんです。いい素材があっても、使い方が悪ければ役に立たないことを学びました。
そして同時に予備校で学んだのは、仲間の大切さです。仲間と一緒に勉強したことで、私は成績がすごく伸びたのですが、仲間たちは私の志望校合格を私以上に喜んでくれました。こうした「チーム学習」は、今実施しているコミュニティナース講座においても応用しています。
予備校の時もセールスレディ時代も現在も、とにかく「素の自分を出す」と応援してくれる人が出てきてくれるのは、本当にありがたいことです。「できない自分」を出すのは、普通は怖いことですが、私は怖くありませんでした。それは子ども時代に、ありのままの自分を受け止めてくれていた、くもんの先生のような人との出会いがあったからです。
「お題」を解くのは楽しい
「批判」はヒントの宝庫

大学の看護学科に入学して知ったのが、「コミュニティナーシング」という考え方です。父が亡くなった時の体験から、「病気になる前から、普段の暮らしに溶け込む看護師」の必要性を感じていた私は、この考え方にひかれました。
しかし当時の日本では前例がなかったため、まずは仲間と5人で「コミュニティナース」を名乗り、手探りで活動を開始。カフェで子育て世代に向けたイベントをしたりするうちに、少しずつ知られるようになりました。そして2017年には、仲間を育て、普及支援を加速させるために、「コミュニティナースカンパニー」という会社を設立します。
「コミュニティナース」になるために看護師の資格は必須ではありませんが、その考え方を広めるために育成講座を設けたのです。この講座を修了してコミュニティナースとして活動している人は、現在全国で1,400人を超えており、地域の公民館やガソリンスタンドなど、様々な場で活躍しています。
人からよく、「壁」はなかったのか?と聞かれます。コミュニティナースの事業開始時は「どうやって稼ぐの?」「業界から何か言われたらどうするの?」など、いろんな声がありました。これを壁と捉える人もいるかもしれませんが、私にはその感覚はありません。あったのは、KUMONで身についた「お題」という考え方。「課題」と言い換えてもよいですが、「お題は自分のペースでやれば解決できる」という感覚です。ですからそんな声も、私にとっては「そうか、現状ではそういう声があるんだ」という現状認識でしかありませんでした。壁や挫折は、私にとってはお題であり、「ではどう解いていくか」と考える。それが面白いんです。そう考えるのも、お題を解いていくのが楽しかったKUMONでの体験があったからでしょう。
そして一人ではなく、仲間と知恵を出し合ってお題を解いていくのが、また楽しい。会社や社団法人の設立は、お題を解き続ける手段なんです。他人からの批判はヒントになるので耳を傾けますが、非難や文句は気にしていません。壁や挫折だと捉えると苦しくて、自分を疲れさせてしまいますが、私はそう解釈しないので疲労度は低い。この「解釈の仕方」が私の元気の素かもしれません。
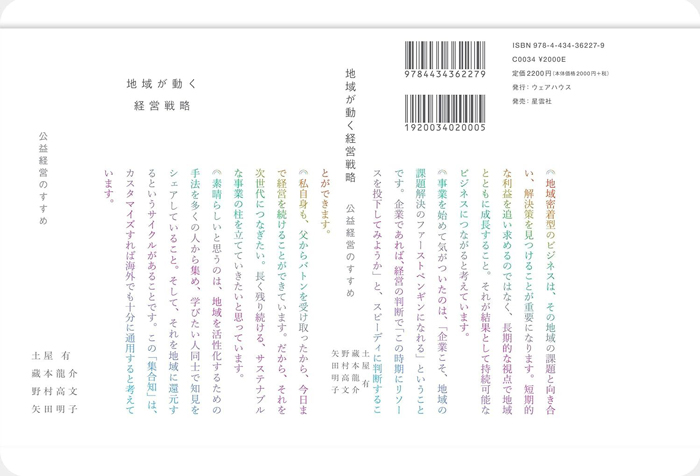
地域が動く地域戦略 公益経営のすすめ
もちろん難しいお題もあります。例えば、私たちが抱える大きなお題は「どうやったら人は相互の関わり合いの中で元気で幸せに生きていけるのか」というお題です。多くの人が自分に合った活躍ができて、健康が増進され、地域の文化的な営みも継承され、地域のリソースを皆で使って分かち合える事業を支えていく… そういうお題を解いていくために、最初は公的な立場である自治体の方々とパートナーを組み展開してきました。
しかし、実際に自治体と活動をしていく中では、次々と新たなお題が出てきました。そんなお題を解決していく中で、自然と民間企業との協業がメインとなってきて、現在は業績も上向きです。うまく進んでこれたのは、今までの活動からいろんな方とのパイプができていたおかげです。とくに、地域に根付いた企業のトップの方々は、私たちの考え方にとても共感してくれています。そのような企業は地域に活力があること自体が企業の存在価値だと考えているので、CSR(企業の社会的責任)活動としてではなく、予算をつけた事業活動として実践してくれています。
大人が成長する姿から
子どもは自然に育っていく

保護者の方は子どもと関わる際に、子どもを「育てよう」と思うのではなく、自分が「育つ」ことを意識するといいと思います。自身が成長していこうとする姿の横に子どもを置けば、子どもは自然に育ちます。これは私自身が地域コミュニティから教えてもらったことです。
私も若者たちを「育ててあげよう」とはしていませんし、私自身も今なお「育とう」としています。思えばくもんの先生もそういうスタンスでしたね。大人がどうあろうとしているかが、子どもの成長に影響すると思うので、そういうパートナーシップが子どもとできているとステキだなと思います。
私には5人の子がいますが、上の3人が物心ついたときに私は大学生だったので、彼らには毎日大学の課題に取り組んでいる母しか記憶にないようです。私は「勉強しなさい」の代わりに「私は最近こういうことに興味もっているんだけど、君たちは何に興味をもっているの?」とよく聞きます。その3人は現在大学生となり、それぞれの関心分野にまい進中です。彼らの話を聞くと私も刺激を受け、成長させてもらっていると感じます。
KUMONや勉強が「めんどくさい」と感じる子もいるでしょうが、「めんどくさい」は、本当は面白いことなんですよ。「めんどくさい」で思考停止するのではなく、「なぜ自分はこれをめんどうと思うのか」「なぜこれをやりたくないのか」に意識が向くと、自分が何を好きで何を嫌いなのか、自分を発見する時間になって面白くなります。「生きていく」ということはその繰り返しであり、人生そのもの。ですから、「めんどくさい」時間を大切にしてほしいですね。
私が皆といっしょにできたらいいなと思っているのは、公文式の考えでできたコミュニティナースの育成プログラムや教室をつくることです。単に学習をするだけでなく、「人間社会において人間同士がどう付き合うか」が学べる場として機能すると面白いなと思っています。

地域コミュニティが密であれば、そこで人間同士の付き合い方を学ぶことができますが、今はそのような機会が少なくなってきています。そんな地域コミュニティの中で、KUMONは子どもたちにとって身近な存在ですし、くもんの先生は、私たちが取り組んでいるコミュニティナースとの親和性がとても高いように思います。すでに「子どもと先生」という関係性ができているので自然な形で「戦略的なおせっかい」が始められるのではないでしょうか。
普通の家庭の普通の子どもたちが、こうした「おせっかいを受ける」という経験をすることが大事だと思っています。KUMONには「おせっかいを受けている」子どもたちがたくさんいる。おせっかいを受けた子どもたちは、自然とおせっかいをする側にもなれます。そして、そういう子どもたちとつながっていることが大きな価値ですね。10年くらいかけて、子どもたちの代にコミュニティナースのことをまんべんなく広げたいですね。いずれKUMONで、国、数、英、コミナス(コミュニティナース)というカリキュラムが用意できたら、こんなにうれしいことはありません(笑)。
 |
前編のインタビューから -相互扶助を戦略的につくり 「地域に育まれた」体験を |