「百ます計算」で子どもたちが
“手がつけられない賢さ”に
公文教育研究会 田中(以下、田中):本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、隂山先生は「百ます計算」の実践など、一貫して「基礎学力」の大切さをうたわれています。まず、その原点や背景について教えてください。

隂山英男先生(以下、隂山):実は私は、教師になろうと思って教師になったのではないんです。教育学部出身でもなく、コンプレックスをもったまま教師になり、せめて子どもたちの学力をきちんと伸ばしてあげる教師になりたいと思ったんです。
しかし現場は甘くない。教師になって4~5年目の頃、勉強ができずに表情が固まり思考停止してしまう子がいました。「この子を伸ばしたら教師として本物かも」と闘志を燃やし、夏休み前に「一緒に勉強しよう」と声をかけて、翌日学校で待っていたり、次の日は自宅まで行って学校に連れ出して学習させたり、ラジオ体操の帰りに捕まえて学校に連れて行ったりと、思いつく限りの方法を試したのですが、何の成果も得られませんでした。
田中:熱血教師ですね。一教師としてできる限りのことはされた。
隂山:はい。努力の虚しさを思い知りました。もっというと、その子が学んだのは「勉強と先生から逃げること」でした。その子が6年生の時に再び担任になり、同じ失敗はできないと悩んでいると、同僚が「岸本裕史※というすごい先生がいる」と教えてくれました。
※岸本裕史(きしもと ひろし、1930-2006)/日本の小学校教師。1985年に「学力の基礎を鍛え落ちこぼれをなくす研究会(落ち研)」(現「学力の基礎をきたえどの子も伸ばす研究会」)を結成。隂山先生は1987年に岸本先生と出会う。
それで岸本先生の研究会に出かけ、百ます計算に出会ったんです。驚きましたね。計算のタイムを教師が計っているなんて批判されるに決まっています。でも明らかに効果があると知り、小学校で1年間やってみました。
すると、子どもに「やってみよう」といった感情が出てきて、鉛筆が動くようになったんです。それが百ます計算にのめり込むきっかけでした。岸本先生が主張しておられた漢字の学習や音読にも取り組みました。
兵庫県朝来町立(現:朝来市立)の山口小学校勤務時代に隂山メソッドが完成していくのですが、そこで4年連続担任した子どもたちの学力がものすごい勢いで伸び、最終的には“手がつけられない賢さ”になりました。私がこれ以上難しい問題をつくれないというところまでいってしまった。難問も解くんですよ。
田中:子どもが自分から賢くなっていくわけですね。好奇心が刺激されたのでしょう。
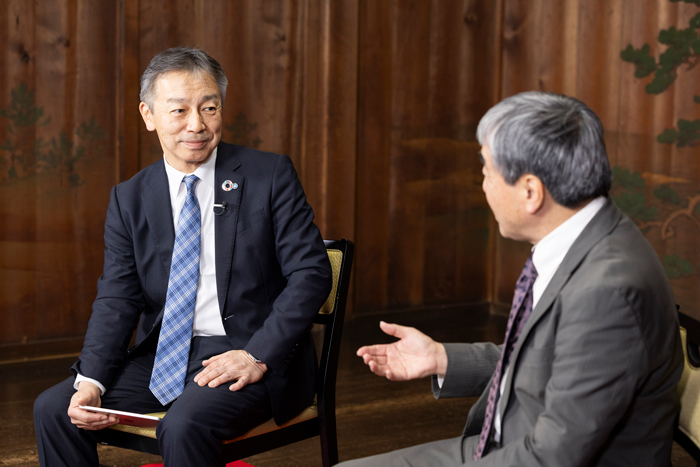
隂山:はい。私は、子どもは勉強から逃げるものとイメージしていましたが、そうではないと子どもたちが教えてくれました。基礎学力というのが、子どもの中にある「潜在的な可能性」を引き出して、見たこともない能力、手のつけられない賢さに至るんだと思い知りました。しかもそこでやっていたのは、公文式でも扱う基本的な計算です。小難しいことではありません。
その子に合う「ちょうど」の教材と
「ちょっとやっただけですごく伸びた」体験が大事
田中:今の隂山先生のお話をうかがっていると、それがそのまま公文式にも当てはまるように感じています。公文式の創始者、公文公(くもん とおる)は高校の数学教師でした。現在の公文式学習が誕生するきっかけになったのは長男の毅さんが小学2年生の時に、彼のポケットから出てきたテストの点数がたまたま芳しくなかったことから始まっています。

ドリルをさせるなどいろいろ試したものの長く続かず、もっと計画的に、高校の数学につながるものだけを幹として必要最小限で続けられる、毅さんにとっての「ちょうど」の自習教材を自作しました。その子に合わせた教材制作の始まりでした。子どもにはもちろん波がありますし、うまくいかないこともあったと思います。そういった時に、公文公は「なぜここで間違えたのだろう」と問題を見返して、本人が自習しやすいように改良していきました。
「小学生のうちに方程式」という目標を小3の学年末に達成した後、「小学生のうちに微分積分まで」という新たな学習計画を立てて、その計画に沿って喜んで学習を続けた毅さん。この学習効果を確信した公文公は、近所の子を集めて自宅で算数教室を開き、それが教室展開につながっていきます。学ぶ子が増えていくにしたがって、教材の改訂ポイントを子どもから学んでいきました。長男の時はうまくいったけれど、この子の場合は違うからこうしよう、と子どもたちから学びながら少しずつ教材をスモールステップにしていって、今も改訂をし続けています。

公文公会長
隂山:あたかも体系ができあがっているように思える公文式でも、今もそうして改訂が続いているわけですよね。
田中:はい。今も改良し続けています。
隂山:公文さんが高校の数学の先生だったということもものすごく大きいと思います。山の頂上にいて、ふもとがどうなっているかわかっている公文さんだから、一本道が見えたんだと思います。改めて思ったのは、公文式は上から下までを見通して最短距離を行かせていることです。だから子どもが自分からやる気になる。これはすごく大事です。
子どもが勉強好きになる方法はたったひとつ、「ちょっとやっただけですごく伸びた」という体験をさせる、これしかないと思っています。そのためにもカリキュラムを念頭に置いて、最も効果的なところに取り組む…私はひょっとしたら知らない間にそれを公文式から学んでいたのかもしれません。その子にフィットした教材なら子どもは自主的に学び出しますよね。
田中:例えば公文では、多くのお子さんの場合、入会すると本人の学年よりも下の教材から始めます。小学校2、3年生なら親としてはかけ算やわり算をやってほしいでしょうが、たし算や“かず数え”から始めることもあります。子どもが「これだったら楽しくできる」と思えるところから始めると、どんどん進み、顔つきが変わってくるんです。
隂山:わかります! なぜ今の親御さんは上をやらせたがるのでしょうね。逆なんですよね、つまずいたら下に戻らなきゃいけないんです、思い切り下に戻る。小5、小6で悩んでいる方は、小3、小4レベルに戻ってはいけません。小1まで戻らないと! やっぱり公文式と行き着くところは同じですね。
基礎学力は生まれついたものではない
「自信と自己肯定感」が力の源に
隂山:私は、そもそも基礎学力とは、知能、つまり脳の性能だと思います。まっさらなコンピュータみたいなものです。今のコンピュータと昔のコンピュータは違うように見えるかもしれませんが実はまったく同じです。違うのはたったひとつ、速度です。その結果、人類が生み出したすべての知恵というものを瞬時に引き出せるようになってきています。

一方、人間の脳の情報処理は、読み書き計算の反復学習によって一気に高まっていくのは確かです。先ほどの4年連続担任した“手がつけられない賢さをもった子どもたち”は、知能検査の数値がものすごく上がっていました。脳の性能は生まれついたものではなかった。それは大きな衝撃であり、希望であり、可能性だと思いました。
田中:基礎学力は、将来自立して様々な方向へと進んでいくためにも必要なものですね。忘れた知識はまた覚えればよく、それよりも何回も何回もくり返して、自分のものにする、それを基礎学力と呼べるのではと思います。
隂山:公文さんは、発達障害があるお子さんでもどんどん伸ばしていっています。そういう子に「読み書き計算の反復をしたらすごく成果が出るだろうな」と思っていたら、すでに公文さんがされていた。脳そのものの可能性を広げていく、高めていくところに気がつかれた。さらに対象を高齢者にも広げていらっしゃるのは、「学習というものは、人間の可能性や生き方そのものを変えられるんだ」ということに公文さんが気づかれたんだ、と思って悔しかったですね(苦笑)。
田中:創始者がいろいろなお子さんをお預かりするようになって直面したのは、個人差・能力差です。誰にでも同じように対応しようとしたら平坦な教材プログラムだったかもしれませんが、創始者は、長男を指導してから会社を設立するまでの間、個人別・能力別に対応しようと、その子その子に合わせたちょうどの教材を手で写しとり、それを渡していました。個人別にしていくと最初につくった教材では足りなくなり、幼児向けの教材に幅を広げ、教材のステップも細かくしていきました。
隂山:私たち学校の教師は違う学年の学習範囲に手を出すことはできませんので、公文さんはすごいな、と思っていました。苦手意識は脳を動かなくする、子どもたちは失敗経験から意欲を失う、自信を失う。だから絶対に苦手意識をもたせてはいけません。公文さんは無学年にした段階でそこをとっぱらった。今、「自由進度学習」が学校教育でも言われていますが、公文さんはずっと前からやっていらっしゃいますよね。教科書に子どもを合わせていくのではなくて、子どもに合わせてどういう教材を提供するかということをなさっています。

田中:子どもたちが自分を超えるというのが大事で、ひとつの目安として自分の学年を越えていくとたくましくなっていく。基礎学力は生まれもって変わらないものではなく、鍛え続けていくものです。となると、それを支える環境、具体的には読書や教育者の存在が大きいのではないかと思っています。公文には「悪いのは子どもではない」と我々を戒める言葉があります。目の前にいる子どもが、どんなに学習意欲がないように思えても、悪いのは子どもではない。教材の進度を調整するなどその子に必要な環境を整えていけばいい。公文の教室や指導者はそういう役割を担っていますし、隂山学級もまさに同じだと思います。先生の意志、子どもに向かう姿勢があると子どもは一気に花開きます。
また、間違っても自力で直して100点にする、できたところを親がほめてくれる。その中で子どもの「自信と自己肯定感」が生まれ、それが大きなエネルギーの源になります。
隂山:生まれもったものより決定的なものは「学習」。必要なのは親御さんの愛情であり、子どもを信じる力。くり返しになりますが、公文公さんは高校教師の立場から小学校教育を眺め、子どもたちにずっと指導していたというところで、学習指導者としての王道を歩まれ、切り拓かれてこられた。尊敬しています。
 |
後編のインタビューから -指導者とは環境づくりのサポート役 |

























