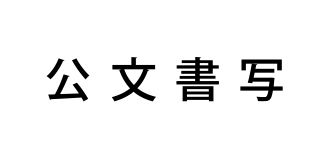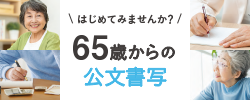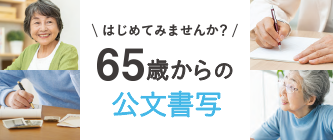公文囲碁ニュース囲碁で育む子どもたちの非認知能力
~兵庫県宝塚市の取り組み
- TOP
- 公文エルアイエル会社情報
- 事業紹介
- 囲碁事業について
- 囲碁で育む子どもたちの非認知能力~兵庫県宝塚市の取り組み
囲碁と、教育界で注目される非認知能力の関係
生涯学習としての価値が注目されている囲碁。その教育的効果をいち早く認め、幼稚園、保育所での保育に導入してきた兵庫県宝塚市の取り組みが広まりを見せている。

囲碁には人が生きていく上で大切な「諦めない気持ち」や「思いやり」、「忍耐強さ」などの非認知能力を育む力がある。その信念の下、活動に深く関わってきた同市教育委員会学校教育部幼児教育センター所長三ヶ尻桂子さんはその始まりをふり返る。

「『囲碁で遊ぼう!Let’s 碁』が導入された2018年、私は宝塚市立丸橋幼稚園の園長でした。導入にあたってモデル園を募集しており、その一環のデモ授業(教員対象)に参加したらとても楽しくて、これは子どもたちも楽しめるのではと思いました」
当初抱いた「子どもには難しいのでは」という一抹の心配を払拭したのは、指導にあたった関西棋院の藤原克也六段の指導法。「(藤原)先生がとにかくたくさん褒めてくださる。どんなところに(石を)打っても絶対に否定せず、必ず前向きな言葉がけをしてくださいました。園の方針として『自己肯定感を育てる』ことを大切にしているので、これは良いと思いました」
自己肯定感とは「囲碁遊び」が育成目的とする非認知能力の1つ。「非認知能力はいわゆる学校のテストでは測れない、社会生活に欠かせない能力です。『自己肯定感』もそうですし、『コミュニケーション能力』や『あきらめない気持ち』『他者への思いやり』『主体性』『忍耐力』などもそう。この言葉が注目される前から、就学前はそういう力を育てる大事な時期という認識がありました」
「囲碁遊び」のどんなところが非認知能力を育むのに良いのか。「例えば対局前の『お願いします』と対局後の『ありがとうございました』。藤原先生は『相手がいるから楽しめる。だからありがとうだね』と、子どもたちにも分かりやすく『ありがとう』の大切さを教えてくださる。また、子どもたちの手を絶対否定しない。否定されず肯定される環境だと、子どもたちは積極的になって自分からやりたいと思ったり、自分の考えで石を置けるようになります」
囲碁は勝ち負けがあるが、負けることすら成長にとって「いいこと」になるという。「負けても諦めずにがんばる経験を重ね自信をもつと次第に大丈夫なんだと思えるようになるんです」

指導者である藤原六段も「楽しいと思ってもらって、自分に自信をつけてもらうことが一番です。子どもたちを強くしたいとは思っていません。強くなったらうれしいけれど、それよりいろんな経験をしてほしい。人とのつながりや、勝った時、負けた時の気持ち、相手への感謝、思いやり…。そうしたことを子どもたちに伝えたい」と話す。
囲碁の技術習得や上達そのものではなく、あくまで子どもたちの「生きる力」につながる非認知能力の育成が「囲碁遊び」導入の目的となっている。
未就学児でも楽しめる囲碁
囲碁はルールがシンプル。石はどこにも置けるから、自分で考え、自分で好きなところに置ける。そんな特徴が、身近に楽しめる遊びとして、囲碁が子どもたちに受け入れられ、広まっていった要因のようだ。「囲碁で遊ぼう!Let’s 碁」のルーツとなった現関西棋院常務理事榊原史子六段の子育て中の活動も、囲碁の普及ということではなく、通っていた保育園や、近くの児童館などごく身の周りの地域貢献から始まった。

この児童館の館長に「せっかくだから囲碁イベントをもっと広めませんか」と声をかけられたのが今から15年ほど前。中山寺という宝塚市の有名なお寺で親子の囲碁入門講座を始めたのが評判となり、やがて宝塚市の教育行政の目に留まる。この講座が「囲碁で遊ぼう!Let’s 碁」と名前を変え、市の全面バックアップの下、全市に広がることとなったのには、榊原六段の人間関係が大きく寄与したようだ。
「背中を押してくださった(児童館の)館長さんも、三ヶ尻さんもですし、前市長はご自分が愛好家だったこともあり、囲碁のよさをよく理解してくださっていました。山﨑晴恵現市長も囲碁の教育的効果を認め、後押ししてくださっています」スタートのデモ授業から今日まで長年全指導を担う藤原六段も、榊原六段とは関西棋院で小さい頃からの付き合い。「子どもが好きで教えるのが上手」なのを知っていた、榊原六段の意にかなった指名という。
2018年に始まった「囲碁で遊ぼう!Let’s 碁」は、現在宝塚市立の全園所に導入されている。
現場の反応は当初、どうだったのか。市立宝塚幼稚園の先生たちの声から子どもたちの反応と、その成果の様子がうかがえる。導入前は「難しいものというイメージ」、「高齢の方がする高尚なゲームというイメージ」を抱いていた先生たちも、実際にやってみると子どもたちがすぐルールを理解し、やる気いっぱいで楽しむ様子に驚いたそう。
また、「囲碁遊び」を通して生まれた子どもたちの大きな変化にも着目した。
「始まる前の挨拶、チーム戦でのお友達の応援などで感謝の気持ちや思いやりなど、いろいろなことを学ばせてもらっています。先生にたくさん褒めてもらうことで自信もつけて、恥ずかしがりの子でもだんだんと積極的になっているのがわかります」(園長先生)

「ふだんは集中するのが難しい子も集中していることに驚きました。毎回、『もっと知りたい』という気持ちで先生の話を聞いているのが感じられますし、ルール感覚を身につけられているとも感じます。負けることの大事さを教えられて、囲碁以外の場面でも『負けても次頑張ればいいやん』と負けを受け入れられるようになってきました」(年長クラス先生)
世代をつなぐ囲碁
囲碁には「世代間コミュニケーション」を促す価値もある。宝塚幼稚園が実施した保護者への聞き取りでも「子どもにルールを教えてもらい、家でも(親子で)やってみた」という回答があった。シンプルかつ奥深いゲームである囲碁は年齢に関係なくいろいろな人と仲良くなれる。世代が違っても同じように楽しめる。
宝塚はもともと囲碁の盛んな地域で、先年10月には宝塚囲碁フェスティバル2024が開催され、老若男女たくさんの方が囲碁を楽しんだ。「囲碁遊び」導入を積極推進してきた現市長山崎晴恵さんも父、祖父が愛好家で、囲碁を身近に感じて育った一人。自身が子どもだった昔は、囲碁は男性がするものという風潮があったというが、現在では「囲碁はだれにでも楽しめるもの」という認識が強い。そんな市長は今後の抱負をこう語っている。

「幼稚園、保育所で囲碁を学んだお子さんがご両親やお祖父さん、お祖母さんと一緒に囲碁を打つこともあるでしょうし、地域の中で世代の違う方と対局することもあるでしょう。囲碁を通じて(子どもたちが)非認知能力を鍛え、家庭の中で3世代が仲良くなり、地域の交流も進む、そのようになっていったらいいなと思っています」