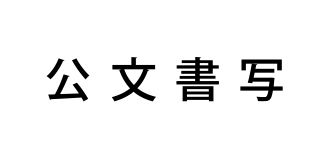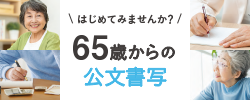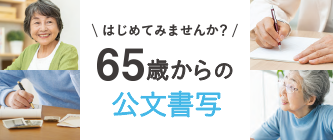公文囲碁ニュース東大囲碁部のメンバーが語る
~囲碁の魅力と効用、その未来
- TOP
- 公文エルアイエル会社情報
- 事業紹介
- 囲碁事業について
- 東大囲碁部のメンバーが語る~囲碁の魅力と効用、その未来
文化庁の「令和6年度生活文化創造・戦略展開事業」に公文囲碁を入り口とした囲碁の各種普及事業が採択されている。公文エルアイエルは、囲碁のさらなる普及推進のために様々な方の声を集め、その魅力を広く発信していきたいと考えている。
今回は東大囲碁部の皆様に登場願い、囲碁好きの学生視点から、囲碁の魅力と効用などについてそれぞれの私見をうかがった。出席いただいたメンバーは次の4名。
-

藤野英輝さん
教養学部文化一類
囲碁部部長 -

川口飛翔さん
国際関係論
学生大会多数優勝の実力者 -

芝野すずさん
農学部獣医学専攻
囲碁は兄弟の影響で始め、
高校生で大好きに -

箕輪英介さん
教養学部理科一類
大学の授業で囲碁に触れて囲碁部へ
話し合いは、まず「囲碁の魅力」はどんなところか、から始まった。(以下( )内敬称略。)
1.囲碁の魅力って何だろう
囲碁はその人の個性が出るゲーム
まず最初に挙がったのは「(対局者の)個性が出る」(藤野・川口)、という意見。「布石にバリエーションが多くて人によって全然違う碁になる」といったところが囲碁の面白さだと藤野さん。
「個性」とは、勝負に勝つ「強さ」といった単純なものではない。囲碁は勝負事だが、「勝てば嬉しいですけど、負けたらつまらないということもない」(箕輪)からだ。「反省を生かして次に繋げられれば、負けもまた勝ちにつながる」(箕輪)し、「上手(うわて)と打つと負けることも多い」が、「相手の手で面白いなっていうのがあるとそれだけで嬉しい」(芝野)こともある。「面白さは勝ち負けだけではないなって思います」(芝野)
囲碁以外のゲームにも詳しい箕輪さんによれば、囲碁はカードゲームや麻雀のように「確率が関係」することのない「完全情報ゲーム」。その 方で「棋風(囲碁の打ち方のスタイル)の相性が良いと上手(うわて)にも勝てたり、すごく劣勢でも一発逆転の手を見つけられたり、運の要素はないんだけどそういうことが起こるのも面白い」(芝野)
囲碁は、地域を越え、世代を越えて交流できる
また囲碁にはコミュニケーションツールとしての魅力もある。「囲碁のルールは世界共通なので、言葉が通じない海外の人とでも検討(対戦のあと行う振り返り。盤上の石を示したり置いたりすることで話さなくても意図が伝わる)で交流できます」(川口)
世界大会にも出場している川口さんは、そんな経験も豊富。「メキシコとか中南米とか、本当に言語が分からない方」との対局もあるそうだが、「何時間もその人と対峙するってなかなかない濃密なコミュニケーションなので、一局打っただけで一日中一緒に遊んだのと同じくらいすごく分かり合えることもあります」
国内でも、全国大会などではいろいろな地方の人との出会いがある。「学生の全国大会でいろいろな地方の子と顔見知りになって、自然と仲良くなることはありました。同世代の方と仲良くなるという意味で囲碁はいいコミュニケーションツールですし、年配の方と対局することもあって、世代間交流の意味でも優秀だなと思いますね」(芝野)
囲碁は地域を越え、世代を越え、人と人とをつなぐ役割も担っている。

2.囲碁をすると頭が良くなる?
記憶力、思考力、洞察力
次の話題は「囲碁の効用」について。特に東大生の皆さんに訊いてみたいのは「囲碁をすると頭が良くなる」これは本当か、ということだ。
ところで「頭が良い」とはどういうことか。彼らの見解はこうだ。「賢さには2つの状態があって、記憶力が良く物事を知っている状態と、思考力がある状態があると思います。囲碁が強い人は特に思考力がある人が多いかな」(藤野)
「それと関連して、多面的な視点から洞察できる能力が僕が思う『賢さ』でしょうか」(川口)。「多面的な視点から洞察できる能力」との類似で「囲碁で賢いと思うのは全体が見えていること」(箕輪)という意見も出た。
受験・試験勉強と囲碁
囲碁で養われる能力として「思考力」「多面的洞察力」などの見解が語られたが、では実際の受験などの場面で、囲碁が役立ったと思ったことはあるだろうか。
これには肯定的な意見が相次いだ。「まず集中力が身についたと思うし、何もない盤上から自分で勝利までの構想を描いてそれを実現しようとする」経験が、「試験でいい点を取るためにどう勉強するかや試験時間内でどう最大効率で点を取るかを考える上で役に立った気がします」(藤野)
「目標があって、それに向かって努力して、努力が結果につながっていくというのは囲碁も勉強も同じ」(川口)
一般的に高度な試験問題ほど記憶力だけでなく、思考力や応用力が試されることが多い。囲碁で「考えたり工夫したりする」楽しさを知り、上達を重ねてきた経験が、試験で問われる力を自然と身につける役に立ったとは言えそうだ。「囲碁をすれば頭が良くなる」と短絡的には断じられないにせよ、囲碁で身につく諸能力は試験にも役立つことは間違いない。
3.囲碁が広がっていくには?
囲碁の未来
残念なことに、現状囲碁人口は減少傾向にある。3つめの話題として、「囲碁の未来」のために、今後の普及に必要なことは何か。若い皆さんの意見を訊こう。
まず藤野さんが囲碁人口減少の原因を指摘する。「今時はスマホで手軽なゲームがたくさんある」。その中で「囲碁は一局にかかる時間が長いし、ルールを覚えて打てるようになるにも時間がかかる」。競合する娯楽の多さが根本原因。これは他のメンバーも同意見。
では、どんな人にどうすすめていけばよいのか。もともとゲーム好きだった箕輪さんは大学の囲碁授業がきっかけで始めた。それを受けて「ゲームが好きで考えるのが好きな人」は「ハマれる素質がある」と川口さん。
芝野さんはもともと少しやっていた人中心に「女子部員を集めたいと思って勧誘」しているが、「特に始めた直後は同じくらいの棋力の人が複数いるのが重要」だそう。
勧誘文句としては「日本の伝統文化」(藤野)、「(海外の人との)コミュニケーションツール」(箕輪)、「囲碁は一生の暇つぶし」(川口)などの意見。
多くの意見が出る中、アプローチの切り口としてやはり挙がったのは「知育」と「認知症予防」だった。
「知育とか認知症予防で興味を持ってくださる方もたくさんいそう」(芝野)
「子どもにアプローチするのが重要だと思うし、知育的なことを打ち出すのが効果的だと思います」(川口)

公文囲碁を通じた囲碁の普及への貢献
とは言え、きっかけづくりとともにルールを覚えてから対局を楽しむところまでのサポートが重要なのも囲碁普及の課題。このためのツールである「公文囲碁」についての感想をうかがい、話し合いを締めくくった。
「ステップが明確で公文式ならではの良さがあるなと感じました」(川口)
「お子さんでも飽きない工夫がいろいろあると感じました」(藤野)
「打てるようになるまでのモチベーションをこうしたツールを使ったり、友達と始めたりすることで維持できれば、囲碁を趣味にする人が増えていきそうですね」(芝野)