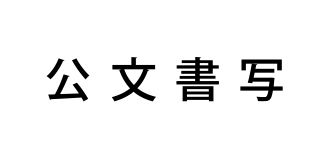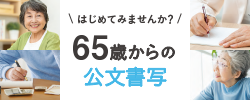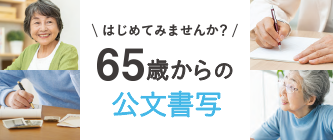スペシャルインタビュー囲碁棋士 一力遼さん
「学習と囲碁」を語る
~学校の勉強と囲碁の類似点
- TOP
- 公文エルアイエル会社情報
- 事業紹介
- 囲碁事業について
- 囲碁棋士 一力遼さん「学習と囲碁」を語る~学校の勉強と囲碁の類似点
文化庁の「令和6年度生活文化創造・戦略展開事業」に公文囲碁を入り口とした囲碁の各種普及事業が採択されている。公文エルアイエルは、囲碁のさらなる普及推進のために様々な方の声を集め、その魅力を広く発信していきたいと考えている。
今回ご紹介するのは、日本囲碁界の第一人者である一力遼さん。
現在日本の7大タイトルのうち4冠(※)を保持し、昨年は日本勢19年ぶりの主要国際棋戦優勝で脚光を浴びた、まさに棋界のトップランナーである。一力さんはまた、高校(都立白鷗高校)、大学(早稲田大学社会学部)へと進学後、現在は家業の新聞社「河北新報社」取締役として経営にも携わるなど、囲碁と学業・実業を両立させてきたキャリアの持ち主でもある。
※タイトルは記事掲載時

こんな一力さんは、囲碁の練習や学校の勉強をどう進めていたのだろう。御本人に子ども時代をふり返っていただいた。
子ども時代の囲碁と学校の勉強
「(囲碁に関しては)特別なことはしていないと思います。詰碁(練習問題)と棋譜並べ(上手(うわて)の対局を勉強すること)をし、教室などで同じくらいの相手とたくさん対局しました」
「特別なことはしていない」とはいっても、そこまで強くなるからには練習量は並大抵のものではなかったにちがいない。実際「勝ってレベルアップするのが楽しくて四六時中やっていました」という子ども時代と今とでは、「あんまり変わっていないかもしれませんね」と一力さん。
では学校の勉強の方はどうだったのか。「4、5歳の頃から数字と算数が好きでした。小学校で覚えているのは当時の校長が数学好きだったのか、校長室の前に算数の問題が張り出されていたんですよね。パズル的な面白い問題が多くて、そこの問題を解くのを楽しみにしていました」
一力さんの数字好きは有名なようで、3桁の素因数分解が即座にできたり、生年月日を言うとその日が何曜日か当てられたりするそうだ。
学校の勉強と囲碁の類似点
「両親から勉強するように言われた記憶」はないという一力さん。こうした話から、囲碁も算数もごく自然に、「楽しく」、「好き」に勉強していた様子がうかがえる。囲碁と学校の勉強の2つには、どんな共通項があるのだろう。
「対局では集中力が不可欠です。局後はどこが良くてどこが良くなかったのかフィードバックをし、足りない部分を見つけてどうすればそれを克服できるのかアプローチを考えます。集中力と適切なフィードバックと課題に向けたアプローチ、これらは勉強全体に当てはまることです」
囲碁で培った方法論が学校の勉強にも応用できるというわけだ。「自分の中で達成度を数値化し、課題を1つ1つクリアしていく感覚は(囲碁も勉強も)同じですね。例えば私は詰碁を毎日1問1分と時間制限を設けて30問程度解いているのですが、試験勉強も漫然とするよりも時間制限を設けて理解度を測る方が効率がいいように思います。また、対局が控えている場合はだいたい2週間前くらいから対戦相手の研究を行って、どういう布石(最初の打ち方)にするかを決めます。試験前も2週間前くらいから過去問などで傾向と対策を立てて本番に挑むので、似ている部分は大きいと思います」
KUMONでは時間を計って教材を学習することで、一人ひとりにあった「ちょうどの学習」を追求している。一力さんのお話はそんなKUMONの考え方ともつながるものがあるようだ。
囲碁の魅力にハマる
囲碁の魅力についてさらに一力さんは語る。「最初は特に『勝ってステップアップしていく』ということが楽しかったのだと思います。また、私はその時々でいい指導者に恵まれました。囲碁のゲーム性でいうと、定石化されている部分が少なく未知の部分が多いというところにハマったんだと思います」
特にPRしたい点としては「とても奥が深くて面白い」ところ、「ルールがシンプルで自由度が高い」ところ、また「勝ち負けの幅が半目(最少差)から100目以上の大差まで大きいというのも囲碁ならではです。100-0ではなく、60-40もあり得る、どこかで損をしてもその損を上回る得をすれば良いというような俯瞰的な判断が求められます」
経営者などに囲碁ファンが多いのも、そうした囲碁の特性と無縁ではない。「特に人と人との対戦では自分がどんなに定石通りに打っていてもどこかで必ず定石を外れます。囲碁は未知の局面での対応力、経験やヨミを駆使した応用力を求められるという点でも魅力的です」
囲碁で「負けること」を経験する
囲碁は全世代におすすめの娯楽だが、一力さんは「特にお子さんや学生の方など、若い世代の方にやってほしい」と言う。「囲碁に打ち込むことで集中力や総合的な判断力、応用力が育まれますし、それは社会に出た後にも役立ちます」
そして「あと、個人的に思う」こととして、「負けた時にどうするか」が重要だと、興味深い指摘をつけ加えた。
「囲碁は必ず勝敗がつきます。当然負けることもあるわけですが、その時に相手を認め、自分の手を反省すると成長につながります。最近は教育現場で勝ち負けをつけないことが多いと聞きますが、人生の中で競争は避けて通れません。負ける経験がないまま明白な結果が出るものにぶち当たるとメンタル的に大変なのではないかと思います」
囲碁で「負けること」を経験しておくと、別の場面で上手くいかない時も気持ちを切り替えて前に進んでいけそうになれる。囲碁にはそんな効用もあるようだ。
入門の現場では「ルールは簡単でも打てるようになるまでが難しい」と言われがちな囲碁であるが、これから始めようかと考える人に向けて一力さんは最後にこう語った。
「囲碁は非常に面白いゲームです。年齢、性別、国籍関係なく一生楽しめますし、判断力や応用力も身につきます。ぜひお近くの囲碁教室に行ったり、『公文囲碁』などの入門プログラムを活用したりして、始めてみていただきたいです。そして、最初は難しく感じても後からどんどん楽しくなってきますので、安心して続けてほしいと思います」