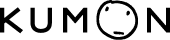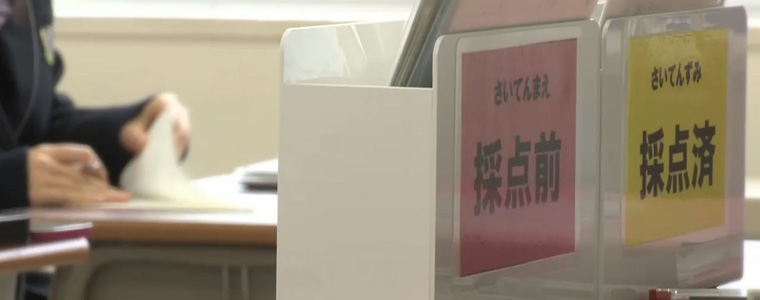
学校での公文式
学校で活用される公文式
机に向かって集中し続ける力をいかに生み出すか
〜教室に静まりが生まれた〜
導入した学校の先生の声

公文式学習は「働く姿勢」にも通じる力を育てる
このような学校や施設の方々の声を多く受け、公文式導入の現場で何が起こっているのか?を明らかにする共同研究が2015年にスタートしました。
この共同研究では、ある自治体の協力を得て、公文式を導入して10年以上が経つ学校を「学習群」、 公文式やその他の民間教育を導入していない学校を「非学習群」として公文式学習法の効果測定をしました。 測定時に使用したのは、学力テストとして使われている学習習熟度テストと自分で考える力を測る PTS(Proficiency Test of Self-learning skills)という公文が開発したテストです。
測定の結果から、「集中力が向上した」「粘り強くなった」といった学習者に起きた変化は、作業できる量とスピードを表す「処理力」、 例題から法則を考える「類推力」、軌道修正できる「修正力」が向上したことで起きたということがわかりました。 調査結果の分析に関わった労働経済学がご専門の松繁寿和先生(大阪大学大学院国際公共政策研究科教授)によると、 これらはそれぞれ、経済学の観点でいうところの「ハード・ワーキング(熱心さ、仕事への情熱)」、「ロジカル・シンキング(論理性)」、 「コミットメント(課題遂行能力、粘り強さ)」にあたると言います。松繁教授は特に「類推力」について着目し、公文式と類推力の関係について次のように説明してくださいました
教育現場の先生方の想い「生徒たちには自己肯定感を高めてほしい」
公文式を導入してくださっている学校や施設の方々には、「自分で問題を解けるという喜びを感じて自己肯定感を高め、 社会に出た時にいろいろなことにトライできるようになってもらいたい」という共通の想いがあります。 公文式がその一助として貢献できるよう、今後も学校や施設の方々と力を合わせて取り組んでいきます。
(2017年1月)