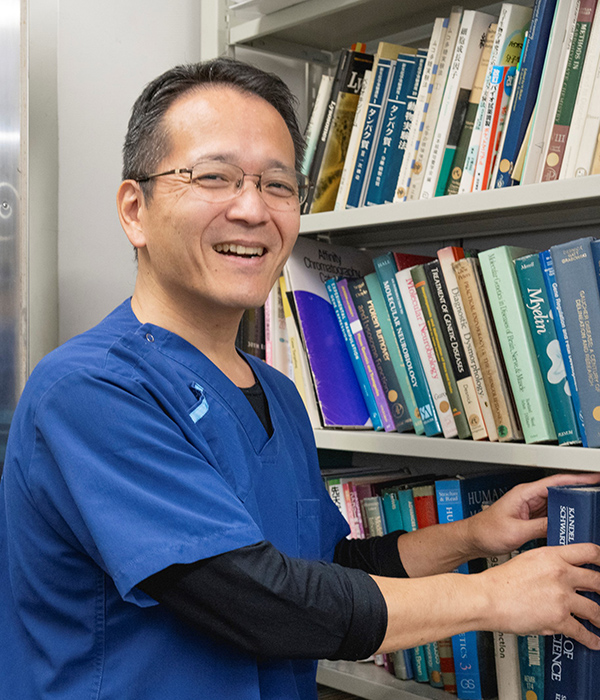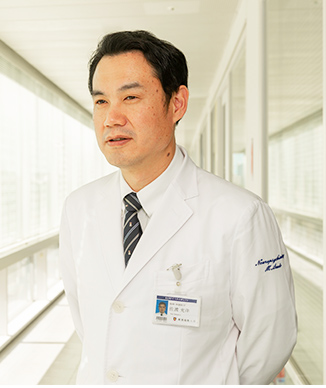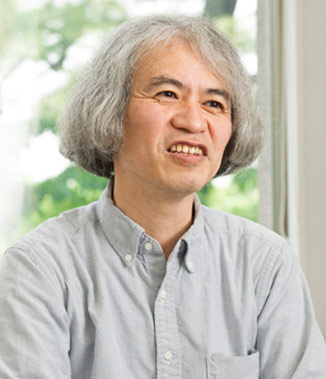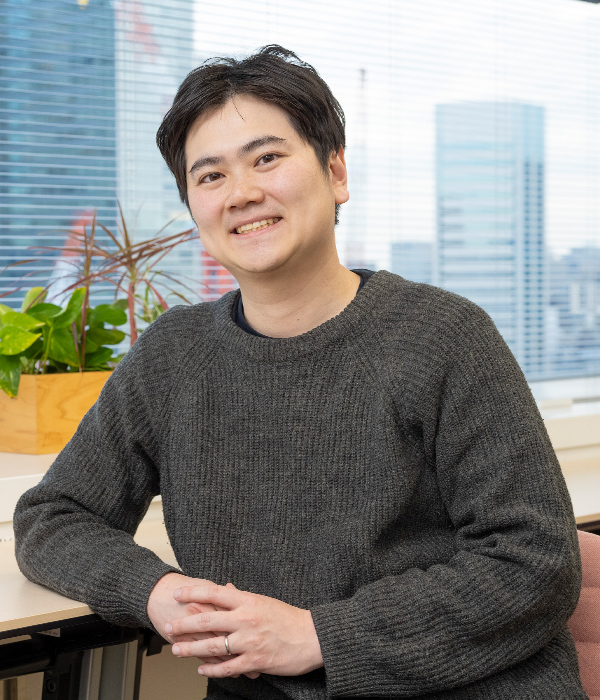MBA取得をあきらめたことで大きな転機につながる

その民間企業(前編参照)の法人営業という仕事で成果をあげ、高い評価をもらえるようになった頃、社内の留学生試験に推薦され、合格することができました。当初は、アメリカのビジネス・スクールに行って、MBA(経営学修士)を取得しようと考えていたのですが、TOEFLやGMATの試験に備えながら、渡米の準備をしているとき、また、大きな人生の分かれ道がやってきました。取引先企業の懇意の役員の方から、「海外出張に同行して欲しい」と請われたのです。「あいにく、その出張時期に、動かせない用事が入っていますので」と二度お断りしたのですが、「どうしても同行して欲しい」と三度目の要請を受けたのです。
ここまで熱心な先方の気持ちに触れると、「これも何かの天の声だろうか」という思いが心に浮かび、TOEFLやGMATの試験を受けるのを諦め、その役員の方の海外出張に同行したのです。ヨーロッパ各地の原子力施設を回り、最後の訪問先がアメリカにある世界最大の技術系シンクタンク・バテル記念研究所でした。そして、この訪問が契機となり、この研究所から働かないかとの誘いを受け、結局、ビジネス・スクールに行くのをやめ、このバテル記念研究所で客員研究員として働くことにしました。いま振り返れば不思議な配剤ですが、その役員の方とのご縁が、私の人生の大きな転機となったのです。
このアメリカのシンクタンクで2年ほど働いた後、日本に帰国しましたが、バテル記念研究所においてシンクタンクの仕事に強く惹かれたことから、まもなく、勤めていた民間企業を退職し、日本で新たに設立されるシンクタンク、日本総合研究所の創業に参画しました。
また、この転職をしたもう一つの理由は、先ほど(前編)お話ししたように、私のライフワークが、人類社会が直面している「5つの問題」(人口爆発・食糧不足・資源枯渇・エネルギー危機・環境問題)を解決することだったからです。もとより、この問題の解決のために原子力工学を学んだわけですが、原子力エネルギーについては、その技術的な問題以上に、人的、組織的、制度的、文化的、そして社会的な問題を解決する必要があることを感じていました。
私の博士論文のテーマでもある「高レベル放射線廃棄物の最終処分」についても、すべては社会的受容、つまり国民がそれを認めるかどうかにかかっていることを感じていました。そうした意味で、私の問題意識は、原子力の技術的なところを越えて社会科学に移り、その問題の解決に取り組むことを志向したわけです。
ただ、そうした思いもあって新たなシンクタンクの設立に参画したのですが、この日本総合研究所を立ち上げた後は、原子力関係のプロジェクト以上に、新産業育成のプロジェクトに取り組むことが自分の使命であるように思えてきたのです。そのため、この日本総研の10年間においては、数々のベンチャー企業や新規事業の育成に力を尽くすことになったのです。
しかし、いま振り返ると、私にとっての本当の人生の転機は、民間企業への就職でも、米国シンクタンクでの勤務でも、新たなシンクタンクの設立でもなく、1983年に与えられた「生死の体験」でした。
「挫折は天の配剤」

確かに、振り返れば、大学に研究者として残れなかった挫折や、就職した企業で希望する研究所ではなく営業部門に配属された挫折など、人生において、何度も挫折を体験してきました。しかし、どの経験においても、私は、その挫折を「天の配剤」だと思ってきました。なぜなら、その挫折の体験を通じて、必ず、人生における大切なことを学ぶことができるからです。そして、私のこれまでの人生において、最も大きな挫折は、32歳のときに医者から癌を宣告されたことです。
「もう長くありません」と医者から余命宣告をされてから、文字通り、地獄の日々でした。自分の命が失われていく恐怖感で、夜中に目が覚め、それは悪夢ではなく現実であることを思い知る。そんな筆舌に尽くしがたい苦しみの日々を送りました。医者から見放され、誰も救ってくれない絶望感のどん底において、両親が勧めてくれたのが、ある禅寺に行くことでした。その寺に行った人の多くが、病気が治って戻ってくるとのこと。藁にもすがる思いで、その寺に行くことにしました。
しかし、行ってみると、その寺には特別な治療法も何もなく、「献労」と称して、毎日、農作業をするだけでした。ただ、その寺に集まっている人たちは、みな病人。腎臓をやられ、水膨れの足で、必死に献労に取り組む人。献労のための鍬を渡されても、足を患っているため、その鍬を杖にして、坂道を必死に登っていく人。その姿から、大切な何かを感じ始めたころでした。
その寺に来て9日目。ようやく禅師との接見の機会を得ました。私は、この禅師から救いの言葉、癒しの言葉を聴けるものと思い、いまの私が、いかに辛い状況か、絶望的な状況かを切々と訴えました。しかし、その禅師は病気の治し方を話すわけでもなく、私を励ますわけでもなく、ただ、こう言い切ったのです。
「そうか。もう命は長くないか・・・。だが、一つだけ言っておく。人間、死ぬまで命はあるんだ」
一瞬、何を言われたか分かりませんでしたが、帰りの廊下を歩きながら、はっと気がつきました。「そうだ、人間、死ぬまで命がある。それにもかかわらず、自分はもう死んでいた。死の恐怖の前で、もう生きることを諦めていた。もう心が死んでいた。」 そのことに気がついたのです。
そして、その瞬間、禅師が付け加えて言った言葉の意味が、胸に突き刺さってきました。
「過去は無い。 未来も無い。 有るのは、永遠に続く現在(いま)だけだ。 いまを生きよ。 いまを生き切れ。」 その言葉が、胸に突き刺さってきたのです。
振り返れば、医者から宣告されてからの何か月、私は、いまを生きてはいなかった。「なぜ、こんな病気になってしまったのか」と過去を悔いることに時間を費やし、「これから、どうなってしまうのか」と未来を憂うことに時間を費やし、決して、いまを生きてはいなかったのです。
しかし、この禅師との接見によって、私の覚悟が定まりました。不思議なことに、「死」を受け入れられるようになったのです。「ああ、明日死のうが、明後日死のうが、構わない。それが天の定めであるならば、仕方がない。ただし、死の恐怖のために、今日という一日を疎かにすることは、絶対にしない。与えられた今日という一日を、生き切ろう。命の限り、生き切ろう。」 そう心に定めたのです。そして、そう覚悟を定めた瞬間に、不思議なことに、死の恐怖は消えていったのです。
そして、1983年のあの日以来、与えられた一日を精一杯に生き切るという生き方を続け、気がつけば、32年の歳月が経っていたのです。
この話をすると、「それは、大変な体験でしたね」と言われます。しかし、もし我々が人生というものを深く見つめるならば、誰もが同じなのです。実は、我々は、誰もが明日も知れぬ人生を生きている。「平均寿命」という言葉に騙されていますが、実は、我々、誰もがいつ死ぬか分からない。その意味では、癌の宣告を受けようが受けまいが、誰にとっても今日しかないのです。「いま」しかないのです。その「いま」を、どう生きるか。それこそが問われているのです。
そして、もし我々が、「いまを生き切る」という生き方に徹したならば、自分の中から「生命力」が湧きあがってくる。そして、不思議なことに、自分の中に眠っていた才能が開花し始めるのです。本来、人間というものは、退路を断ったとき、潜在的な能力が大きく花開くのです。
むしろ、大きな落とし穴は、自らの内にある「自己限定」の意識でしょう。「俺はもう60歳を越えたし・・・」「技術はわかるけど、営業は苦手だ・・・」といった形で「自己限定」をしてしまう。そして、「自己限定」の意識が心の奥深く固着すると、その意識通りの限定された人生になってしまいます。その意味で、KUMONの創始者、公文公さんは、心底、人間の可能性を信じていた。だから、KUMONが掲げる「自己肯定感」とは、ある意味で、「自己限定をしない」という意識を、子どもたちの心に育んであげることなのですね。
子どもたちには「3つの真実」を見つめて歩んでほしい

いまの時代、これからの時代に、親が子に伝えるべき大切なことのひとつは、「死生観」だと思います。拙著『未来を拓く君たちへ』(くもん出版)でも述べましたが、子どもたちには、「人は、かならず、死ぬ」「人生は、ただ一度しかない」「人は、いつ死ぬかわからない」という人生の「3つの真実」を見つめながら歩んでほしいと思っています。昔は親子孫の三世代で住む家が多く、日常のなかに「死の看取り」があり、子どもたちは、自然に「死生観」を学んでいったのですが、いまは、親から子どもたちへ伝えるべき時代になりました。
この「3つの真実」を見つめることは、決して、暗いことではありません。命に終わりがあることを知り、一日一日を生き切ろうとの覚悟を定めて歩む人生は、素晴らしい密度の人生になっていきます。「人生の長さ」は、天が決めるものですが、「人生の密度」は、自分で決められるのです。そして、その「密度の濃い人生」は、自然に、その人間の中にある可能性を花開かせていくでしょう。実は、才能の開花というものも、「死生観」を定めているか否かで、大きく違ってくるのです。
私は、家族団らんで食事をしているとき、こう語るときがあります。「こうして皆で楽しく食事をしていても、人生というものは、いつか、ひとりずつ去っていくのだよ。だから、いまこうして家族が集まって楽しい時間を過ごせることに、感謝しよう。そのことの有り難さに、感謝しよう。」と話しています。「有り難い」は、英語では”Thank you.”と訳されますが、実は、その本当の意味は、”It is a miracle.”なのです。すなわち、「奇跡」、何気ない日常の一瞬も、実は、奇跡のごとき「有り難い」一瞬なのです。
子どもたちには、決して「自己限定」をせず、「自己肯定感」を心に抱きながら、いまという一瞬を精一杯に生きてほしいと思います。しかし、その生き方を子どもたちに伝えるためには、まず、我々親自身が、自分の人生と真っすぐに向き合っていなければならない。我が子の心の中に「自己肯定感」を育てようと願うのであれば、我々親自身が、「自己肯定感」を抱いているかが問われるのです。
すなわち、子どもの成長を支えるということは、親自身が成長していくことに他ならないのです。一回限り与えられた何十年かの人生において、人間として命尽きる、その最後の瞬間まで成長していくという、その「覚悟」を伝える。その後「姿」を見せる。それが、教育というものの究極の形だと思います。
されば、我々親に問われるのは、自分が子どもに何を語るかではなく、自分がどのような生き方をしているか、そのことに尽きるのです。まず、親が、一回限りの人生を、精一杯に、そして一生懸命に生きる。その姿を見せることができるならば、子どもには不思議なほど、その生き様が伝わるのです。そして、その子どもは、最高の人生を送ることになるのです。
私の両親は、名もなく慎ましく生き、去っていきましたが、子どもたちに、その姿を見せてくれました。その姿が、この一人の未熟な人間を、ここまで導いてくれたのです。そのことへの感謝の念は、終生、尽きません。
 |
前編のインタビューから – 母が育んでくれた“自己肯定感”、父から教えられた“学びの姿勢” |